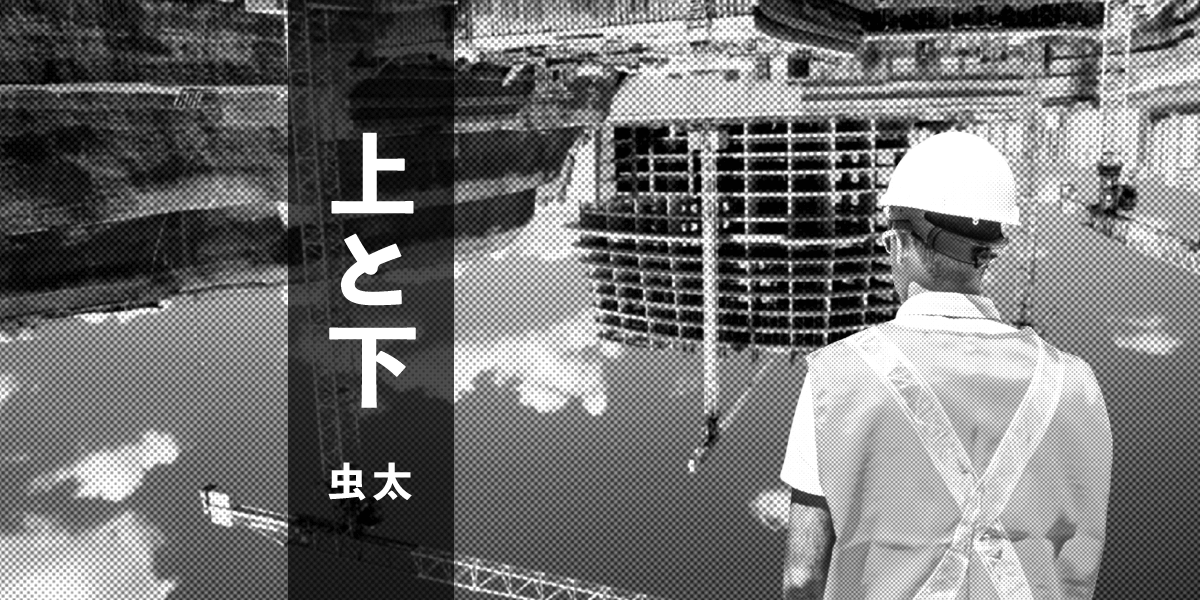先行公開日:2022.1.29 一般公開日:2022.3.5
虫太「上と下」
7,771字
ピリッと頭のてっぺんに痛みが走り、目が覚めた。アルマンは壁にもたれて、知らない部屋に立っていた。目の前には白い壁。そこにステンレスの照明、左右には垂れ幕。清潔そうだが、どこか均衡を欠いている部屋だ。明らかに、ここ数週間住んでいたあの郊外の従業員宿舎ではなかった。
「そりゃあペテンだよ。騙されたんだ、俺たちは」宿舎でイヴァンはそう言っていた。「俺だってドイツで気楽な都会暮らしを想像してたよ。さっさと夕方までには仕事やっつけてクラブで女ひっかけてさ。まさかこんな部屋に詰め込まれるなんて」
「じゃあ、何か反抗しないと…」
アルマンはそう言ってみたが彼は、「どうやってだよ。裁判がしたいのか? 住むとこはどうする?」と問いつめる。
「それは…」
「幻想は終わり。ブルガリアで工事するよりずっと稼ぎはいいんだ。どうせ金が貯まったらすぐ帰る。お前の故郷の国だってそうだろう」
部屋の隅にはゴミが溜まり、向こうでスラブ系の同僚たちが騒いでいる。アルマンはため息をついて、四段ベッドと薄汚れた天井を仰いだ。
白い奇妙な部屋で、彼は最後の日の記憶をたどる。出勤して、現場は駅裏ビル、足場の解体作業、頭に痛みが走ったあと血が流れて意識が…。すると、ここは病院か。
「電動釘打機ですよ」
下から声がした。目を伏せてそちらを見ると、彼の足よりも一段低い床から、ぬっと男が出てきた。その髭を生やした若い男がこちらへ迫り上がってくる。シャツとセーターベストというラフな出で立ちだが、手にしたクリップボードとインテリ風な物腰で医者とわかる。不審な要素はなかったが、布置が異様だった。
「撃ち出された釘が頭頂部に刺さったんです。上体を起こせますか」
医者の足元が見えて、アルマンはしだいに違和感の正体に気がついた。今自分の目の前にあるのは天井だ。彼は壁にもたれて立っているのではなく、ベッドに仰向けで寝ていたのだった。
それからは検査と看護を受ける日が続いた。
「立ったり歩いたりは問題ないでしょう。運動や姿勢保持は新皮質ではなく脳幹などで行われますからね。ただ頭頂葉は遠近感や配置など、高次の処理をしますので…」
医者の話は彼には要領を得ないままだった。巨大なトイレットペーパーのような装置にかけられ、その芯穴が馴染みの場所になるまで何度も入れられた。課題を出され、花瓶やハサミ、自動車のスケッチを描かされたり、医者がもつペンに指示通りに手を伸ばしたりした。目覚めたあとのあの歪みが消えてからは目立った不調はなかった。それでも若い医者は次から次へと彼に細かな検査を課し、結果を見て「ふーむ」と唸ってはまた別のものを試した。「いつ仕事に戻れるのか」と彼はそればかり聞いた。
生のコンクリが顔に撥ねて、アルマンは舌打ちをした。彼が抜けている間に工期は遅れ、現場には疲労と焦りが蔓延していた。彼は引き続き、コンクリから気泡を抜くため鉄筋を軽く叩いた。
現場の職長がアルマンの知らない若いドイツ人と話している。「トマスとかいう訓練生だとよ。お前が病院で寝てる間に来たんだ」宿舎に戻った日にイヴァンがそう言っていた。イヴァンの見立てでは、トマスは親方から計画全体について、アルマンたち外国人作業員よりも詳しく聞かされているそうだ。「大したことねえよ。まだ新米さ」と彼は憎々しげに言っていた。
「こっち側が大幅に高いんじゃないか?」
打設した面を指して職長が今度はアルマンに言ってよこす。「大幅に」というのは3mmかそこらの差のことだろう。「すぐ確認します」と彼は返事をしながらも作業を進め、汚れた顔を拭う暇もなかった。病人として世話をされるもどかしい日々を終えた今、もうこの本塁を守るしかなかった。
機材を運び、まだ壁のないビルの側面から足場に出ると、都市上空の冷たい風が防音幕をはためかせた。隣のビルでは、スーツ姿の男女がガラス窓の向こうで働いている。足元では人々がシラー通りを行き交っているのが小さく見える。ガラスと鉄筋でできた彼らのビルからは街すべてを見下ろせる。ヴィルヘルム様式のファサード、破風屋根の旧市街、教会の尖塔さえはるか下にあり、決して声の届かない距離だ。アルマンは少し下を見渡して今の居場所を踏みしめた。
ビルの外側を数歩あるいたとき、頭に電気が流れたような短い痛みが走った。するとその直後、景色が横転した。
ビルとビルの間に投げ出されて隣のビルへと落ちる、そんなありえない光景が浮かび、死の恐怖が彼を捕らえた。
こんなことになるならハーネスをつけていればよかった、中で作業していればよかった、そもそも今日はまだ宿舎で休んでいれば…。そういったさまざまな後悔が一瞬の内に頭の中を駆け巡る。思考に比べるとあまりに遅い動きで、彼は空いている左手を鉄骨に伸ばした。
体はどこにも落ちなかった。しかしまだ視界は回転を続けている。彼の眼は何か大きな動きを捉えているわけではない。変化を捉えることも難しく、先ほどからそうであったと思える景色の状態そのものが記憶を裏切って刻一刻と更新されていった。彼はついに倒立して空に向かって吊り下げられた。今では街を闊歩する市民たちが最も高い位置にいて、自分は底のない下層でしがみついている。アルマンは鉄骨を掴んだまま頭を回して周囲を見た。足が震えて動かない。首を下に向けると足越しに、建物の間を巡る蜘蛛の巣のような道が天に張り付いていた。
どれくらいそうしていたか、彼には分からない。数十分にも感じられたが、ほんの十数秒間だったかもしれない。ある瞬きを境に夢から醒めたように世界が反転し、元に戻った。そっと鉄骨から手を離そうとすると、襟を掴まれぐいっとビルに引き入れられた。
「お前、何してるんだ」
職長が怒鳴った。
「またあの売春婦のとこか」
イヴァンは、鏡を前にジャケットを着るアルマンに言う。
「彼女はそんなんじゃない」寮でまともにドイツ語が通じるのは彼だけなのでアルマンは彼としか話せなかった。
「そんなんだよ、あれは」イヴァンはスタンドで買ったドネルケバブを頬張った。「お前はいいよな。女がいないのは、本当の生活じゃない」
「そうかな」
昼間のことは彼にもしつこく言われた。何ふらついてたんだよ、しっかりしろ、そんなんだといつまでも舐められたままだぞ。
それでも今は、足取り軽く出かけることができた。張り出した中国語のネオンサインが、滑らかに磨耗した路地の石畳と彼の顔を赤く染める。どこからか闇を縫って香水の香りが届き鼻をくすぐった。
外の立ち席でワインを飲む客をすり抜けて店に入った。テーブル席にはゼラニウムの造花とキャンドル、壁にはどこか地中海の絵が架けられている。中も賑わっていた。エリナはカウンター席で、すでに魚介料理を食べていた。
「ああ、ごめんね。注文しないで座ってるのも気が引けて」
「いいよ、遅れたからね」
アルマンはルーマニア語で答えた。ワインと肴を頼み、力を抜いてバースツールに身を委ねた。
彼女とはこちらに来てすぐに知り合った。アルマンと同郷で、彼がまだ切符の買い方もわからなかった頃に助けてくれたのだ。門前払いしようとする役所の窓口でやりあう方法を教えてくれたのも彼女だ。
「怪我は大丈夫だったの」
「平気、平気」
エリナはいつも初めのうちはドイツ語を保っているが、アルマンは久々の母語での会話を楽しみたくてやきもきしていた。
「今日も残業長かったみたいだけど」
「ああ、山ほど仕事があるからな」彼は、仕事のことを話した。背丈より大きな枠材をもちあげるときの力み、広大な敷地を一日で正確に仕上げる手際、高所にある狭い足場を悠々と行き来する度胸。アルマンは誇らしげに気分良く話したあとで、職場の同僚の振る舞いが頭を掠めた。事務方の女の職員が現場に来ていると、浮かれたように天井梁に跳びついて懸垂をしてみせる男。
「へえ、たいへんそうね」エリナは携帯端末を開いて見ている。「つらいことはないの」
「あの宿舎は辟易とするね。狭くて、俺の他に男が7人もいる。鼾がうるさい奴もいる。けど、仕事は楽勝さ」彼は気丈に、冗談っぽく笑う。
「じゃあ今日うち来る?」
彼は二つ返事で同意した。
アルマンが初めて降りた駅だった。想像していた、キオスクやバーの並ぶ下町ではない。静かな住宅街のある郊外だ。広い歩道には人気がなく、街灯が整備されていて明るい。低い塀に囲われた住宅の庭ではバラやベコニアが夜露に濡れていた。10分ほど歩いてエリナが入っていったのはそのうちの一軒だった。
「住み込みの副業してて」
言い訳するようにそう言いながら鍵を開ける。
「なんだ。男を連れ込んだのか。まあいいさ」暗がりの向こうから声がした。「どうせ反抗もできん。家と暖炉は残り、現れて過ぎ去るのは人の方」
廊下を曲がり、奥の部屋を覗くとベッドに横になった老人がいた。ベッドを圧倒するように本棚が並び、古生物の骨格らしき模型が飾られている。窓際に大きな胡桃材の書き物机がある。
「友人のアルマンです。明日はヘルパーが来れないそうなので入浴介助を手伝ってもらいます」
「わかったわかった、かまわんさ」
老人はハンスという名だった。銀行で働く彼の娘が、ネットを通じて住み込み介助員としてエリナを雇ったのだという。
「まあ寛いでくれ。この通り茶は淹れてやれんが」エリナはシャワーを浴びて別室に引っ込んでしまい、アルマンは彼と2人残された。落ちくぼんだ眼窩に伸びた白い眉毛がかかっている。
「娘はここにいないのか」アルマンは本棚の前のソファに座った。窓際の書き物机は介護用品の置き場になっていた。
「あれは仕事で、めったにこっちには帰ってこん。私もこれ以上迷惑をかけたくない」
「それでエリナを?」
「そうだ。どのみち誰かの世話にはなるんだが」ハンスは咳き込み本と読書用眼鏡をベッド横の机に置いた。「ろくに何も残せないうちにこの歳だ。真理を求めて思索している間だけ永遠を感じられる。床ずれの痛みで終わる永遠だがな」
「でも娘を残しただろう」アルマンはソファに横になった。今日はここで寝るつもりだ。
「娘は娘さ。自分の一部と信じるのは妄想だ。私自身が成したことじゃない」
「書斎に籠もっていたからさ。俺たちの仕事はずっと残るぞ」彼は体をハンスに向けて話し始めた。修繕中のビルのことや、父のしていた土木工事のこと、測量を学び故郷に橋を架けることが夢だということ。
「それが夢ならなぜここに来た。お国で働けばいいじゃないか」
アルマンは曖昧な唸り声で答え、ソファに頭を戻した。窓の外はあまりに静かだった。遠くで車の音が聞こえる。
「すまん。偏狭な奴と思わんでくれ。ただお前の故郷にお前を必要とする人がいるだろうと思ったんだ」
ああ、と少し遅れてハンスの言葉に返事をしたつもりだったが、その声は夢とのあわいで不確かになった。彼は疲れていた。
翌朝は慣れない仕事の連続だった。アルマンは、腕を引っ張ってハンスを起き上がらせようとしてエリナに叱られた。言われた通り、ハグするようにハンスの背中に腕を回す。客観的な測量ではなく、自身の身体で彼の体重を感じた。重心が彼の方からアルマンへと移り、力まなくても団子になって転がるように自分たちの身体が動いた。
車椅子でハンスを浴室に運び、衣服を脱ぐことから浴槽への移乗まで、ひとつひとつを手伝った。要領がわかってきて効率よく進めようとすると、「そこは自分でやってもらって」とエリナの注意が入る。
背中をスポンジで洗っているとハンスがうめき声をあげ、アルマンは老人の肌の脆さを知った。
エリナが3人分の朝食を作った。スープの缶詰を開け、全粒粉パンとハムとチーズを並べた簡単なものだった。彼女は、腐っていたからとレタスを捨てた。それでもアルマンにとっては久しぶりのまともな家庭料理だった。爪のささくれを気にする彼女を見て、アルマンは故郷の母の乾いて筋張った手を思い出した。3人で食卓を囲んだ様子は即席の家族のようだった。
「俺も理想郷を期待したわけじゃないよ。でもこれじゃ詐欺だ」
食後もしばらく寛ぎ、アルマンは老人に下請け派遣業者との契約のことを話した。労働時間や宿舎が聞いていたのと違うことを。エリナはもう仕事に出ていた。
「働いてる人間は、みんな騙されているのさ。金をもらっていても、もらっていなくても」とハンスは言う。
「ここで働いている、エリナもか?」
「ああ。そうだ」ハンスはきっぱりと答えた。
帰ってきた従業員宿舎はあいかわらず荒んでいた。部屋の隅にはビールの空き瓶とサラミの容器、アルミホイルが寄せ集められ、埃がたまっている。「掃除しろよ、お前ら。ジムに行く体力があるんなら」そう言いつつ、アルマンは一人で片付けに努め始めた。
それからも短い頭痛と方向付けの混乱は数日に1回の周期で訪れた。階段の手すりをもつ癖がついた。通りの前方へ落下する気になって街路樹を掴んだ。地下鉄でもそれに襲われた。電車が天の暗い穴から落ちてきて頭をかばったこともある。その時、アルマンは目を閉じて体の感覚を取り戻そうとした。重力は依然として大地へと彼を引きつけている。少し足踏みをして均衡を保ち、ゆっくり目を開けると元に戻った地下鉄のホームが見えた。
生活のさまざまな場面で遠いものを近くと錯覚したり、上方向が転換したりした。だがアルマンはしだいにそれらをやり過ごす一連の方法を身に着けた。
まず目を閉じる。その状態で眼球に意識を向けながら左下を見ると、目眩に似た感覚があり、喉の奥、頭蓋と頸の境目あたりを軸にして水に浮いて横になるように方向がずれ始める。そこで、立っているときは足の裏に意識を向けて、座っているときは身の回りの物に手を触れ、ゆっくりと目を開ける。そうするとずっと早く回復するということに気づいた。
その日は朝から従業員同士で仕事の手順について諍いがあり、一人がへそを曲げて帰ってしまった。工期が遅れたため追加で型枠工が雇われ、名前を知らない従業員が増えている。先ほどから時折、そのうちの一人の若い従業員が鉄骨をドラムに見立てて工具で叩いている。誰かが注意するほどでもないその響きが現場を微かに苛立たせていた。
現場はビルのまだ鉄骨だけの階層。ハーネスをつけての作業だ。作業階にはまだむき出しの鉄筋が櫛の歯のように並んで生えている。そこにフロアクレーンが自身の支柱を巻き上げて昇ってくる。その様は天蓋の下の祭壇か舞台装置のようだった。従業員はそれぞれの役に従って持ち場につき、アルマンも工具を装着して鉄骨の上に登った。
梁に立って下を見下ろしたときに頭痛がして、見下ろしている舞台が逆転した。急いで柱を掴み、ルーチンになっている対策を講じた。ゆっくりと目を開けたとき、それは起こった。見えたのは未知の世界だった。
下にクレーンがある。それは正しいはずだ。しかしその前のフロアは湾曲し、その曲面を横向きに立った作業員が歩いている。反対側の鉄骨は逆方向に伸びていて、ビルの内側が金属球に反射させたように裏返っていた。視界の半分しか元に戻っていないようだ。正立と倒立の共存した捩じれの中で彼は自分がどこにいるのかさえ分からなくなった。一番遠くで柱に捕まっている顔の見えない作業員の姿が、ハーネスのバックルの錆まで、まるで目の前にいるように仔細に見分けられた。それはアルマン自身だった。
数日後、職長はアルマンを呼びつけた。解雇猶予は二週間。高所恐怖症の発作が見られる、職場の安全のため、というのがその理由だった。アルマンはそれに反論できなかった。一体どうやって自分に見えている世界を説明できるだろう。誤解を解いたところで彼らの懸念を解消することはできるだろうか。彼には分からなかった。イヴァンは何も言わず難しい顔で彼の肩を叩いた。
彼は曇り空の街を徘徊していた。仕事は数日休んでいるが、あの寮にいても身や心は回復しない。アルマンはベンチに座ってぼんやりとマルクト広場を見やった。餌を期待したハトたちが素知らぬ顔で集まってくる。
昼間から、どうやって生活しているのか分からない人々がベンチや階段に座り、タバコを吸って駄弁っている。キリスト教の伝道や、アンティファの抗議演説が聞こえる。ホームレスの老人はせっせとデポジット瓶を拾い集めている。その合間に金にならないであろうゴミ拾いをしたり、パンをちぎってハトに餌やりもしている。誰もが役を演じていた。
「ウィード。ウィード」
マリファナ売りの若い男が英語で声をかけてくる。ノーと言ってあしらったあと、彼はマリファナ売りの立ち位置から見える善悪の遠近法について考えた。そしてまた広場の他の者たちや故郷の人たちの、それぞれが見る地球儀に思いを馳せた。思索はもつれ、どこにも行き着かなかった。陽が落ちて、闇が広場を包んだ。雨が降り出した。
「哀れなアルマン」
そう呼びかけられて顔を上げるとエリナが立っていた。「連絡したらいいのに」
「また彼に手伝ってもらいます」
エリナはハンスにそっけなく告げた。ハンスはアルマンの事情に興味がないように何も聞かず、ずぶ濡れの彼を迎えた。
「おお、万物は流転し、大工がまたうちに来た」
「調子はどうだ」
アルマンは翌日、部屋の間に低いスロープを敷き段差を無くす工事を任された。家には、書斎兼寝室とキッチン以外の部屋にほとんど物がないのを知った。
エリナに他の介助を教わり、アルマンは食事も作った。挽き肉に玉ねぎとスパイスを入れて捏ね、パプリカに詰めてオーブンで焼いた。塩気は薄く、少し焦げた。
「年寄りには脂っこ過ぎたか」
「もう健康を気遣う歳でもないさ」
数日後エリナが、住み込み労働は拘束時間が長過ぎるという理由で契約を切り、アパートに越して行った。もっともな理由だった。
ハンスはベッドで本を開いている。アルマンには長い文章はさっぱりだったが、奇妙な挿絵が目についた。
外から通り抜けできる建物の一角が吹き抜け階段になっており、階段に座る少年が上を見上げているのが絵の下半分。天井だった四角の面が、絵の上半分では床と見なされ、そこから同じ光景を上から見下ろしたように描かれている。上と下は矛盾しながらも奇妙に滑らかに連続している。
「エッシャーというオランダの画家の、〈上と下〉という作品だ」本を覗く彼にハンスが言う。「人間の認識は特定の観点や生物学的な条件に縛られるわけだ」
「リアリズムだな。これに似た景色を最近よく見る」
アルマンがまじめな調子で言うとハンスは笑った。居候になってからの時間はゆっくりと過ぎた。
これからどうするのか、とハンスは尋ねた。
「あんたが言ったように、故郷で仕事を探すことを考えてる。もう少ししてからな」彼は軽くソファにもたれた。
「私のことは気にせんでいいぞ。お前はこっちで仕事を探すことだってできるし。うちにはヘルパーだってたまには来る。お前は自由なんだ」
そう言いながらハンスは静かに目を閉じた。そうだな、とアルマンは答えた。俺は自由だ。
ピリッと、また電気のような頭痛が通り過ぎた。いつの間にかアルマンは横になっていた。ハンスがその傍らで佇んでいるように見える。彼はその観点を保ったまま、しばらくハンスを見つめていた。
虫太「上と下」はKaguya PlanetジェンダーSF特集の作品です。特集では6つのコンテンツを配信しています。
- 高山羽根子さんによる魔女SF「種の船は遅れてたどり着く」
- 正井さんによるケアSF「優しい女」
- 近藤銀河さんによる論考「SFの中で踊る魔女 ─未来をフェミニストとして生き延びるために─」
- なかむらあゆみさんによる老姉妹SF「玉田ニュータウンの奇跡」
- ジェーン・エスペンソンさんによるケアSF「ペイン・ガン ある男のノーベル賞受賞式に向けたメモ」(岸谷薄荷訳)
- 虫太さんによるケアSF「上と下」