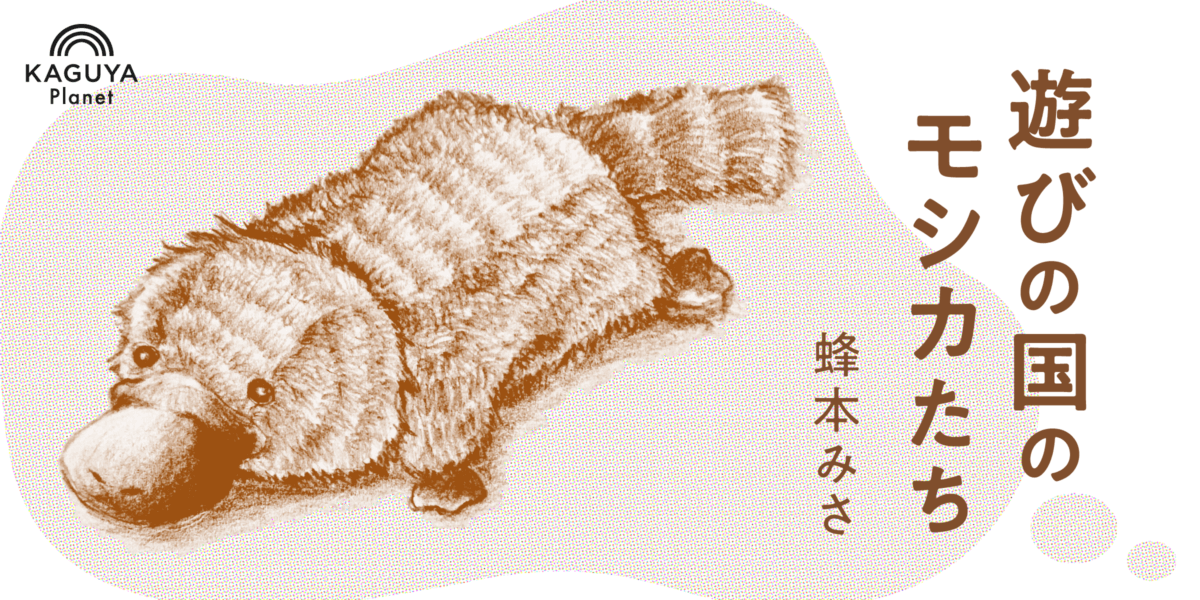また、Kaguya BooksのInstagramでは、『遊びの国のモシカたち(仮)』の新着情報やぬいぐるみ情報を紹介しています。
蜂本みさ『遊びの国のモシカたち(仮) 12』
11 ぬいぐるみ診療所の夜
6,368字
「あんた今日来たカモノハシやろ? 急患の」兎はゆったりした声で言った。病院の壁に「お写真サービス付き」の文句と一緒に張り出されていた写真の兎だ。あんまりリアルじゃなくて、何度も繰り返し描いて線のとろけた落描きみたいに顔も手足も間が抜けていたけれど、立派な白衣と聴診器をつけていた。
「怖がらんでよろしい。どれ、ちょっと案内したろか」
兎は先に立って作業机の上を歩き始めた。当たり前のように思えたのがかえって不思議だった。遠足で猿が口をきいた時もこんなふうに、空気が水の中みたく揺れていたっけ。ぼくは兎の後を追いかけた。
「あなたはだれ?」そう尋ねると、兎は振り返らずに「わしはこの病院の院長や」と答えた。
「お医者さんはムグラさんでしょう」
「うん、あれとわしとふたり合わせて医者なんや。ぬいぐるみにはぬいぐるみの医者が要る。そやけど手え動かすもんも必要や。まあ、ビジネスパートナーちゅうこっちゃ」兎医者はそう言って、まあ明日になったらわかるわ、と付け足した。
「ここが手術室」
兎医者が示したのは、昼間の受付からも見えていた大きな作業机だ。何もない広場のぐるりにたくさんのまち針を生やした針山や、色とりどりの糸巻きが並んでいる。薄暗がりに沈んだそのあたりは、腕利きの庭師が刈り上げた植え込みに見えた。歩いてるうちにぼくはやっと落ち着いて、夜の公園を散歩する気分であちこちを眺めてまわった。左手にある工場みたいなのはきっとミシンだ。奥には巻物の山がそびえている。こんなにすっきりとしたところが手術室だなんて、どういうことだろう?
やがてぼくはたくさんの取っ手がついた小引き出しに行き当たった。一段目を開けてみると色んな太さのゴム紐が入っていた。二段目は切り抜かれたフェルトの端切れだった。一番上の段を開けると、目玉のボタンがぎっしりとひしめいていた。ぎゃっ、とぼくは声を上げて飛びのいた。真っ黒なやつ、白目のやつ、猫みたいに瞳が縦長なやつ、大きさごとに整頓された色んな目玉たちがさんざめいてこちらを見る。傷ひとつないそいつらは暗がりの中でつややかに光っていた。
針山まで逃げてきたけれど、その向こうに見えていた巻物の山と思ったものがみんなぬいぐるみの毛皮だと気づいて、ぼくはまた情けない悲鳴を上げてしゃがみこんだ。ふわふわの白、毛足の短い茶色、柔らかなタオル地のクリーム色、どれも平たくのされて芯にきつく巻かれ、棚の暗がりに黙りこくっている。それに隣のてっきり雪山だと思っていたもの、あれは綿じゃないか!
「怖がらんでええ、替えのパーツどもや。サイズも色も質感もようさんある。あんたがどんだけ元の形なくしても移植手術で治せるから安心しい」
兎医者は目玉の引き出しを閉めるのが音でわかった。ぼくはおそるおそる顔を上げた
「元の形って、たとえばしっぽがちぎれちゃっても?」そう言って、縫い目がやや心もとなくなっている自分のしっぽを抱きしめる。兎医者はそんなことはなんでもない、という風に笑った。
「しっぽでもくちばしでも目玉でも、全身なんでもや。ぬいぐるみは人間なんかよりずっと丈夫やからな」
ぼくは昼間の診察を思い出した。そしてその言われた全部を手術して、ふわふわの毛皮につややかな目を光らせた自分の姿を想像してみた。
「それっていいことかしら?」とぼくは言った。「そんなにあちこち取っ替えて、ぼくがぼくのままだって言える? 捨てられちゃう元の部分の方がよっぽどぼくなんじゃない?」
「そこがぬいぐるみ治療の奥深いとこなんやなあ。次は病棟に行こか」
兎医者はほこり避けの布がかけてある、テントのような場所にぼくを案内すると、布の端っこをめくって中へ入っていった。「先生、先生」というひそひそ声が巻き起こった。はいはい回診ですよ、と兎医者は言い、ぼくを声たちの前に引っ張り出した。
「こちらはカモノハシのモシカさん。急患で来たんや。短い間やけど、ようしたって」
ふたたびひそひそ声。布を透かして降るかすかな光に目が慣れて、重なった暗い小山がだんだんくっきりしてくるにつれて、こちらを見つめるたくさんの目が浮かび上がった。
小山はみんなぬいぐるみだった。兎も熊も恐竜も、お豆腐もタコも車もいたけれど、誰もがやわらかい体を持っていた。そしてひとり残らずぼろぼろで、ものすごい年寄りだった。とても言えやしないけど、もしぬいぐるみのおばけ屋敷があったらこんなだったに違いない。彼らは興味津々、ぼくを取り囲んでその場でくるくると回らせた。
「あらっ、お腹から綿が!」
「事故にでもあったかね、かわいそうに」
「にしても変な顔だねえ。怪我のせい? それとも何かのキャラクター? ずいぶん地味だけど」
最後の声には腹が立ったけれど、礼儀正しく「カモノハシのモシカです、カモノハシはオーストラリアにほんとにいる動物です」と答えた。ぬいぐるみたちは一通り調べ終えると口々に自己紹介を始めた。名前に年齢、入院した理由。相棒の人間について。ほとんどが三十歳を越えていて、相棒もとっくに大人だということだった。入院した理由はいろいろだ。両目をなくした、ペンキをかぶった、犬に引き裂かれた、毛皮がすっかり抜けた、綿にカビがわいた、足がアロマキャンドルで焼け焦げたなどなど。ひとり残らず重症だった。目もあてられないくらいひどい怪我なのに、彼らの口調にはどこか面白がっているようなところがあって、おまけに自慢げなものだから、ぼくはどう返していいかわからずにちょっとまごついた。
「みんな、ぼくなんかよりずっと大変な怪我みたい。お気の毒です」
ぬいぐるみたちは笑った。「気の毒なんてとんでもない。私たちは世界でもっとも幸運なぬいぐるみの一員なんだよ」
それを言ったのは年取った熊のぬいぐるみだった。たぶん。というのは、頭がまるごとなかったからだ。熊とわかるのは胸元に白く――といっても手垢で真っ黒に汚れていたけれど――浮かんだ月の輪のおかげだった。細かく縫い綴じられた首の傷から声が出るので、どこに話しかけたものかちょっぴり困った。
「幸運って?」
「ぬいぐるみの最期を考えたことはあるかね? 目が取れようが手がもげようがそんなことは問題じゃない。ぬいぐるみが死ぬのは、相棒に必要とされなくなるときだ」
まわりのぬいぐるみたちが静かにうなずいた。その仕草から、首無し熊が患者たちの長として大事にされているのがわかった。熊は続けた。
「寝る時だってお出かけする時だっていつも一緒で、私たちは肉と布のきょうだいで、一秒たりとも離れていられなかった。それなのに相棒は私たちがいなくてもだんだん平気になっていく。それが正しい変化だという人もいるがね。やがて棚に飾られるようになり、大掃除の日に箱へ放りこまれたら最後だ。それは、見捨てられるとか忘れられるってことですらないんだね。何年も後で懐かしいと頬ずりされても、ぬいぐるみの魂はもうそこにはいない」
「必要とされなくなったぬいぐるみの魂はどこへ行くの?」とぼくは尋ねた。
「さてね、ただほどけて飛んでっちまうんだろうよ。ぬいぐるみにも天国があればいいんだが」と熊はため息をついた。「だからね若いの、怪我は災難だったにせよ、ここへ連れて来られたことを喜びなさい。相棒はあんたをまだ必要としているんだから」
傷ついたぬいぐるみたちがこちらを見ている。その目玉のほとんどは、表面に細かい傷がついて白っぽく曇っていたけど、この目好きだな、とぼくは思った。まわりの光をぼんやりと映して、すごく優しい感じがするから。それからもおしゃべりは続いて、夜は更けていった。
「たくさん話せてうれしかった。あなたの手術、うまくいくといいね」最後にぼくがあいさつすると、首無し熊は大笑いしてこう言った。
「治療はもう終わってるよ。あとは退院を待つだけだ。頭を失くしたのはもう何十年も前でね、あの子にとってはこれが本当の姿なんだ」
ぼくらはテントを出た。「どうやったかな」と兎医者が聞いてきたけれど、すぐには答えられなかった。ぼくはゆっくりと言葉を選んだ。
「ぼろぼろになっていくの嫌だったけど、今はもう構わない。ミミがきっと治してくれるもの。だけど、ずうっと長生きするのがいいことか、わかんなくなっちゃった」
「ほう。なんでそない思う?」
「ぼく、ミミの幸せのためならなんでもしたい。みんなの相棒もきっとみんながいて幸せなんだと思う。でもミミは時々、ぼくと一緒にいてつらそうにしてる。今日だって学校を休んじゃったし、明日もきっと休むだろうな」
「へえ、そうか」と兎医者は感心したように言った。「人いうのは、ちょっとアホやからなあ。望みと幸せちゅうのが一緒やったらええんやけど、そうもいかんのやなあ」
その時、すすり泣く声を聞いたような気がした。振り返ると、受付カウンターのある方から確かに泣き声がする。「他にも誰かいるの?」と尋ねたけれど、兎医者は「あれはええんや、ほっとき」と言うばかりだった。
「でも、泣いてるみたいだけど」
「そやな。ちょっとむつかしい患者なんや」
ぼくはどうしても気になってそちらの方へ歩き出した。なんで泣いてるのか知りたかったんだ。それに病棟のぬいぐるみたちと話してずいぶん気持ちが明るくなったから、今度は自分が泣き声の主をなぐさめてあげたいと思ったせいもある。けれど誰の姿も見えなくて、ただカウンターの手前にカバーをかけられた荷物がこんもりと盛り上がっているだけだった。泣き声はそのカバーの下から聞こえてくる。ごめんください、こんばんは、と声をかけても返事はなかった。
「どうして泣いてるの?」ぼくが何度目かにそう言うと、「うるさい!」と破れ鐘のような声がして、ぼくは驚くあまりに後ろへころりんと尻もちをついた。
「おれに構うな」声はぴしゃりと言った。おじさんみたいな低音なのに、すねたような甘ったるい響きもあって不思議だ。ますます正体が気になる。カバーはよく見ると布製で、暗い緑の生地に白い線でつる草に似た模様が描かれていたけれど、一箇所が派手に破れて穴ができていた。その奥に何か見えた気がして、来るな、あっち行けと声がする穴の方へ身を乗り出した。
「こらこら、あぶない。そのへんにしとき」
兎医者が言うのと、ぼくがまっさかさまに穴へ落っこちるのは同時だった。あちゃー、と兎医者はつぶやいた。カバーの中はほこりの匂いでいっぱいだ。あたりを探ろうと起き上がった途端、「来るなって言っただろ!」と思い切り怒鳴りつけられて、ぼくはくらくらした。声よりもっと驚いたのは、声の主は子どもがやっと抱えられるほどの巨大な生首だったことだった。太くて黒ぐろした眉毛の下に金色の目玉が燃え上がり、同じく金色の歯をむき出しにして真っ赤な化け物が吠える。鼻先が欠けて白い部分が見えているのもおどろおどろしかった。
「こんばんは、いい夜だね」勇気をたっぷり込めたあいさつはまたしても「うるさい」の一言で片付けられた。だけど返事があったことにぼくは少し気をよくした。ちっちゃなぬいぐるみのあいさつなんか、無視したっていいはずだもの。
「おーい、そいつは獅子舞や。顔は怖いけど傷つきやすい奴でな、そっとしといたり」と穴の縁から兎医者が手を振った。いまいましい医者め、とそいつは金の歯で歯ぎしりした。シシマイってなんだろう? わからなかったけれど、動物の一種だと思うことにする。「シシマイはなんで泣いてるの?」と尋ねると、シシマイはこれまで以上の激しさで怒り狂った。
「なんでだと? お前らふわふわ連中が自慢たらしくしゃべり散らかすからだろうが。おれを馬鹿にして!」
「騒ぎすぎたならごめんね」とぼくは言った。「でも馬鹿にしたりなんかしないよ。そもそも君がいたこと、知らなかったし」
この返事はさらにシシマイを傷つけたらしかった。おれなんかいてもいなくても同じだ、誰にも愛されずにこのまま滅びるしかないとしくしく泣き出したのだ。
「だけどほら、君は必要とされているからぬいぐるみ診療所に来たんじゃないか。元気を出しなよ」ぼくはちょっと恥ずかしく思いながら、さっき教えてもらったばかりのなぐさめを言った。「おれはぬいぐるみじゃない」というのが答えで、それは実際そうだった。シシマイは固くてつるつるで、毛らしい毛といえば両耳の間に生えた白い毛だけだったのだ。じゃあなんでここに連れてこられたんだろう?
「おれはかわいくもないし、柔らかくもない。早く帰りたい。父さん、母さん」
「ちょっと待って、君ってもしかしてまだ子どもなの」
子どもで悪いかとシシマイは破れかぶれにむせび泣いた。途端にいろんなことがすっきりお腹に収まった。恐ろしい顔に銅鑼のような声をしているけれど、幼稚園の子が迷子になって泣いてるのと同じなんだ。そうとわかると不思議と怖くなくなった。
黙ってあごの付け根をとんとん叩いてやると、シシマイはじきに大人しくなった。ミミが小さい時、涙が止まらなくなるとイノちゃんやまくるちゃんがこうやって背中を叩いてたのだ。ぼくも時々はやってあげたものだった。シシマイはじきに、しゃくり上げながらもここに来た理由を話し始めた。
シシマイいわく、シシマイはこの町の神社に住む由緒正しい獅子舞なんだという。獅子舞っていうのは、目に見えない悪いものを食べて追い払う不思議な力を持った動物だ。お祭りの日には大勢の人の前で父獅子、母獅子と一緒に舞って、人々の平穏を守る。今年もその準備が始まったのだけど、ここで問題が起きた。人間の子どもがシシマイに体を貸すのを嫌がったんだ。練習は疲れるし、なんのためにバレバレな動物のフリをするのかわからないし、だいいち獅子舞みたいに赤い顔した変な動物はこの世に存在しないといってね。まわりがこの頑固者の子どもを説得しようと獅子舞の由来を言って聞かせたが、大人たちのうちでも獅子舞はライオンだ、いや鹿だ、イノシシだ、狛犬だと違った意見が出て、かえって混乱させるばかり。とうとうかんしゃくを起こした子どもは風呂敷――ここでわかったが、模様の入った緑の布カバーのこと――を振り回し、生首を床に投げ捨てて役を降りてしまった。ぼろぼろになったシシマイは、困り果てた大人たちの手で器用なムグラさんの元に運び込まれたというわけだ。
「悲しいのは怪我だけじゃない」と獅子舞は言った。「おれは自分が一体何なんだかわからなくなったんだよ。せめて肉食動物か草食動物かだけでもはっきりしてほしいものだが」
「わかる気がするな」とぼくはしんみり答えた。「ぼくもよく言われるよ。鴨とカワウソとビーバーをつぎはぎしたみたいな動物だって」
「本当か?」獅子舞は目を輝かせた。「言われてみればお前、たしかに変だな。こんな変てこな生き物は見たことがない!」ウワッハッハ、と笑う獅子舞にぼくは少しムッとしたけれど、元気になるならと黙っていた。
「まあ、治ったところで体がないんじゃどうしようもないんだ」と獅子舞はため息をついた。
「代わりに役をやる人はいないの?」
「いたら最初からあんな分からず屋のちびすけに役は回らなかったさ。子どもの獅子舞には子どもの体が要るもんだから、あいつは押し付けられたんだよ」
自分を壊したという子どもを、意外にも獅子舞は気の毒がってみせた。見かけより優しい性格なのかもしれない。
「祭りってのは普段目に見えないものを見て、耳に聞こえない音を聞く特別な日なのに、そんな酔狂なやつ今じゃめったにいない。屋台の食べ物や演し物が目当てのやつばかりだ」獅子舞のぼやきを聞きながら、ぼくは何か思いつきそうになっていた。
目に見えないものを見て、耳に聞こえない音を聞く子ども。ぼくにはひとり心当たりがある。
クラウドファンディングをご支援くださった皆様は、共通のパスワード【moshika-mimi-asobi】で読むことができます。