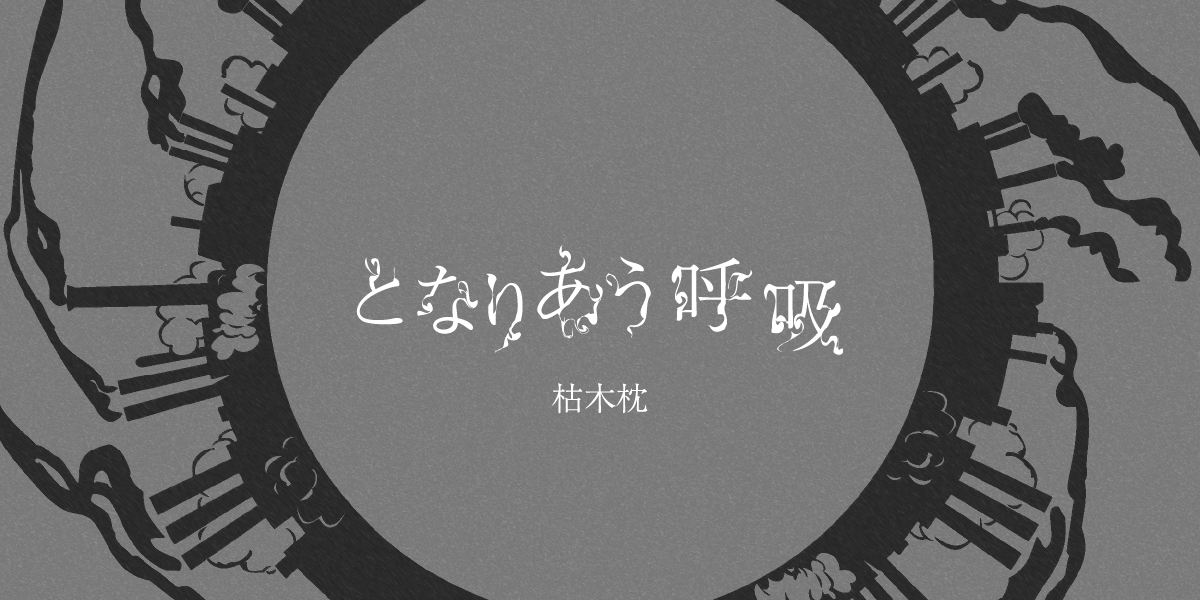先行公開日:2022.2.5 一般公開日:2022.3.12
枯木枕「となりあう呼吸」
12,800字
子供をうむには適さない土地でも子供はうまれる。その日その街で分娩室にはいった親子は二組だけだった。ひとりは夕暮れの始点にうまれ、もうひとりはぼやけた陽を西の地平がじゅうぶんにまきとり終えたあとにうまれた。しばらく両親の腕に抱かれ、ふたりは新生児室で顔をあわせた。となりあうベッドで寝かされていたが、さしてお互いに興味を示さなかった。はじめて浴びる五感の濁流に耐えるので忙しく、お互いはお互いを意識の外においていた。シロップを飲まされ、からだのあちこちを調べられたあと、ほどなくしてふたりは同時刻に泣いた。数時間もすると、じぶんとそれ以外の境界にもなれて、隣にぼやけた明るい塊があることを認めて舌をだした。ひかりにむかってどれだけ伸ばせるか試そうとする。ひかりまで届いた気がして、じぶんの舌とおなじ味がすることをお互い認めた。それはシロップの味であるとはまだ理解できない。新生児室から連れだされるとき、ひかりの味が恋しくてまた泣いた。
それぞれの病室をそれぞれの看護師がノックした。看護師はシャム双生児としてうまれ一歳になるまえに分離手術をうけた。肩には大きな跡が残っている。いまは別々のからだでおなじ病院に勤務していた。たべるときのリズムも、眠りに誘われまぶたが重くなる時刻も、双子の神秘をなぞるようにほとんどおなじだった。廊下を挟んで西と東の対称位置にある病室で「とても元気で健康な赤ちゃんです」と看護師たちはおなじ声量で告げた。
親たちは息をもらした。片方の赤子は左手の指が六本あり、もうひとりは耳たぶが四つあり左脚の小指がなかった。両親はひかりのような我が子を歓喜のまま抱きしめた。からだが、所作が、感情をとめどなく放ちうることに驚いたが、我が子が泣きだしたので、両親はそれぞれの間で歯どめなく語るからだの感覚を忘れた。
夕暮れにうまれた赤子はマヤと名づけられ、夜にうまれた子供はモネと名づけられた。街は病気か、からだの崩れた子供で溢れかえっていた。比較すると、ふたりは奇跡みたいに美しく整った赤子だった。両親には顔立ちも端正におもえた。生後数日の我が子の未来に期待しながら、街に充満する煙を吸わせないよう丁寧に布でくるんだ。工場から溢れる煙の粒子をひとつぶも吸わせたくなかった。じぶんたちとおなじく子供を授かった夫婦が大切そうにくるんだ包みを抱いたまま車にのりこむ姿をみて、目があい、微笑みを投げあった。二台の車両は相反する方向へ走りだした。
さいきんの子供は崩れやすくできているから、ちょっとした拍子にやわい骨を折ったり指にひびがはいって弾け飛んだりしないよう、マヤの両親は家中をしつらえなおした。包丁やハサミはベルトで固定し、家財のあらゆる角をヤスリで丸めた。床もつねに綺麗にした。古びて脆い貸家にしか住めない家計だったが、できる限り安全な環境でマヤを育てたかった。
這いつくばれるようになると、マヤは鏡に寄っていき映っているじぶんをぺろぺろと舐めた。赤子は鏡をみると気になって舐めてみたりじぶんの姿とは認識できないままその動きにわらったりするのだ、とすでに大きい子をもつ隣人から教わったが、それにしても執拗におもえた。そこに甘いものでも塗りたくられているかのように、目を離すと鏡のまえに這っていく。ほかのものにはあまり興味を示さない子だったので不思議でならなかったが、マヤが言葉を覚えはじめるとそんなひっかかりはすぐに忘れた。はじめて喋った単語は両親のどちらを示すものかで揉めたが、実際にマヤが発音したのは林檎を意味する単語だった。次に舌がおぼえたのは鳥と煙で、両親の呼び方はその次だった。家に唯一かけられている絵画に大きな林檎が描かれていて、実物をみたことのないマヤは林檎をひとよりも巨大なものだとおもっていた。
マヤの家庭は街のなかでも裕福ではなかったが、そもそも街全体が貧しかった。建ち並ぶ工場の煙突だけが街のシンボルで、ほかのシルエットは工場からもれだした煙にまとわりつかれ朦朧としていた。鳥の住む高度だけ、かろうじて煙から逃れていた。くだものは育たなかったし、外から運んでくるにしても売り場につくまでに九割は汚れてたべられたものではなく、この街では貴重品だった。マヤの両親はどちらもただの工員で、普段はくだものなどくちにできない。両親は金をすこしずつ貯めて、マヤが無事に育ったら籠いっぱいの林檎を買ってくると約束していた。マヤの両親は、この街から遠く離れた、いまはもう滅びた農村の出身だったから、こんなに可愛い子に果実の甘みを教えてあげられないことを悔いていた。工場での作業は農村での生活とは異なり、じぶんの手がなにをつくっているのかもわからず、ただ日々が指先を黒ずませていく。喉の奥にあたらしい膜でもできたかのように呼吸がそこはかとなく苦しくなっても、別の道などありはしないから、ただ林檎を買うことだけを考えて工場にからだを捧げた。なにも考えず、工員の営みを被って生きれば、家に帰って静寂に逃げ込める時間、みずからの子供との安息の時間だけはなんとか保っていられる。
煙がいっそう濃い日だった。うろんな街角の路地で、靴みがきの子の咳が大きい。その子が咳き込むたびにのぞく舌は紫がかり、脚はつけ根から崩れてほとんど形を成していない。お代をうけとるにも這って移動していた。たびたびよろけてしまい、せっかくみがいた靴を汚して怒鳴られている。マヤよりひとまわりは年上の子だが、肌にはりもなく、ひと押しでからだが砕け散りそうにみえる。きっと親の両方か片方はからだが弱く、この街の煙にやられて、虚弱をより強調して生まれた子だろう。そういう資本のない家庭の背景をからだから感じさせる子も、工場の近隣や風向きで煙がたまってしまう賃貸の安い地区ではよくみかける。とくに煙の濃い日は下町の住民が煙害の薄い地区の路地にでて夜を明かすから、荒れた治安のなかで喧騒もよりつよくなる。路上の騒ぎ声をきくと、煙のなかの、おぼろげなシルエットの隣人はみな悪人にみえてくる。
喧騒のなかから怒声がきこえる。なにかを蹴りつけるようなおとがつくった煙のすきまに視線をむけると、転がった道具のまわりに塵のようなものが舞っていて、靴みがきの子はもういない。工場に雇われている街の掃除人がさっさと積もっている塵や欠片を掃除する。片づけた欠片と塵がおおよそ子供の体積とおなじくらいだったからといって掃除人を責めようもない。掃除人は掃除人の仕事をしただけだ。こんなに霞む煙のなかでは、みれるようにしかものをみる余裕はない。しかし、両親は掃除人からみえない角度で、ちりとりのなかのくすんだ瞳の欠片と目があってしまい、不安そうに身を翻して帰路を急いだ。そういった悪い予感をなんども繰り返してきたのだから、もちろんいつかは的中する。それがこの日というだけだった。
玄関口にたつと、なかから小気味のよいおとがした。戸をゆっくりあける。われた窓からはいった煙が部屋を陰らせている。重い煙はその質量をもって両親の脚を絡め鈍くした。煙のすきまから、両手で抱えた林檎に夢中でくちづけるマヤの横顔がひかった。薄やみのなかで様々な形の手がマヤのからだにまとわりついている。手たちは両親に気づかぬまま蛇のようにマヤのうえを這う。林檎を齧るおとがするどく鳴り、煙からひとつずつ抜けだしてくるたび両親は泣き叫びそうになったが、お互いの腕を噛んで耐えた。両親がようやく怒号を発して飛びかかると、とりどりの形をした手は煙の奥へそのつけ根があるかのようにするすると逃げだした。なんとか一本だけ細い腕を掴んでいた。おもいきりひくと、崩れやすい若者の腕だったのか簡単にひきちぎれた。若く青白い手だった。指先をなんども踏みつけるとマニキュアで青く染めた爪がわれて破片が飛んだ。マヤの手から林檎をひき剥がして潰した。からだのあちこちからでている血を拭いてやり、室内の煙が晴れてしまうまえに家中の鏡を割った。そうしたところで、その数年後には、風呂場の水面に映ったじぶんの姿を、赤黒い手形に覆われた肢体をみて、理解したその意味にマヤはうまれてからいちばん大きい叫び声をあげることになる。
劇場はいつも蒸れて熱かった。窓をあけるとすぐに煙と粉塵がはいりこみ、粘着質なタール状のものが床や壁にこびりついてしまう。密閉した空気のなかで動かすピンスポットのまわりはより熱く、鼻から息を吸うと汗の味がする。マヤは肌を隠したくて袖のながい服をきていたから、フードやたわんだ袖に熱がこもっていつもここちが悪い。
「照明係!」
舞台上で役者や踊り子を指導している劇場のオーナーから指示があり、ライトの角度を調整する。ここでは照明係としか呼ばれないがもう慣れた。家に帰っても、両親にはいちど落としてひびわれた硝子細工に触るかのように接され、お互いの機微だけ読んで声もなく生活するようだから、マヤは久しく呼ばれていないじぶんのなまえをそろそろ忘れそうだった。
マヤの両親は貯めていた金で窓枠にはめる鉄格子と無数の南京錠を買った。走って逃げられるくらい、脚の骨が固まる年齢になるまで、両親を伴っての外出しかゆるされなかった。学校にも中等部から、それも一年遅れてはいったが馴染めずにやめてしまった。マヤの歳ではまだ工場にはいけないから、靴でもみがくか、路地でいかがわしい店の客ひきをするか、こういった数少ない娯楽場で小間使いにでもなるしかない。
劇場の賃金は低かったが、舞台をみるのは好きだった。演者たちにひかりをあて、そのからだを輝かせると、じぶんもそこにたっている気になれた。マヤとおなじ歳のある演者を気に入っていた。役者や踊り子候補の、練習生の子供はちらほらいたが、名のある役を舞台で務めているのはその子だけだ。演者と照明では部隊が違ったので、まだ話したことはなかった。こちらが眩んでしまうよう、その演者にライトをあてるときはよりつよく調光した。ただみていたかったし、みられたくなかった。しかし、おなじ照明係で下っ端のエコはそうではなく、稽古が終わるたびにその役者に駆けよっていった。モネ、モネとなまえを呼びながら。照明係の下っ端はほかにいないから、そのたびにマヤがとめにはいらなくてはいけない。邪魔になるからやめろよ、と諌めるとエコは「やめろ、やめろ」と繰り返す。幼い頃に転んで顎が変形してしまい呂律が悪く、そのせいかエコはひとの言葉尻を繰り返す癖があった。そのたび首をつかんで揺らしてやるが、もがいてモネのいる舞台に駆けていこうとする。
モネは舞台道具の姿鏡に映ったじぶんの姿をみていて、エコのことなど気にもとめていない。軽くステップを踏んでから、モネは指さきで鏡を撫でた。
「動き、あってるか」
「問題ない」と鏡はいった。
「でも、わからなくなる」とモネは腰をひねった。「まわりの子は誰も似てないから、どんな体幹が、動きが正しいのか」
「いいんだよ、あるていど形になれば」と鏡はいった。「モネ、おまえは将来この劇場でいちばん客を呼び込める演者になるよ」
不満そうに、モネは苛立ちをくわえて乱暴に床を踏む。
「からだは大事にしろ。工場にはいきたくないだろ」と鏡は呆れたような声色でいう。「怪我なんかしてみろ、価値がなくなるからな。指一本たりとも崩すなよ」
モネは軽く鏡を蹴った。鏡の裏から身をのりだしたオーナーがモネのあたまを撫でる。不満げに払い除けると、オーナーの二重顎と膨らんだ腹がぶるぶると揺れた。
モネは劇場の誰からも期待されていたし、あらゆる意味あいで求められていた。あまりにも汚れのない肌と整った肢体にみんな触れたがる。均衡のとれた肢体は、むしろ崩しやすさの証明になって、あやうくよりかかり、故意のないままそのからだの一部をこそぎとってしまいたい、と大勢の言外でおもわせた。モネが踊るステージを俯瞰してみると、遠目には、客席で掲げられる腕は拍手をしているのか、いまにも掴みかかろうとする手の群れなのか、判別がつかない。ひとが群がる様子をみると嫌なきぶんになり、マヤはフードをより深くかぶった。じぶんがモネをみているとき、どんな目をしているのか、どんな表情でいるのか、マヤには見当もつかなかった。
共同墓地で浮浪者が焚き火を囲んでいる。モネは一歩ずつ踊るように靴を鳴らして、浮浪者に近づいていく。浮浪者たちは天使でもみつけたかのような表情でモネをみつめる。モネが近づくにつれ、浮浪者の顔は徐々に崇拝の表情から、みずからも自覚できない欠乏に駆りたてられゆがんでいく。最後の一歩をモネが踏みしめると、そのおとを合図に火照った浮浪者たちがとり囲む。からだを汚れた手の群れが貪り、短く鳴った悲鳴さえ浮浪者の波に飲まれて沈んだ。浮浪者たちの靴の下に小さな血溜まりが広がる。やがてひとりひとりと浮浪者が去っていき、あとには乾いた赤黒い欠片だけが残り、モネの姿はどこにもないはずなのだが、舞台にあがったエコが浮浪者のボロを着て袖にはけようとしているモネに抱きつき騒ぎだした。
マヤは慌ててスポットライトを倒しそうになる。照明の操作に集中していたので、持ち場からエコが消えていることに気づいていなかった。リハーサルを邪魔した報いは連帯でうけることになる。逃げだそうと劇場の裏口にまわってドアに手をかけたが、マヤは後ろから蹴り倒された。
三人の練習生に囲まれる。その後ろにモネもいる。モネのとり巻きで、崩れてはいるが大きなからだをした三人だ。煙を使った遊べる薬をばら撒いているとか、人攫いのグループを手伝って金をもらっているとか、背後にいるモネとあわせてこの三人の悪い噂をよくきいたが、オーナーから指導されている様子もなかった。形のいい子供のほうが、大人たちと似ているからだのほうが接しやすいのか、優遇されているのは明らかだった。
空き倉庫に連れこまれ、カーテンと鍵を閉められる。暗がりにエコもいたが、なにもわかっていない様子だった。「おまえがこの馬鹿をとめないからリハーサルが台無しだ」と三人のうち誰かがいった。床に叩きつけられ上着を脱がされる。からだを隠すために着るような服だから、あらわれた乱れのないマヤの肢体に、三人は暗がりのなかで幽かに浮かぶ手形の痣をみるまで意味がわからなそうな顔をしていた。
「なにこれ?」モネはしゃがみ込んでマヤの肌に触れた。「痣か。おもしろいな」
おもしろくない、とマヤがもらすと、三人は脚をあげた。モネがマヤを揺らし揉みあう。むかいあったマヤとモネは、痣をまぎらす暗がりのなかではみわけがつかず、ゆくえを失った三つのつまさきは空気を蹴った。
「おまえ舞台でろよ」
マヤの形を確かめながらモネはいう。お互いの目が近い。くちに甘い味がひろがる。唾を飲んだ。三人がモネに抗議しているうちにモネの手を払って抜けだす。
劇場をでて街をうろついた。労働を終えた工員たちとすれ違う。工場内の売り場で買った食品の袋を携えて、おなじリズムで靴底を鳴らす一団はうっくつとした行進にみえる。劇場のまえを通ると、行進の列から数人がチケット売り場に吸い込まれ、ほかの工員は路地の客ひきに手をひかれていった。劇場からもれる歌を、工員の薄給をむさぼる華やかな音楽をききながら、工員だけにはなりたくない、と呟いた。どのみち行き場もないマヤは劇場に戻るしかない。
キャットウォークで照明の電球を交換している最中、背後から三人の黒子が近づいてくるがマヤは振りむかない。担ぎあげられたときも、重さが失われたことを体感だけでしるような、呑み込めない表情を顔に貼りつけている。舞台にむかって投げだされ、みずからのからだを、重力がその指先で舞台床にむかってひいてからようやく短い声をもらす。落下しながら舞台上のモネと目があう。目をみひらいたまま、あらかじめ肩に装着してあったワイヤーがマヤのからだを空中に留め、そのままみつめあう。舞台から手を伸ばせば届く位置でしばらくそうしている。マヤがいる地点から天井まで青いベールがあしらわれている。マヤのからだはぼやけて、湖に映った影としてそこにある。ふたりはベールを挟んで指さきに触れる。モネは手ですくう。顔にかける。ひたいから顎まで伝って溢れる雫の波紋がおさまると、水面にむかって顔を沈める。手をとりあう。ずっとみている。一秒だけ息を忘れる。まざりあう呼吸のなかで、肺に水がはいって溺れてしまうまでそうしている。マヤのほうが耐えきれなくなって、顔を真っ赤に染めて泡を吹くと、ようやく我にかえったモネがひきあげた。顔をだすとそろそろ夕暮れだった。湖のゆるい波を斜めに跳ねたひかりが眩しくて、ふたりは目を細めた。こんなに綺麗な湖が街はずれにあるってしらなかったな、とマヤはいう。「秘密の場所だ」とモネが濡れた髪を振り払う。
「役者、やってみてどうだった?」
わかんないな。
「でも大成功だった」
まあね。
「これからもでろよ、舞台」
また湖役で?
「なんでも、おなじになってくれれば」
どうして?
「不安だったんだ、おまえに会うまで。ほかの子は誰も似ていないから」
そっか。
「照明係じゃもったいない」
次はなにをやる?
「双子がでてくるのがいいな」
なにかある?
ふたつの喉がビブラートしたその演目に水死するくだりはないので、ベールで霞ませなくてもいいように、ふたりはもっと姿を似せる必要がある。これ、と木陰においていた鞄からモネがナイフと袋をだした。袋には工場からくすねてきたものと薬品を混ぜた液体がはいっている。液体を煙草に染み込ませて、乾ききるまえに火をつけ吸いくちをふたりでまわした。呼吸の低いおとが耳の裏側で大きくなって、まばたきするたびにまぶたの裏で虹彩が波紋形にゆれる。自然とくちの端から弛緩した笑みをこぼした。痛みをからだの外におきざりにして、お互いをナイフで切りとりあう。ふたつの耳たぶと手足一本ずつの小指を、それぞれが解剖でもされない限りはみつからない場所に隠した。手の跡をどうしようか、と訊くまでもなくおなじようにしたらいいし、これからふたりはおなじなまえで呼ばれればいい。
もうそっくりだ。
動きもあわせなきゃ。
こう?
こうだよ。
わかってきた。
きいて、揃えて。
ふたりは呼吸のおとをきく。いち、に、さん、と鼓動を重ねあわせる。吸う快感も吐くおとも質量が大きい。吐いた煙がふたりを包んだ。ふたりはふたりの景色のなかで煙をいかようにも支配することができた。みたこともない動物をつくり、みたことのある豪華なたべものとやわらかなソファをつくった。煙で遊びながら、ふたりはなにもかもがじぶんたちのものであるように感じ、じじつ煙のなかで、触れられないすべてがえられるのだから、いまこのときすべてはふたりのものだった。煙のなかでの遊び惚けるふたりに星のない夜が分厚いベールをかけて、くらい湖のほとりでおなじ色の瞳だけひかる。
こっそりあとをつけていたエコが木陰から飛びだすと、追ってきたはずの、目あての子がふたりいることに驚いて転んでしまう。その様子を退屈そうに眺めてから、四つの瞳は寄りあって喉を鳴らした。ぴったりと組みあったわらいごえに囲まれてエコは泣きそうになる。ふたつの、まったく同一の歩調は重なりあったまま離れていく。どちらを追えばいいのかわからないまま、ただふたりのわらいごえの端をとって木霊させ、エコはその場で泣き崩れた。
工場からでる煙は年々濃くなって、鳥たちさえ逃げ場をなくしてぽつりぽつりと墜落した。冷え固まった煙のねばりと砕けた鳥の破片で道が汚れるから、さいきんは街の掃除人が忙しそうにしている。工員に盗ませた原料を買って持ち帰り、気化させて樹脂やほかの薬品と一緒に煙草に馴染ませる。モネは暇していると商品の葉をパイプに詰めてつぎつぎ吸ってしまう。夜もふけて客入りのおおい時間になったので裏口の鍵をあけた。最初の客が乱暴な足取りではいってくる。次々と客が流れ込み、からだの整った世代か、くだものをたらふくたべて育った形のいい若者からまえの席を埋めていく。工場帰りの客がたちみのスペースに目一杯ひしめいたら客席のライトも消え、闇のなかで幕だけ浮かびあがる。シンガーの甲高い声とともにひらいた舞台のうえをとりどりの光彩が跳ねまわり、踊り子たちはひかりの円と脚を遊ばせる。モネは後方の席の客にむけて視線と笑顔をばら撒いた。モネのからだに浮かぶ手形の痕はその階層に座るやや崩れたからだの客のうけがいい。幕が閉じて客からチップをうけとり終えたら、更衣室で衣装を雑に脱ぎすてて、あすの稽古に憂鬱になりながら路上にでる。もう夜もふけて風がつよい。煙は薄く、久々に星がみえる。チップをわたす際やけにシンガーにまとわりついていた客を路上でみかけた。視界にはいらないよう道を変えるか迷っていると、その客の背中は奥まった路地に吸い込まれていった。モネに呼び込まれた客は、煙草をためし吸いしたあと「五パック買うよ」とポケットの紙幣をまさぐりながら、モネの顔と首筋にはっきり残った痣をみて「あんた、きょう劇場で踊ってなかったか?」と呟いた。モネはテーブルのうえで脚を組み、こんな脚で踊れるかよ、と捻れた左脚を突きだした。たしかに踊るどころか歩くのにも不都合な脚だ。客はモネの脚に触れようとする。つかまれそうになり手を払うと、いきりたったように筋の浮いた腕はしなびて客席の床に倒れた。演出のためにつきだしたスラストステージの、手が伸びる距離まで踊りでなくてはならず、触れようとしてくる客も少なくない。「あとなんかい踊ればこの街からでられる」とひとりの踊り子がいった。「でてもなにも変わらないよ」とシンガーはながい髪を触った。「若いころは舞台を転々としてたけど、どこの街もおなじ。工場の番号とつくっているものが変わるだけ」シンガーは雀蜂というあだ名で、モネの親とおなじ年代の、もう往年の歌手だがいまだ人気だった。形がみずからに近くて若い演者をみにきている客が大半なのだから、劇場としても若い歌手を欲していたが、この広さのホール全体に響く声で歌い、喉を壊さないでいられる若者はそういない。モネはこの歳をとった歌手が好きではなかったが、嫌いにもなれなかった。雀蜂の歯は本数が多く、くちをひらくとミキサーでかき混ぜられたような口内がのぞける。その世代には珍しく崩れたからだを、酔った客なんかが嘲ると「このくちだからこの声で歌えるのだ」と鼻を鳴らした。「おまえら、ほんとうにつまらなそうに踊るね」雀蜂は舞台終わりの踊り子をみるといつもそういった。「そんなに金がほしいのか?」欲しいに決まっている、とモネは仕入れた薬品をひきとりながらいった。「まあそうだろうな」とオーナーはわらった。工場にいきたくはないからな、とモネはいった。「工場がなきゃこの商売も成りたたねえから、おまえも工員とおなじようなものだがな。その左脚じゃ工員以下かもしれないが」とオーナーが三重になった顎を震わせるたびに蹴りをいれたくなったが、そんなことさえモネの身では不可能だった。仕入れ代と上納金をかっさらって手短に去っていく肥満体を睨みつけ、左脚が痛むのでパイプに火をつけた。客にいくつかの商品をさばいたあと、三人の仲間を招きいれる。下調べしたオーナーの金庫の隠し場所と襲撃の実行日を手短に伝え、三人を追い払った。床につくとむかし負った脚の傷がひどく痛み、やまない苦痛のなかで意識を失う。脚をねじ切られる夢をみた。起きると塩が浮くような汗をかいている。なんともない、きょうも踊れる右脚に安堵して劇場にむかった。この日は工場の第一〇一塔の建設記念日で、工員には劇場のチケットが配られていた。「工場にはかなり儲けさせてもらった」オーナーは三重顎をふるわせながら踊り子たちの肩を叩いた。「必ず成功させてくれ」モネはまったく緊張しない。どれだけ下層の客があふれようと、もらえるチップはさほど変わらない。緞帳がひらき、オーバーチュアが鳴ったら動きだす。舞台袖で劇を眺めているオーナーの姿を確認し、モネは劇場の裏口にまわる。事前に警備を襲撃させ、警備員に変装していた三人の仲間と落ちあう。二人には見張りを任せ、残りのひとりを連れて支配人室につづく階段をのぼる。支配人室を掻きまわし、隠し戸のなかにみつけた金庫を仲間とひっぱりだした。バールでこじ開けると金庫の中身が勢いよく溢れだす。全身に浴びてモネはよろめく。ふらつきながらも、触れようとしてくる手や浴びた視線を振りまわすように方々にからだを散らして、いっそ客の波のなかへ身をさしだすかのようにモネは危うく踊る。すこしまえの舞台で奈落に落ちてしまった踊り子のことをおもいだしていた。普段は脚が砕けてしまわぬように慎重にステップを踏むが、落ちた踊り子の、ひびわれた、どこか安堵した顔をおもいだすと、どうしても靴を強く踏んでしまう。曲終わりに、たん、とつよく乾いたおとが鳴る。鳴ったおとの意味を、モネはじぶんの腹にあいた穴をみて、数秒遅れてから仲間たちに裏切られたと理解する。仲間の拳銃から硝煙がかおる。金庫からもれた、モネにとってはなんの価値もない、工場の製品たちが血塗れでわらっている。ふたりの警備員をつれて支配人室にはいってきたオーナーに肩を叩かれる。「金なんか奪ってどうする。この街からでるか。どこにいっても、おまえみたいなのはおなじように生きるしかないんだよ」とオーナーは銃口をモネの顎につきつけた。「おまえの仕事は街の、工員のための娯楽なんだから、おまえだってこの街の一部だろ」まえにそう雀蜂にいわれたことをおもいだし、うっくつとする。なんのために踊っているのかモネはとっくにわからなくなっている。演目の最後を朦朧とこなしていると、脚をたがえて転んでしまう。舞台は終わり幕がゆっくり閉じていく。二階のガラス張りになっている支配人室がモネの視界にはいる。金庫を抱えた人物が支配人に飛びかかり、そのままガラスを突き破るのがみえる。せっかちなカーテンコールを落ちてきた鈍い肉のおとがかき消す。金庫とオーナーに押し潰された客の手からパイプが転がり、散らばった工場の製品に火をつける。燃えあがる。炎の幕が劇場を覆っていく。モネは閉じていく幕のすきまからモネをみる。完全に幕が閉じて、客たちは劇場のドアに群がり怒号をあげる。燃える踊り子が客席に散っていく。ステージに壁としてたてられていた四枚のパネルに火がまわる。倒れたパネルがモネの右脚を挟む。気づいた客が駆け寄ったがひとりでは持ち上げられない。火のなかで、モネはきのうみた夢をおもいだす。熱でぼやける視界のなかで、パネルをもちあげようとした客がまったくおなじ姿で二人にふえ、ようやく脚が軽くなる。幻影のように重なるふたりの客はモネが礼をいうまえに倒れてきた柱に潰される。煙のなかを這っていき、いつまでも晴れない視界のなか、煙のくゆる路地にでたと気づくまでにはかなり時間がかかる。
工場が費用を負担し、葬式は一挙に行われた。ひとまず簡易的な墓石が建てられ、墓碑銘とおなじ大きさで工場製であることが刻まれている。本物の花など買えないから、みなパルプ紙でつくった造花を手に参列した。
双子の客の墓はどこか参列者にきき、モネは花をくべた。死んだ双子の客はむかしから街の病院で看護師として勤めていた、ときいた。双子のからだは焼けて残っていなかったから、劇場の焼け跡から集めることができた、あわせて人体ひとつをだいたい満たす骨をおなじ棺に納めた。「死ぬときまで一緒とはな」と参列者の一団からきこえる。参列者は好奇のまま棺をひらいたり閉じたりした。双子の遺体を窃視した目のなかで、双子に双子のもの珍しさをかざりたてて群がる。
列から抜けようとするとふいに押され、モネは墓のまえに倒れ込む。墓石にはじぶんのなまえが彫ってある。まだ埋められていない棺をあけ、黒焦げて顔もわからないじぶんと対面する。焼け残ったコートのポケットから熱で変形した鉄製の煙草入れがのぞいている。街にもどり、こっそり盗んだ煙草入れをペンチでねじあけ、懐かしい葉の匂いをかいだ。パイプに葉をつめて吸う。くゆらせた煙のなかで、骨が粉々になりそうな震えに襲われる。
外にでると、寒いのか暑いのかもわからない。風だけが立体で肌に触れた。街に漂う煙をこねて、幕のすきまからみえた姿をつくろうとするがうまくいかない。靴は自然と劇場のほうへむかったが、煙でぼやけてどこにむかっているのかをモネはしらない。
焼き崩れた劇場はいくつかの柱を残して、黒ずんだ骨とそのまわりを漂う塵の跡になっていた。救いようもない、黒ずんでもなお求める手が、ありもしないロープにむかってせめぎあっているようにモネにはみえている。焼け跡から離れようとすると声がきこえる。煙のなかで、それだけが確かな輪郭をもって。歌だと気づくまですこし時間がかかる。焼け跡から歌がきこえるなんてモネには想像もつかなかった。
歌声に近づくと、綺麗だった髪まで焼け焦げて、火傷でもう以前とは変わり果てた雀蜂が喉を鳴らしている。歌だけが、雀蜂を雀蜂だとモネにしらせる。焼け跡でなにをしているのか、意味もわからないまま眺めていると、いくつかの小さい影が、子供たちが煙のなかから抜けだしてくる。子供たちは歌に身をまかせ輪になって揺れる。モネよりもひとまわり小さい、もっと崩れた子たち。踊り子を真似ているのか、とモネは訊いた。子供は首かもわからない首を横にふる。雀蜂は晴れやかな顔で頷いて、さきほどより高らかに歌いあげる。「かつらくらい被ったらどうだ」と通行人から飛んできた野次も、雀蜂の歌にかき消され、どんな姿であれ雀蜂は雀蜂であることが歌うほどにつよく響く。歌の背景で子供たちのステップが心地よく鳴る。子供たちはじぶんだけのからだで、じぶんだけの踊りを、じぶんのからだでしか踊れない踊りを踊る。からだがひびわれても捉えなおして、はじめからそうであったかのようにあたらしい歩調でステップを踏む。子供たちがまいておこした風がつよい。煙は払われ、視界は水っぽく洗われる。だからこの風のなかでは、モネの目をかりて、子供たちのからだを、崩れていると、なにかが足りないと、形が違うと、あたりまえのように語ることはもうできない。観衆もみるのをやめて、輪のなかに加わり靴を鳴らす。いずれ外縁に客が集まるまで輪は煙を退けつづける。みずからは動かない目がすこしでも視線をむけたら、輪はほどけて散り散りになる。客の誰かがなまえを呼んでも決して振り返らない。
もう呼ぶなまえもない踊り子は窓のない路地にはいった。靴を脱ぐ。誰もいない背後に放る。踊り子はきょうはじめて踊る。踊るために踊る。呼吸を整える。いち、に、さん、といまよりずっと遠い場所からきこえている呼吸を数える。数えながら、裏拍も寄りつかない余白を探して、徐々にリズムを崩していく。呼吸はとなりあい、そのうちきこえなくなる。記憶の湖の底で息をひきとり、ただ過去から背を押す遺体として綺麗なまま凍っている。つまさきから崩れるようにひとつめを踏む。決してからだは崩れないと確信しながら。次のステップを路地の奥へ。もっと深いところへ。夜の幕はそろそろ西の地平にまきとられる。まだ名づけられていない朝のすきま、つよすぎてくらむ曙光のなか、どんな目も届かないひかりのなかへ踊り子は飛び込む。だから、ここからはもうみえない。
Kaguya Planetでは「となりあう呼吸」と世界観を共有する作品として執筆された暴力と破滅の運び手「灰から灰へ、塵から塵へ」、野咲タラ「透明な鳥の歌い方」が掲載されています。そして『SFG vol.4』には枯木さん自身による姉妹編「ささやかなおとの鳴る」が掲載されています。詳細はこちら。