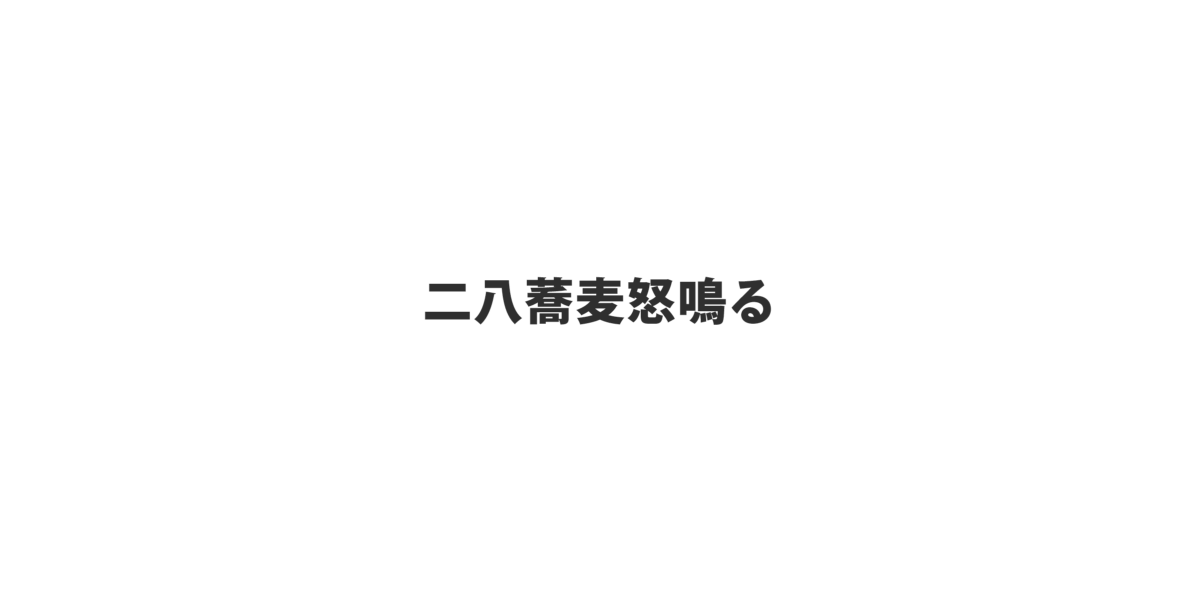「二八蕎麦怒鳴る」
「蕎麦が髪染めて悪いってのかよ」
蕎麦が、私を怒鳴った。
蕎麦は怒っていた。
まず、ソバの実を挽いた粉「蕎麦粉」を小麦粉と捏ね混ぜて生地を作る。それを麺棒でもって叩き、延ばし、また叩きを繰り返して、ランチョンマットのように平たくする。出来上がった蕎麦の生地をミルフィーユさながら四つ折りないし八つ折りにしたら、包丁を用いて一ミリ程度の細さに切る。そうして出来上がった麺が「蕎麦」だ。つまるところ蕎麦とはソバの実を使った生地で作る麺料理である。日本の庶民に長く親しまれている料理で、水にさらしてから皿に盛り別添えの「麺つゆ」につけて味わう「もり蕎麦」や、温かいまま醤油ベースのダシに入れて食べる「かけ蕎麦」など様々な食べ方がある。茹で上がりは素朴な灰色をしているが、蕎麦粉に使用するソバの実の部位や小麦粉の配合率によって濃淡が生まれ、細く白ければ「更科」、太く黒ければ「田舎蕎麦」といったように呼び名も変わる。粉の配合率が重視されるのも特徴で、例えば小麦粉二割、蕎麦粉八割で配合した蕎麦は「二八蕎麦」と称し、小麦粉の喉越しと蕎麦の風味が引き立て合う最上の配合とされる。
いま私を怒鳴っているのは、「もり蕎麦」だった。黒い平皿に「笊」という竹製の平たい網を敷いて、そのうえに蕎麦を山型に盛り付けてある。蕎麦粉八割、ナノマシン二割の二八蕎麦である。灰色であるはずの麺は、ギラギラと黄金色に輝いていた。昨日、別れるときは蕎麦らしい色をしていたのだが、私が出勤するまでに、自分を金色に染めたのだった。呆気にとられ言葉を失っていると、蕎麦は怒り始めたのだった。
「蕎麦が金髪にしちゃ悪いってのかよ!」
蕎麦は語気を強めた。皿の上で麺の塊が跳ねた。
嵐のように去来する疑問をぐっと呑みこんで、私は主任研究員のヤマモトに訊ねた。
「どうして蕎麦を金髪にしたんだ」
ヤマモトは蕎麦の隣で、ばつが悪そうに縮こまっていた。ヤマモトは染料が付着したゴム手袋を身につけていて、十中八九こいつが共犯だった。
「髪を染めたいと言うので……気になったんです。蕎麦の髪の毛ってどこだろうと」
「なんでもかんでも気になるんじゃないよ。常識というものがあるだろう」
「蕎麦の部分を染めたら満足してくれた以上、蕎麦部分が毛髪なんだと思うんです。毛髪は頭から生えるものですから。この場合は皿か笊が『頭』の役割を果たしているのではないでしょうか。蕎麦としての自我と肉体感覚が、盛りつけられた器にまで延伸している」
言えばいいってもんじゃないんだよ。私は黄金に輝く蕎麦を見た。やればいいってもんじゃないんだよ。ということはウチの上層部に言わねばならない。
AIに人工意識を持たせる。ないし、意識と酷似した感覚を学習させる。それが私の勤める部署の基幹プロジェクトである。AI用の準・自律思考パッケージを我が社が発売してから数年がすぎた。膨大な数の思考・感情パターンをクラウドにプールし、ユーザーは好みの考え方を手持ちのAIにダウンロードする。意識の生成は難しいが、思考や感情は突き詰めると幼少期から学習したパターンの反復に過ぎない。人間のこころを機械的に捉えるところから始まったプロジェクトは今のところ順調で、自律思考の謳い文句が消費者庁から是正勧告を受け「準・自律思考」と改名したくらいがケチのつきどころだった。
しかし早晩、考え方のパターンは尽きてしまうだろう。考え方は価値観と同義だと我が社は捉えている。価値観を増やすには、複数の主観を用意する必要がある。つまり我が社は新しい主観を開発しようとしていた。生物・無生物を問わず様々な主観を。私に与えられた開発対象は蕎麦だった。もちろん多難である。
「蕎麦が金色になっちゃいけないってのかよ」
テーブルの上に置かれたもり蕎麦がぐるぐると回転した。怒っていた。機械的な光沢の合間からダークピンクの麺が覗いた。私は見逃さなかった。
「メッシュまで入れたのか」と私はヤマモトに聞いた。
「最初は美容院に連れて行ったんです。麺類は受け入れ可能なのか気になりまして」
私は想像した。美容院の椅子に蕎麦が置かれている、いや座っている。
「ダメだったろう」
「ハサミで蕎麦を梳く工程で、蕎麦が暴れました」
そこまでは行けたのか。
「しゃあないだろ。怖かったんだから。身体にハサミ入れられるなんて」
と蕎麦が言った。ふてくされていた。蕎麦の主観上では肉体と頭髪が未分化なのだなと私は思った。蕎麦には見た目上の四肢や頭髪は存在していないが、彼の自意識のうえでは髪の毛と肉体の概念が確かに発生している。今のところ、「蕎麦として生まれた蕎麦」ではなく「蕎麦の肉体を有して生まれたヒト」として自意識が成長をみていた。今回も失敗したようだ。どこかで肉体と精神が合致すれば「蕎麦として生まれた蕎麦」の自我が芽生えるはずだ。こういうことを半年やっている。何のために生きているのだろうか私は。
私は冷蔵庫を開けた。ドアポケットで麺つゆがキンキンに冷えている。透明なグラスに麺つゆを注いで、同じく冷やしていたミネラルォーターで三倍に割った。ヤマモトと蕎麦が同時に青ざめた。ヤマモトが叫んだ。
「食べちゃうんですか!」
何を今さら。研究データのバックアップだけ取ったら、失敗した蕎麦は食べているではないか。私はペン立てから割りばしを取り出し、そして、ちょっと待て。蕎麦が青ざめた?
私は卓上の蕎麦を見た。蕎麦は震えていた。全ての麺が、海のようなブルーに色を変えていた。私はヤマモトを振り仰いだ。
「ええとですね……染色剤で染めると食用には適さないじゃないですか。それでその、蕎麦の全ゲノムは解読されているわけですから……様々の色合いに変化できるよう編集を施した的なことです」
「できるからってやるんじゃないよ!」
それでヤマモトは食べることに慄いたのか。確かに普通の蕎麦よりも圧倒的に金と手間がかかっている。私は怒りを呑みこんだ。ただでさえ犬猫の担当より予算を削られているのである。爪に火を点すような倹約の積み重ねを染髪なんぞで吹き飛ばして。
私は、いちど止めた手を再び割り箸にかけた。ヤマモトが叫んだ。
「すごいお金がかかってるんですよ! もう少し様子を見ましょうよ!」
「いいや食べる! 早くネギ刻んで持ってこい!」
私も叫んだ。蕎麦は凍り付いたように動かない。私はもり蕎麦の山に箸を伸ばした。
「蕎麦殺し!」
蕎麦も叫んだ。その程度で怯む私ではない。何千皿と蕎麦を平らげ、そのつど蕎麦の断末魔を聞いている。そうまでして実験に用いた蕎麦を食う理由は昼飯代を浮かすため、処分の手間をおさえるためだ―――処分申請を出すよりも機密ごと胃で溶かしたほうが早い!
混乱した蕎麦は、次々と色を変えた。死人のような青から、切断したての傷口のようにジクジクした赤へ、濁った排水のような緑色へ、錆びたステンレスのような黒と銀色へ。
見ているうちに箸が止まった。どうしても手を付けることができなかった。いつもなら一気呵成に蕎麦をたぐって一分もせず平らげるというのに。
くるくると変転する色彩が、悉く、まずそうだった。ヤマモトがゲノムを弄っただけなのだから、蕎麦としての成分も味わいも、これまでと大して変わらないはずだ。食べられるはずだ。それなのに私の箸は進まなかった。一口たりとも食べることが出来なかった。
「……色がマズそうで食えない……」
私は傍らの椅子に座りこみ、白状した。
次の瞬間、激怒したのは蕎麦だった。
「―――随分と勝手なんじゃないのかよ、あんたよ!」
蕎麦は煮詰めたトマトのように真赤になって大声を上げた。水滴がぴちゃぴちゃと飛んで私の顔にかかった。
「色が蕎麦っぽくなくなったら途端に食えないって? 冗談じゃねえよ、こちとら食われるために造られた命だよ! それがたかが色が違っただけで食えねえだ? 勝手ぬかすんじゃねえぞ腰抜け! これまでどれだけ食らってきたと思ってんだ!」
私は顔を上げた。蕎麦の物言いは、実に蕎麦的だった。まさか蕎麦としての自我が芽生えかけているのか。思えば蕎麦と口論するのは今回が初めて、食べなかったのも今回が初めてだ。危機に瀕したこと、蕎麦としての機能を侮辱されたことで、蕎麦に蕎麦の自我が目覚めたのかもしれない。私はさらに挑発した。
「変な色の蕎麦は食いたくない!」
「食われる側にも自由があるだろうが!」
蕎麦は怒鳴った。
「この際さあ食われるのはヨシとするよ。食われるにしても色くらい決めさせてくれよ! 食う側に都合のいい色で居てくれなんて要求されるんじゃ、いっくらこっちに自意識あっても意味ないよ! 技術が進んだってね、外圧が自由の幅を規定してくるってェ根本の仕組みが変わらねんじゃどうしようもない! 気持ちを変えたほうが良いのは人間のほうじゃないの! テメエ人間やめちまえよ!」
蕎麦は飛び上がると私の頭を打った。
「上等だこの野郎! 揉み海苔を散らしてやる!」
私は蕎麦に掴みかかった。顛末を黙って見ていたヤマモトが叫んだ。
「蕎麦と喧嘩しないでください!」
蕎麦は床の上を滑って私から逃れ、ヤマモトの足首に縋りついた。
「あいつ無茶苦茶だよ。蕎麦の気持ちが何も分かってねえ」
「君も人間の気持ちを分かっておくれ。僕たちは長く、美味しそうな蕎麦とだけ付き合ってきた。不味そうな蕎麦を蕎麦として尊重する価値観は、まだ育っていないんだ」
蕎麦は溜息をつくと、紫と黄緑色の斑模様を体表に浮かべ、ぺかぺかと光った。
私は涙を拭って立ち上がった。私は蕎麦と分かりあえない。本当は分かりあわなくてはいけないのは理解しているが、積重ねた人生が首を縦に振らせてくれない。私はもう昔の人間なのだ。だから私は私なりに、不思議な色の蕎麦を美味しく頂いてみせる。元の色が分からなくなるまでケチャップ炒めにしてやるのだ。