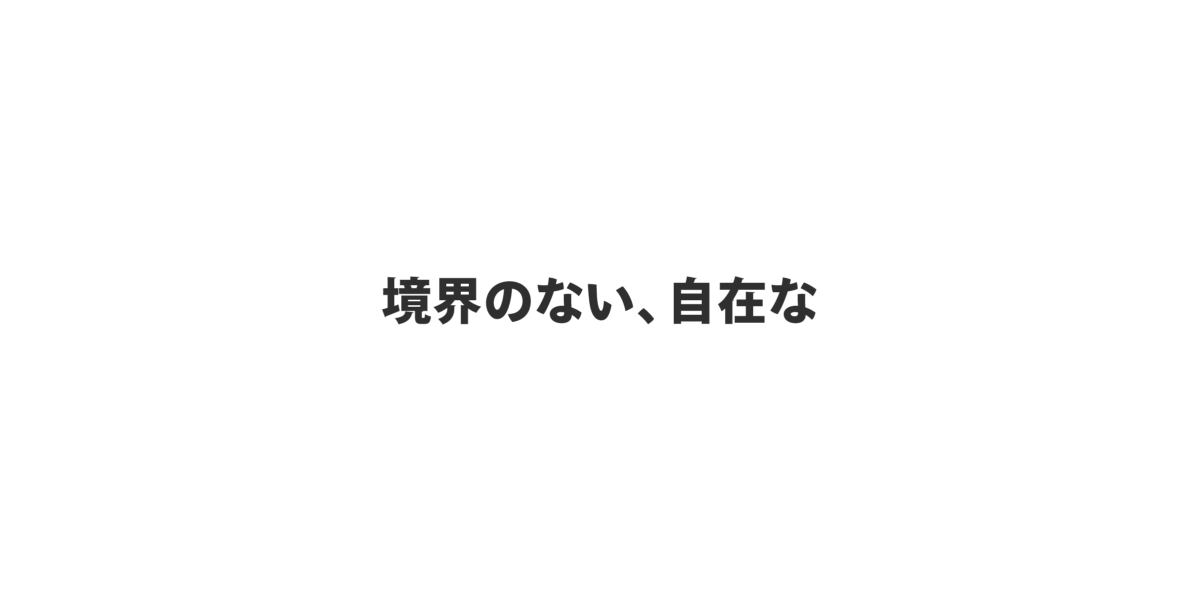第二回かぐやSFコンテスト読者賞受賞作品
「境界のない、自在な」
興奮してはしゃいでいたミミも、手術室の無機質さ、医者たちのくぐもった眼をのぞいて、少し怖くなったのか、唇をぎゅっと窄めた。医者の手が固いくちをこじあけてチューブを差し込む。麻酔やその他の、無学な私には計り知れない薬品が全身にまわると、医者たちは慣れた手つきでミミの皮膚を剥がしていった。さきほどまで小さな城壁だった唇さえ、すみやかに切除される。筋肉だけになった娘の姿は、人体標本でもみせられているようで、血縁や親心とか、そういう感情を飛び越えて、生理的にみていられなくなり待合室に戻った。曽祖母は連れてこなかった。手術のこともいわなかったし、そもそも彼女はよくわかっていない。予防接種や歯科矯正、曽祖母が産まれた集落でいうと割礼のようなもの、といっても納得はしないだろう。この光景をみせたら、私や病院を悪霊に憑かれていると勘違いして、そこらの草を摘んで儀式的な行動にでるのは目にみえていた。集めた草木がじぶんの故郷のものとはかけ離れていることに、認知症の曽祖母は火をつけてからも気づかないだろう。
ミミは嬉しそうだった。術後に全身を覆った灰汁色のあたらしい皮膚は、学校で流行っているアニメのキャラクターに似ているそうだ。数時間もすると、その色にも飽きて、青く染めた肌のうえで魚を泳がせはじめた。そんなものはみたこともなかったから、勝手に私のクレジットを使ったのかと驚いたけれど、どうやら有料のものではなかった。近所のひとつ上の子に教えてもらったらしい。
肌の海で泳ぐ魚に触れようと、曽祖母はミミを突いたり抱きしめたりを繰り返し、古い故郷の言葉で精霊との対話を試みた。曽祖母は原始的な生活を営む少数民族のなかで少女期を過ごした。成人するまえに都市開発で集落を追われ、街にうつり住んだあとは出版社で働きながら五人も産み育てた。患ってからは意識が朦朧として、たいていは少女のころの、自然のなかで狩りと農作をし、あらゆる自然現象を神の名前で呼んでいた時代に巻き戻っている。どこかから枝をもってきた曽祖母が、モリをつくって魚を捕ろうとしている。ミミに魚を消すようにいうと、こんどは全身に広がった空を鷹が旋回した。この家には子供が二人いるようなものだ。養育と介護を引き受けたのは私だから文句はいえないけれど、こんなに肩が凝るとは知らなかった。曽祖母はモリを矢にするために先端をより深く削り、散らばった木片を自動掃除機が吸った。曽祖母が壊してしまうので、今年にはいってから三回も修理にだしている。
校門まで連れて行くと、ミミは他の子に手を取られて校舎まで走っていった。子供たちは、みんなめまぐるしく色が変わるので、ミミがどこにいるのかすぐに追えなくなる。ここの地区では、近い歳の子はみんな人工皮膚への切り替えを済ませていた。うちは遅いほうだ。ちょっと家計に痛かったが、ミミが地肌でいるのを嫌がった。格好悪いし、のけものにされたくない。余裕のない地区では十代中盤になっても地肌のままの子もいて、あまり良い扱いは受けないときいていた。私が十代のときはそこまで重要な身体矯正じゃなかったけれど、文化的にはちょうど推奨され始めてはいた。肌の色で争っていた時代を鑑みれば、建設的な思想におもえる。健康上のメリットも大きかった。できものや日焼けに悩まされることもない。子供の出産令が市から届いたタイミングで、私も肌をすべて換装した。普段は元の肌の色を固定して、たまに明度を変えるようにしている。親の肌が特定の文化圏の血をのぞかせていると、周囲の親とのつきあい、学内でのコミュケーションで不利に働く傾向にあると市のガイドブックに書いてあった。昇降口からこっちをみている子がいたので、手を振った。あの子はあんたの子じゃないよ、と曽祖母が明晰な声でいった。
六台目の掃除機を壊している曽祖母を尻目に、ひき肉を整形する。今日はハンバーグだ。手料理なんてだいぶ古臭い趣味だが、調理中は無心で、考えずにいられるので好きだった。ミミは課外授業で少し帰りが遅い。駄々をこねるので、先に曽祖母の分だけ焼いてしまう。彼女はとても美味しそうにたべる。意識だけ二世紀ほど若返っている彼女は、じぶんの内臓のほとんどが機械化されているなんて知りはしないだろう。生活に飽きた祖母と母はみずから眠ってしまった。男たちは顔も知らない。調べてもいいけれど、ただの精子提供者に、なにかしらの郷愁を抱けるとはおもえない。
私はいつにしようか、と最近考える。子育てが終わったら? 曽祖母が亡くなったら? 自己決定能力がないとみなされた曽祖母は寿命まで生きるだろう。いまや寿命で亡くなるひとなんてまずいない。ミミが大人になったあとは、曽祖母は施設に預けてもいいかもしれない。
学校から通知が届くとともに、ミミが帰ってくる。肌が傷ついている。皮膚の表面につくられた模様や色ではなく、あきらかに立体的な、ほんものの傷だった。曽祖母が止血しようと駆け寄ったけれど、このあたらしい皮膚は血を流さない。
母親として学校に呼び出されたのは初めてだった。口頭、書面、映像の順で経緯を説明された。ミミは加害者だった。地肌の子へ、紫色の肌の一団が石を投げて遊んでいる。葡萄のふさみたいに寄りあう子供たちのなかにミミもいる。地肌の子は反撃にでる。ミミは押し倒される。地肌の子の、絵の描きやすそうな肌から滴った血をミミが被る。ひかれた赤い線をなぞるように、いつの間にかそこにあった鋭利なものでミミが削られる。
地肌の子の母親は、服からはみでる部分だけ人工皮膚にしていた。事務的な手続き、法的な手続き、転校の手続きを済ませて家に帰る。ミミの皮膚はだいぶ損傷していて、身体機能の修復は緊急病院で行なってくれたけれど、色彩の機能はとまったまま。完全な修復手術ははやくて一ヶ月後。初めて受けた暴力に、ミミはずっと震えている。与えるときは、暴力を与えたときはなにを考えていたのだろう。想像力を養うカリキュラムを増やしたほうがいいのかも。あとは心療内科への通院。いまより少し学費の高い学校を探す。
転校してからのほうが状況はひどくなった。事件のあとで暗くなっていたのに加えて、学校でなに色にもなれない肌を馬鹿にされて、ミミの精神はよくない方向に転がっているようだった。心療内科から様々なセラピーを勧められている。ミミにとってなにが最適か調べてもわからない。検索した内容はすべて正しく、そして間違っているようにおもえる。どれがミミにあてはまるのか、私の娘はどのパターンなのか。
昼食をつくろう、ちょっと考えることから離れよう、とキッチンに立つと戸棚に白い手形をみつける。振り返ると、裸の曽祖母が立っている。指が白い粉で染まっている。全身に模様が描かれ、老体が揺れるたび肌から粉が舞う。ミミも喜んでた、と曽祖母がいう。色がないって泣いてたから、うん、もう年頃の女だから、少しはやいけれど。ミミの部屋をあけるとベッドが粉まみれだ。どこかに預ける余裕もなく、曽祖母にはコートだけ羽織らせて玄関まで引っ張った。わけのわからないペイントを施された偽野生児が、私の娘が、虹色の子供たちに取り囲まれている図が浮かぶ。汗のかわりに肌が冷たくなる。
学校は野生児の集落になっていた。子供たちはみんな肌に、ミミからトレースした模様を浮かべている。教師が、ちょうどインディアンの歴史の授業にはいったところで、と笑う。私たちはアメリカ先住民じゃない、国も違う、と曽祖母は叫ぶが誰もきいていない。ミミは集落の女王になって、大きな葉で扇がれている。祭りが終わったあとも、浮かれてこの格好で歩いて帰るといいはる。
ずっと住んでいる街並みなのに見覚えがなくて、いつも迷いそうになる。建てものも、植栽も、ひとも、色と模様が数秒ごとにうつろって忙しない。彩りに、風景のなかに記憶がない。怖いね、と耳元でいわれる。曽祖母の、縞模様の顔が近い。老いて、その時間の分だけ、濁った知的な眼が私をのぞいている。やっていることはおなじなんだ。どうにかしようと、おもいどおりにしようとする。精霊を呼ぶ、機械をつくる、乳のない母親が粉ミルクを沸かす、おなじだってわかっているよ、私は。だから、でも怖いとだけあんたにいっておく。こんなに自在な、なに色でもなくなって……次は形まで失うのかもしれないね。でもその色と形があたらしい親で、子で、時代なんだろうね。舌が動きをとめると、曽祖母の眼は透き通って、またすべもなく無垢な、なめらかな表情に帰っていった。
眼を離していた。ミミがいない。街に溶けてみつからない、どの子がミミかわからない。怖いね、が響く。探そうとすればするほど、あまりに多彩で境目がわからなくなる。曽祖母の肩を掴んだ。魔術でもなんでもいいから、ミミをみつけて欲しい。よそもののお願いはきけない、と縞模様の幼い顔がいう。唇の動きにあわせて粉が飛んでくる。彼女の瞳に映る、私の顔は誰にも似ていない。曽祖母の肌に触れて、その色と模様を肌理まで受け継ごうとするけれど、でもGPSの存在をおもいだしてミミの位置に足が向かう。噴水のグラフィックのまえで魚捕りの真似をしているミミをみつけて、抱きしめる。
八台目の掃除機が壊れた日。ボルシチをつくる。焼きあがると同時に、ミミが帰ってくる。靴先が血で染まっている。すぐに靴を脱がせた。人工皮膚が止血してくれていて、一旦は安心する。小指がない子のほうが多いの、とミミはいう。キッチンから包丁が一本なくなっていたことにいまさら気づく。救急病院への連絡のあと、私は各院の金額をみくらべながら、いまはなに色の血液が流行っているの? と娘にきいた。