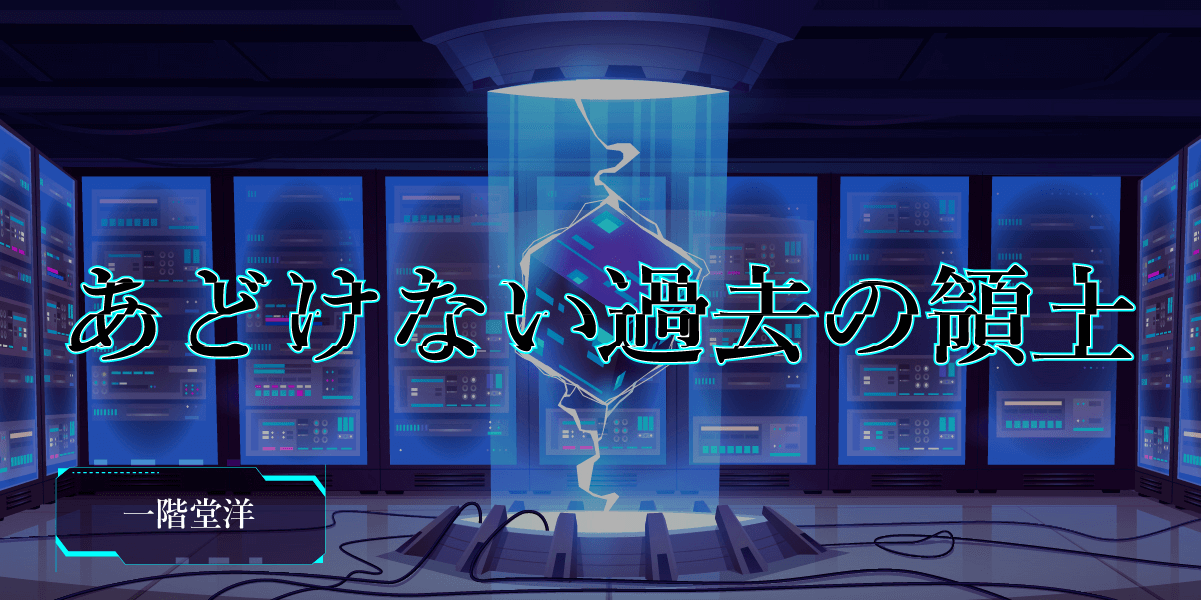先行公開日:2022.4.23 一般公開日:2022.6.4
一階堂洋「あどけない過去の領土」
12,602字
1
そこの中年、と声をかけた。七月の湿った夜だった。草と土の匂いがした。頭上では羽虫を腹に蓄えた街灯がちらついている。星が低い位置で光っている。
男は自家用車を降りたばかりだった。薄青の作業着を着ている。顔はよく見えない。
私は二歩近づいた。その、と男が言った。どなたでしょうか。
「あたしは『対話処理サービス』の職員。研究者の使いっぱしりをやってる。名刺やるよ。あんたは望月さんだよな」
彼は眼鏡をかけた男で、少し太り気味だった。数年は笑ったことがないという顔をしていた。彼は私の名刺を眺めた。
「ミナイさん……どこかで会ったことがありますか」
「ないだろね。でもあんたのことはよく知ってる。職場も知ってる。離婚したことも知ってる。あんたの娘さんが引きこもりなのも知ってる。他にも知ってて欲しいことはある?」
彼は私と目を合わせなかった。
「手短に言うと、あんたの娘さんと話がしたいんだよ」
望月は眼鏡をとって、目をつむった。しばらく時間がたった。もう夜ですよ、と彼は短く告げた。非常識でしょう。そして、自分がやっと通れるくらい細くドアを開けて家の中に入った。鍵が回った。太ったリスみたいな男だ。
「ハイ」
頭上から声がした。少女が二階の窓から見下ろしている。彼女が手をひらひらと振った。私は同じように手を振った。
「お父さんとどういう関係?」
「気になる?」
「クソ悪いなら気になる」
「じゃあクソ悪い。ちょっと手伝ってくれない? あたしは怪しいけど悪いやつじゃない」
「いくら?」
「は?」
少女は表情を変えなかった。手伝ったら何円もらえるの。
「この守銭奴。何でも好きなことをしてやるよ」
子供は髪を指に巻きつけた。まあ、いいよ、と答えた。そしてベランダから消えた。しばらくして玄関のドアが開く。白い手が出てきて手招きをした。
たたきは綺麗に掃き清められていた。下駄箱の上には何枚か写真が飾ってある。どれも褪色していて、見るたびに記憶から引き伸ばさないといけないように思えた。彼女は私を眺めて、体をぶるっと震わせた。少女の後について二階に上がる。
「どうしてあたしを家に入れようと思った?」
少女は振り向かずに答える。
「お父さんと仲が悪くて髪の色がおかしいから」
小さい部屋はがらんとしていた。折りたたみベッドが部屋の隅にしまわれている。ほとんど空の本棚が置かれている。パソコンのそばにVRグラスが打ち捨てられている。典型的なインターネット中毒の子供、ローブナーを十七時間ぶっ続けでやるタイプの子供だ。彼女は椅子に座った。プラスチック製のマグカップから一口すすった。話って何。
私はリュックから携帯端末を取り出した。
「あんたが『最適化された碧素』さん? これ命名あんた? ちょっとひどいぞ」
「超昔に自動でつけられたやつ。どうして知ってるんですか」
「ディスプレイつけてみな」
少女は画面の横に手を触れた。ローブナーという社会交流基盤が起動している。三次元モデルのキャラクターが座っている。目の前にはおとなしそうな黒髪のアバターがいる。頭上に『ミナイ』と書かれている。私は端末を操作する。スクリーンネームがオレンジ色に変わる。そして吹き出しに文字が映る。
>理由と手段のどっちが知りたい?
「あたしはミナイ。対話処理サービスのメンテナ。ローブナーでは色々どうも」
少女が舌打ちをする。
「だましたんですか? 久しぶりに普通の人と会ったと思ったのに」
「そもそも聞かれてない」
鳥がどこかの木を離れる音がした。少女は椅子の上に脚を上げた。会話を録音してもいいですか、あなたが私の罪状を述べるのは結構なことだけど。私は頷く。
それで? と碧素が尋ねた。
「あんたに話してほしいLOKAボットがある。うまくいったら何でもする」
「やらなかったら?」
「何も起こらないといいよな」
碧素はしばらく黙っていた。そして、トラックパッド付きのキーボードを引き寄せて、デジタルアパレルのサイトを示した。
「ここの服が欲しいんだけど」
何でもって言っただろと返して、チャットボットのスナップショットを実体化した。デフォルトのアバターに縮退したボットが現れる。
「何を聞けばいいの?」
「こいつに『五年前の夏、富士川について書かれた書類は誰が書いたか教えて』って訊いてほしい」
彼女は部屋のどこかを指さして、「富士川? そこの?」と訊く。私は頷く。
少女は疑わしげに私を眺める。そして諦めたように息をついた。こんにちは、とボットに話しかける。当たり障りのない返答が返ってきた。「あなたの名前は何?」「私はLOKAといいます。あなたは?」自明な会話を素早く積み重ねていった。私は端末をトレースモードで動かす。旧世代のチャットボットに同じ会話が流されて、尤度が評価される。普通の対話シークエンスに見える。
ドアがノックされる。キーボードを叩く指が止まった。短い沈黙の後で、父親がドアを開けた。彼は唇を何度かなめて、何か言おうと右手を軽く挙げた。その時、「何でもしていいって言ってたじゃん!」と碧素が声を荒らげた。
彼女は椅子を立って、マグカップを投げつけた。それがドア枠に当たる。水が飛び散って彼の顔にかかる。少女が次に投げるものを物色した。私はそれを制した。してはいけないと告げた。私は弁解らしきものをした。
「変なことはしてない。録音もある」
ぬるい空気がドアから流れ込んでくる。父親はコップを拾い上げて、服の裾で水を拭き取った。何かばらばらと言葉をこぼした。要約すると、階下に降りてきて話をしようと言っていた。そしてドアを閉めた。
間。
画面内の少女がAFKに切り替わり、対話相手を失ったチャットボットが消滅した。こっちの世界でも少女はややAFKだったが、私が消えることはなかった。彼女が窓ガラスを眺めて、
「好きなものをくれるんですか? あなたのやりたいことができたら」
と訊いた。ああ、と彼女に告げた。碧素は品定めをするような顔をした。
「じゃあ、お母さんに会わせてくれますか? 私のですよ、あなたのじゃなくて。場所は知らないし、今なにやってるかも知らないけど」
おそらく法に触れない範囲で実行できると言った。少女は頬をぴくりと引きつらせた。
「多分、下の階で餃子が待ってますよ。お父さんはケンカをすると餃子を包むんです。クソバカですよね」
父娘のどちらに向かって話すか悩んだ末、大皿の上の餃子に向かって話すことにした。
ご存知の通り、チャットボット大規模全知識アーキテクチャは、知識グラフの上に構築された対話用言語モデルだ。LOKAは過去の会話とデータを元に、別の会話を生成する。
しかし一方、LOKAは文章や対話シークエンスのいくつかを丸暗記している。つまり、会話を生成するのではなく、再現することがある。
「ある文書を探してほしいと頼まれててね。昔は公開されてたけど、誰かがこっそり消しやがった文書だ。それをLOKAは覚えてるとあたしたちは踏んでる。
碧素さん、あんたは――それがどういう賜物か知らないが――LOKAの生成されたものと、本当の会話を区別できる。あんたがそれを何に使ってたかには目をつぶるとして、原理的には、あんたを縛り上げて、ずっとLOKAと会話させてれば、いずれそれを見つけられる」
望月が豆板醤を溶かす手を止めた。雑誌の知識ですが、と続けた。
「学習データも政府がLOKAと一緒に召し上げたんじゃないんですか」
はは、と笑って餃子を口に入れた。口の中を空にするまで、父娘は私の顔を眺めていた。
「ゼタバイト級のデータをどこに保存するんだ。北海道を更地にするか? 牛さんを屠って? 対話処理サービスが持ってるのはモデルだけ」
碧素が口を挟んだ。
「さっきのチャットボットがその記憶の近くにいるってわけ?」
頷く。餃子を二つ食べる。
お父さん、これは犯罪じゃないからね、と碧素が告げた。だからお父さんに何かを言われる筋合いはない。父は何も言わなかった。
2
次の金曜日の朝、始発に乗って山梨に向かった。望月が「フォーマルな服で来ていただければ」と言ってきたので、私はフォーマルと推定されるところの服装をしていた。望月は私を見て怪訝そうな顔をした。目を合わせずに「娘をよろしくお願いします」と告げて、玄関を出ていった。ダイハツの車が遠ざかる音が残った。少女は階段の下から三段目に立っている。私よりも高い目線を保っている。
「ミナイさん、意外と普通ですよね。メンテナってもっと……こう……」
キーボードから手を離して、碧素が尋ねてきた。ボットを起動してから、もう二時間近く会話をしていたが、芳しい兆候は見えなかった。
「あたしは比較的善良な方だから」
対話処理サービスはまともな職場ではない。この第三セクターが作られたのは、数年前、アメリカのIT企業が作ったチャットボットが、プロパガンダと陰謀論を拡散したことに端を発する。政治家たちに注目! あいつらは若い少女を監禁して、その細い金髪から興奮物質を抽出しているんだ! 当時のデジタル庁はこれを重く見て――正確には、重く見ることで予算を消化しようとして――チャットボットの接収を決定した。巨大言語モデルの保守と運用。そして私の職場ができた。干からびたワニを模したロゴまで作られた。
廉価な人手を確保するために、『サービス』は私のような就職先のないポスドクを大量に雇い入れることになった。考えてみて欲しい。一般ユーザーを制御できるような権力を、研究一筋で頑張ってきたポスドクに与えたらどうなるか。彼らは未成年のユーザーを恫喝したり、モデルに難癖をつけてみかじめ料をせしめることを覚えた。要するにカスになった。
少女は指に髪を巻き付けたり、先っぽを噛んだりしていた。汚いからやめろと言おうとしたところで、彼女が「お願いがあるんですけど」と言った。
「勉強、見てもらえませんか。化学、バケ学のほう」
「もちろんいいよ。あんたと遊んでても時給は発生するし」
彼女は教科書をディスプレイに映した。有機化合物の炭素・水素の質量比を次の実験結果から求めよ、と述べられている。「高校生は難しいことをやってるんだな」とつぶやいた。
「もしかして解けないんですか」
「は? あんたにも考える時間をあげただけだ」
それから数分後、私は解説を熟読し、更に数分考え、原子量というのは実際のところ、量ではなく比ではないかという仮説にたどり着いた。子供は『バカを見る顔』をした。
彼女は「この問題は」と話を始めた。増加した二酸化炭素の質量から炭素を逆算し、吸い取った水から水素を逆算した。
「なんかクソ普通に分かっちゃった。私、頭いいかも」
そうとなれば、なぜ私は屈辱を受けないといけなかったのだろうか? 私の考えをよそに、少女は指を複雑に絡めながら言う。勉強は好きなんですよ、こうやって人と話すのも。
「じゃ高校に行け。大学に行ってもいい。東京には腐るほど大学がある。実際いくつかは腐ってる」
少女はマグカップの水を飲み干した。Tシャツの裾で水滴を拭った。窓の向こうで、大きな鳥が滑空していくのが見えた。
「できたら行きたいですよ。高校だって引っ越せば通えるところはあるし……でもほら、通信教育もあるし、この家もあるし」
七月が終わった。碧素の母親は二十万で見つけられた。東京の駒込で再婚していた。病気もなし、怪我もなし。
私は毎週金曜日に中央線と身延線を使って山梨まででかけた。玄関のベルを鳴らすと、少女がドアを開けた。棒アイスを持っていた。膝で折って、片方をよこしてきた。今日は滴定について教えてあげますよ、と肩をたたいてきた。もちろん、私は別に教えてくれとは頼んでいない。
「ミナイさんちょっと」
碧素が短く呟いた。私は画面を見る。極めて普通の会話が流れている。モデルの尤度も安定している。このまま会話を続けると……と少女が囁いて、またありきたりな返答を返す。
「小森さんが言ったこと覚えてる?」とLOKAが告げる。千塚の交差点で事故があったって話? と碧素が打ち込む。ボットが答えを返す。それ、コープの前、夜だったよ、めちゃくちゃ暑い日、夜で三十五度とか言った日で、事故、子供が車にってやつ。少女が注意深く返答をタイプする。
古い言語モデルに同じ会話を流す。極めて小さい尤度が出てくる。つまり、LOKA以外のモデルがこの会話を生成することは、ほぼありえない。これはモデルの優劣に基づくものではない。そうではなくて、LOKAはこう考えている――この会話はありうる。なぜなら、この会話が実際にあったことを私は覚えているから。損失関数の奇妙な谷にこの会話は存在している。
私は驚く。この会話が存在することではなく、この子がそれを探し出し、きちんと追跡できることに。
「わかるんですよ。言葉の向こうに本当の人がいるかどうか。それがどう進んでいったか。みんなはその違いが分からないみたいだけど……」
皮肉なもんだ、と私は呟いた。ローブナーはLOKAの誤解を解くための遊びだったんだよ。チャットボットはSNSに出てきても絶対にバレる、プロパガンダなんか流しようがないっていうのが目的だった。音声合成はできるかもしれない、でも、日本語の生成は難しいとみんな思ってた。少女は肩をすくめた。
ディスプレイにはローブナーの交流ワールドが表示されている。多くのアバターがひしめき合っている。ゲームを共有し、写真を撮り合っている。複雑な反射シェーダーと衝突演算を使って、お互いのグラフィックプロセッサの強度を競っているアホもいる。誰もがLOKAを使って喋っている。滞りのない会話が世界を埋めていく。それが彼らのやりたかったことなんだろう。
昼過ぎに家を出た。旅館でトルーマン・カポーティの小説を読んでいると、碧素が電話をかけてきた。
「もしもし」
「明日暇ですか?」
「は?」
「明日暇ですよね?」
私はスピーカーを見た。もちろん何も起きない。
「暇だけど」
「じゃあちょっと遊びましょう。外に出たくなったんです」
東向きの窓からは、深い色の富士山がよく見えた。
「どっか行きたい場所ありますか」
彼女の父親が車を出すらしかった。私は少し考えた。
「滝があるだろ、トリップアドバイザーに載ってるやつ。涼しいらしいぞ」
彼女は電話を切った。千行くらいスカラのコードを書くと、夜になっていた。風呂のそばの自動販売機でポカリスエットを買った。店番代わりの柴犬が眠たげに歩いてきた。私は彼と(一方的な)話をした。
深い渓谷の根本に望月が車を停めた。目の前に滝が見えた。我々はウィンドウを下げて、それをしばらく鑑賞した。
あの滝のどこかに黄金が眠っていて、と碧素が訳知り顔で言った。多くの若者がそれを取ろうとしたんだけど、みんな失敗したんだって。その若者たちは最後まで幸せだったんだろう。歩くのはどう? と少女が言う。私たちは車を降りる。
滝壺に落ちる細かい飛沫が、風にのって私の頬まで届く。滝から少し下流まで歩いた。小さな瀞がいくつも連なっていた。私と望月は、さっきまで光があたっていた岩に腰を下ろした。尻がじんわりと暖かくなった。
「中年、仕事、治水管理だろ? ここにも見回りに来るのか?」
「年に二回くらいですよ。ダムの近くのほうがずっと重要ですから」
碧素はごつごつした石の上を器用に歩いていた。魚がいたらもっと楽しかったのにね! と遠くから叫んだ。水は濁っていた。水盆の縁の方に泡が留まっている。
「そう簡単に見つかるわけないだろ」
「ミナイさんはやってみたことがあるんですか?」
「ない」
「やってないことを否定しないで!」
父親が隣で「育て方を間違えましたかね」と呟いた。さあ、と私は答えて、ノンアルコールの缶ビールを開けた。別の缶を望月に差し出した。
「あいつが育てたほうがよかったのかもしれない……東京で……」
そうささやいて、父親は言葉を切った。眼鏡をとって水滴を拭いた。森の奥で何かが飛び立っていった。木漏れ日が男の顔に複雑な模様を作った。
少女は一人ではしゃいでいた。川に立って「冷たい!」と当たり前のことを叫んだり、水をすくってはあてもなく太陽に向かって撒き散らしていた。緑のガラスの破片を集めては神に捧げる、文明が滅んだ後の世界にいる双子の巫師の妹のように見えた。
そうだね、と私は答えた。東京には美術館もあるし。しばらくして、何か慰めになるようなことを言わないといけなかったのだと気がついた。
水の入ったペットボトルを差し出した。足を洗ったほうがいいといった。碧素は砂を洗い落とした。彼女の首筋には汗が浮いていた。ちょっと疲れたから休む、と車に戻っていった。
私達は川沿いを歩いた。向こう岸までの吊橋が架かっていた。私達は仕事の話をした。それ以外に共通の話題がないように思えた――仕事の話が共通の話題だと仮定すればの話だが。
橋の中央で望月が歩を止める。風が吹いて、吊り橋がわずかに上下した。彼は川下の方を眺めた。来たときよりもずいぶん影が伸びていた。私は彼から少し距離をとった。木でできた橋板は黒っぽく朽ち始めていた。
「……いい川だと思いますか?」
彼は私の目を見て、すぐにそらした。真夏の風が吹いた。体が熱くなるのが分かった。蝉の声が変わり始めていた。
「覚えてるやつもいるんだな」
彼は手の甲で口元を隠した。
「あなたが探してるのは、この川についてのことですよね」
「部分的にそう」
私は彼に近づいた。手を伸ばせば殴れる位置まで来た。あんたのことはよく知ってるよ、と言った。あんたが四十にもなって薄給で働いてる理由も知ってる。あんたが昔、ここの近くのアルミ工場で働いてた事も知ってるし、その会社が産廃を十年間ずっとこの川に垂れ流してたのも知ってる。私達の下を水が流れていく。その川底を灰色の粘つく泥が覆っている。水草や水棲生物たちを押しつぶして。
「できる限りのことはした。賠償金も払った。八メートルの堤防ができた……」
私は彼の隣に立った。同じ欄干を掴んだ。ざらざらとした黒い泥が落ちていった。
「じゃあ水質調査報告書の正当性も認めるんだよな? あれはあんたの会社が東海大学に頼んでやらせたんだよな?」
「署名の検証が――」
「聞き飽きたよ。ご丁寧に耐量子暗号で署名して、秘密鍵を消して、しかも地方公共団体認証基盤から検証鍵を消し去って……書類が偽造されている可能性を持ち出したら、泥沼になるのは分かってただろ。あたしみたいなのが骨壷の中までついてくる」
彼がつま先で橋から小石をぱらぱらと落とした。それが水面に小さな波紋を広げる。やがて減衰して何も見えなくなる。鳶が空の遠くで鳴いた。
「なあ、この町にはもう六百二十七人しか住んでない。これ以上何をするべきなんだ? あの老人たちに浄水器でもやればいいのか? オール電化の新築住宅でも買うべきなのか? パナホームで?」
話を逸らすなよ、とつぶやいた。あたしは、あたしが死ぬまでにこの瀞が元通りになることはないって話をしてるんだ。
「ここは私の住んでいるところで、あなたの住んでいるところじゃない」
ここはあたしの生まれたところなんだよ。ここは私が母さんの腹から出てきて、最初に吸った空気が生まれた場所なんだ。確かに、あたしはここに住んでない。さっきの滝も初めて見た。正直、川に棲む生き物のことなんてあたしにはわかんない。切り身が泳いでる方がよほどメンタルモデルに合ってる。奈良田の言葉もしゃべれない。でもあたしの帰ってくる場所はここ以外にない。それがわかんないのか?
「……故郷も選ぶことができる」
「できるわけないだろ」
遠くでクラクションが鳴らされた。私は踵を返した。ここから落ちればあたしは死ぬだろうね、と告げた。あんたの考えが正しければ、あたしの死体を見つけるやつはきっと誰もいない。あんたはいつもの日々に戻れる。ダムの近くを歩いては修繕する場所を見つけてりゃいい。試してみてもあたしは怒ったりしないよ。してみろ。
彼は私を突き落としはしなかった。
どうしたの、と碧素が訊いた。なんでもない、と答えたつもりだったが、何の声も出なかった。そうすると、もうどうやってこの子に答えたらいいか分からなくなってしまう。
「ねえ、何かあった? お父さん、ミナイさん」
父親が車のモーターを入れて、来た道を引き返した。五時のサイレンが鳴った。オレンジ色の西日が車を焼いた。空の反対側から濡れた夜が広がり始めている。私は目を閉じた。太陽が我々を焦がし、月がそれを冷たい灰に冷やすところを思い浮かべた。そうはならないのは知っていた。ただ、叶わない望みはそれだけで価値があった。願い続けることができたから。
碧素が私の肩を触って、熱いものに触れたみたいにぱっと手を引っ込めた。
「帰ったらもう一回挑戦してみようよ、その……探しものが見つかるかもしれないし」
彼女は下唇を噛みながらパソコンを立ち上げた。ローブナーのスプラッシュスクリーンの後に、見慣れた画面が表示される。少女が泣きそうな声で言った。
「今日は本気でやります、全部うまくいくから……」
私は何も言わなかった。うまくいかないだろうと考えていた。この子がどうして欲しいかは理解することができたが――きっと、望月と笑顔で握手でもすればいいんだろう――私には単にそれができなかった。
彼女はいつもよりずっと荒っぽくキーボードを叩いた。子音をいくつか間違えた。会話はいつもどおりに進んでいった。何度も繰り返した失敗をまた再現していた。過去の会話のキメラ、円滑なだけのやりとり、どこにもいかない会話だった。
チャットボットが私達に尋ねた。あなたってもしかして幽霊ですか? 尤度が極端に大きくなった。あまりいい兆候ではなかった。違います、と苛立ったように碧素がタイプした。
『本当に? あなたはロボットでしょ』
「私はロボットじゃない、あなたがロボットなんでしょ」
『じゃあそのことを証明してくださいよ』
「それはそっちの仕事でしょ」
『自分の名前を言ってみろよ』
「私は――」
碧素、と彼女に呼びかけた。自分の声が思ったよりも荒かったことに驚いた。少女がはっと振り返った。彼女の目には涙が滲んでいる。
「クレバーボットに切り替わったのは分かるだろ。もうやめろ」
「嫌です」
「じゃあ好きにすれば」
彼女はキーボードを拳で叩いた。なんで、と叫んだ。私は咄嗟にマグカップを持ち上げた。水が入ってないことを確認して、彼女から少し遠くに置き直した。
「仲良くしてよ、なんでみんな、私のいないところで大切なことを……」
少女が顔を覆った。手のひらから涙が漏れた。彼女の肩に触れた。ひどく熱かった。私は「あんたは全く何も悪くない」と告げた。これはかなり正しかった。私は五分だけ待って、家を出た。来週の土曜日に母親と会わせてやると連絡を送った。
3
碧素は指定された時間ぴったりにやってきた。怯えたようにロイヤルホストのソファに腰掛けた。しばらくして、化粧の薄い女がやってきた。髪をセットした男が付き添っている。どちらも加齢に抗おうとしているように見えた。
現在地を共有しとくから、終わったら来てくれ、と言って席を立った。碧素が水のコップを遠ざけて、それからまた引き戻した。コップに本来の場所があって、その場所をなんとか探そうとしているみたいに。
一時間と少し経った。近くの公園のベンチで鳩を見ていたら、碧素が隣に座った。私達は何も言わなかった。体中が汗でべたついた。
「……なんか訊いてよ」
「泣いているやつには何も訊かないようにしてる」
「泣いてない」
「ならそれでいいよ」
近くをトラックが通って、ベンチが小さく揺れた。私は立ち上がって、少女の膝を軽く叩いた。帰りのバスに遅れるぞ。碧素が携帯端末を投げつけてきた。私は避けなかった。彼女は私の肩を掴んだ。指が食い込んだが、それほど痛くはなかった。
「なんでなんも言ってくんないの? どうだったとか訊いてくれてもいいじゃん? ミナイさんは私のことがどうでもいいの? 人生で他人がどんな気持ちか気になったりしたことないの!?」
「ない、一度もない」
碧素は怯えたような、怒ったような顔をした。あたしは人生で一度も他人の気持ちが気になったことがない、と告げた。映画を見ただけで泣く男もいる。人が泣いていても特に何も思わない女もいる。そういうものだ。望月からメールが一通来ていた。娘と一緒に帰ってきてくださいと述べていた。
「お父さんと仲良くしたほうがいいんでしょうね……」
と碧素がだいぶ落ち着いた声で呟いた。高速バスは自動運転になっている。車内にはまばらに人が乗っていた。毛羽立った古いシートには、煙草の臭いがこびりついていた。私は特に何も言わなかった。
でも、と続けた。お父さんは私に「何でもしていい」って言うんですよ、私がパソコンを買うときも、ローブナーにハマってるときも……何でもしていいよ、それで話は終わり。それがすごく卑怯に思えるんです……。
彼女は腕をがりがりと掻いた。
「大人になって東京に出てくればいい。あたしもそうだった」
サービスエリアに停まった。私達は缶のカルピスを半分ずつ飲んだ。さっきの話、と少女はゴミ箱の前で言った。
「本当にそう思ってますか? 高卒認定とって、統一テスト受けて……」
私はしばらく悩んだ。「本当には思ってない」と言った。少女が困ったような笑みを浮かべる。
バスの中で、「お父さんと何の話をしていたんですか」と少女が訊いた。あの川に汚泥を不法投棄している会社があったこと、その会社の調査室に少女の父親が勤めていたこと、そして、この不法投棄が最低限の復旧で手打ちになったことを告げた。
「白状すれば、この調査は単なるあたしの趣味だ。『サービス』にチクればあたしは無職になる」
バスの窓ガラスに頭をつけた。道路の振動が頭を揺する。
ずっと研究者でいられたら、こんなことをする必要もなかった。三十歳までに、格子暗号のフロンティアを切り開けたら、それは私に生きる理由を与えてくれただろう。それを持仏にどんどん進んでいけた。しかしそうではなかった。私は過去に見切りをつけて、コネで第三セクターに滑り込んだ。夜に浮かんでしまうのが怖くて、ダブルベッドのより細かいシーツを握りしめている。
私はたまに、むしょうに恋しくなる。過去を恨み、憎しみ、そして自分を徹底的に傷つけていた日々に戻りたくなる。それは痛みに満ちたものだったが、私には呪うべきものがあり、それを呪っていることができた。
バスが高速を降りて手動運転に切り替わった。もうすぐで着くべきところに着く。そうしたらまた次に行く場所を定めないといけない。
望月は駅まで車で迎えに来てくれた。夕立の後の匂いがした。お母さんに会った、と車に揺られながら、少女が呟いた。父親はカーラジオを切る。信号が黄色に変わる。頑張ればなんとかなりそうだったが、彼はブレーキを踏んだ。横断歩道を渡る人は誰もいない。
自動車がゆっくり発進した。ミナイさんから話を聞いた、と娘が告げた。
「お父さんはあんまりいい人じゃなかったんだよね」
家についた。父親は家の鍵を開けて、娘の方に向き直った。確かにそうかもしれない。そしてドアが開く。
ダイニングテーブルにパソコンが置いてあった。テンキーのついている、かなり古い機種だ。
「ちょっと座って下さい」
望月が言った。私は彼の目の前に座った。隣に碧素が座った。壁には白く灼けた写真が貼ってある。三人の親子の輪郭だけが、懐かしい夏の日差しのように残っていた。
「検証鍵について妻に話したことが何回かあります。それのどれがLOKAに残っているのか、私にはわかりませんが」
彼はいくつかのメールやメッセージアプリの履歴をしめした。あいつは私がクビになるか知りたがっていたんですよ。
「本当はあんたがこっそり隠し持ってるのに期待してたんだけどね」
碧素に「役に立つ?」と訊いた。彼女は私の顔を見て、父親の方に向き直った。そして泣き出した。顔を伏せて、しばらくすすり泣いていた。父親がティシューケースを取って、彼女の前に置いた。何回か鼻をかんだ。なんでこんなふうになっちゃったんだろうと、途切れ途切れに言った。
「なんで何もかもぜんぶ元通りになるって思ってたんだろ」
我々はしばらく黙っていた。泣き止んだ少女が私の肩口を掴んだ。お父さんは来ないで、恥ずかしいから。私は二階に連れて行かれた。
チャットボットが立っている。少女が髪を後ろで一つにまとめた。感情を抑えるように、「多分、データは手に入ると思う」と呟いた。
「ずっとそれにアクセスしてたから」
チャットが流れるように進んだ。突然、ボットが望月の名前を呼んだ。碧素はプロンプトに言葉を入れた。普通の愛の言葉のように見えた。チャットボットが妻の名前を呼び、そして娘の名前を呼んだ。その子の健康を祈ったり、週末にどこに連れて行くかを話したりした。望月の会話がまるごと残っている場所に私達は行き着いていた。
二年前、地元の話をしてたら、LOKAが突然お母さんの名前を呼んだ、と碧素は言った。すごくびっくりした。正しく答えれば、オリジナルの会話が復元できるのも分かった。お父さんたちがどういう話をしてるか知りたかった。必死で訓練した。馬鹿みたいに人と喋って、LOKAの癖を知った。お母さんたちは楽しそうだったし、幸せそうだった。なんで離婚なんてしたんだろうって思ってた。うまく話せば、いつかきっと、また元通りになると思ってた。一緒に住んでたときは、私も楽しかったから……。
彼女は目を拭って、細く長く息をついた。
「何を聞けばいいんだっけ」
私は手短に要件を伝えた。少女が文字を打つ。『レンダリング中』と表示される。チャットボットの頭の上に長大な文字列が流れる。私の端末にそれを取り込んで、検証機に流した。文書が次々に検証され、そのたびにターミナルに『よい署名』と表示された。
うまくいったよ、と伝えると、少女が名残惜しそうに頷いた。おそらく、この子はもうローブナーにアクセスしないんだろうと思った。この子は子供時代を振り返ることを覚えた。両親との思い出が実際はどういうものだったかを理解した。一度そうなれば、あどけない過去の領土に立ち入ることはもう許可されず、私たちはそれを遠くから懐かしく眺めることしかできない。
碧素は一階にいる父親に声をかけた。彼はドアの前まで来た。入ってきていいよ、と少女が言った。
望月が自動車で駅まで送ってくれた。静岡新聞に知り合いがいますよ、連絡先を教えましょうか、と別れ際に尋ねてきた。私は送ってくれと頼んだ。
特に意味は無いんだと思う、と呟いた。署名が検証できた程度で責任者が決まるわけではない。八十にもなる元町長をしょうづけても、川に魚が戻ってくるわけじゃない。あの川で鮎が取れようが、誰も気がつくことはない。父親は「そうでしょうね」と同意した。私たちはお互いにとってつけたような事を述べた。そして別れた。
電車がちょうど行ってしまって、私はプラットフォームで二時間近く待つことになった。虫の声が減っているのが分かる。空が高くなっている。雲の色が薄くなっている。枯れ葉を燃やすときの悲しい匂いが空気に混ざっている。次の電車が来なかったとしたら、私はどこに行けばいいのだろうか?
# 参考文献
– Nicholas Carlini, Florian Tramer, Eric Wallace, Matthew Jagielski, Ariel Herbert-Voss, Katherine Lee, Adam Roberts, Tom Brown, Dawn Song, Ulfar Erlingsson, Alina Oprea, and Colin Raffel, Extracting Training Data from Large Language Models, arXiv preprint arXiv:2012.07805, 202.