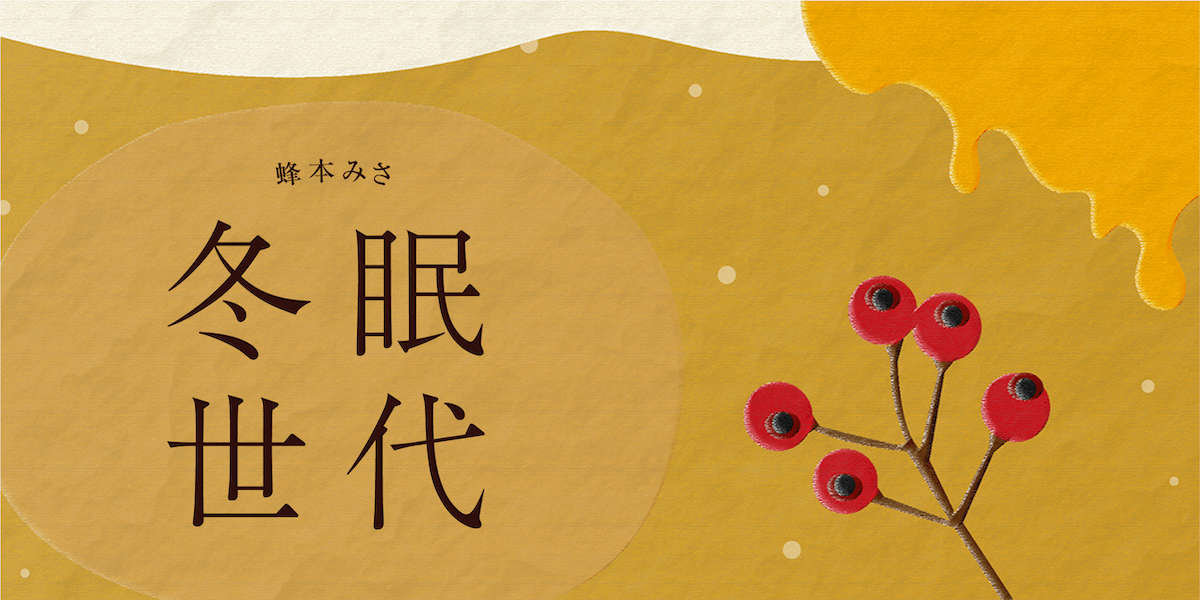先行公開日:2020.12.27 一般公開日:2021.1.30
蜂本みさ「冬眠世代」
7,363字
工場を誰よりも遅く出て誰よりも速く走る。スグリの赤毛は遠くからでもよく目立つし、工場から村まではほとんど一本道だから、そうやって一熊一熊追い抜いていけばぜったい会える。ちんたら歩く列の脇をすり抜けて枯れ草の上を急いでいると工場仲間が次々声をかけてくる。ツブテ、夢で会おうな。また春にな。寝すぎてなめし方忘れんなよ。冬眠組は今日で仕事じまいだった。おれだってちょっと名残おしいけど今はスグリだ。だって冬眠組の仲間とはいつでも会える。スグリには今日を逃したら来年の春まで会えない。
だんだん肺が苦しくなってきて、口からもれた白い息がふっ、ふっ、とうしろへ流れていく。夕方の空気はもうずいぶん冷たい。脂肪をたくわえた腹がひざをきしませてもかまってられない。遠くに赤い頭が見えた瞬間体の重さがぜんぶ吹っ飛ぶ。「スグリ」とおれは大声で呼ぶ。ふりかえった顔におどろきは見えない。うちの工場の最新作であるゆったりした鮭皮の上着と、縦縞のはいったイトウ皮のズボンを身につけていて、それが彼女のためにあつらえられたみたいに似合っている。いや、みたいじゃなくて、実際工場長は自分の娘に似合う服ばかり作っている節がある。
「走ってきた?」とスグリは笑う。おれは息が跳ねないように努めながら「久しぶりに、星の樹、見にいくんだけど」と言う。「ああそう、わたしも行こうかな」それでおれたちは横に並んで歩きだす。
腕をふると鮭がちゅうを舞って土に落ちて飛んで跳ねて押さえかじりもっと太らなくちゃもっと太らなくちゃ骨がくだけ腹がさけて白いしぶき川は流れ赤いたまごこぼれ冬がくる冬がくる冬が。
星の樹は地面が巨大な円形にえぐられてできた広場の真ん中に生えている。その光景は子どもの頃からちっとも変わらない。遠巻きにたたずんでいると秋の終わりの弱々しい風が吹いて、梢を揺らしたあとふたりの顔をくすぐっていく。あ、とスグリが上の方を差す。とがった葉の間に赤い粒が散っている。星の樹はこの季節にみずみずしい実をつけるのだ。昔こっそり樹にのぼってふたりで食べたほの甘い果汁の残像が口のなかに広がって、おれはたまらず樹に登ることにする。下の地面に飛びおりるとスグリが「汚いよ、やめなよ」と止める。「そんなわけないだろ、とっくにただの土になってるよ」
下の方にでっぱったこぶを足がかりにして、両腕でしっかり幹にしがみつく。信じられないほど体が重い。下手に動くと爪がはがれそうだ。なんとか横枝に尻を引きあげ、西日を受けてつやつや光る赤い実に手を伸ばす。つかんだ、と思った途端枝がみりみりといやな音を立て、あっという間に地面に叩きつけられる。
「ツブテ!」樹のまわりの土を汚いと言ったスグリが駆けよってきてくれて、ぶつけた鼻の奥をつんとさせながらおれはそれが嬉しい。どっさり実をつけた枝を小さな鼻先に突きつけると、スグリは一瞬きょとんとしたあと笑いだす。
「ありがとね」広場のふちに腰かけて実を食べながら彼女は言う。「いいんだ、どうせなるべく太らないとだし」おれはぷっと茶色い種を吐きだす。意味を察したスグリが大げさに目を見開く。また? って顔だ。
「うん。今年もだめだった。あと十四日したら冬眠する」「どうりでむくむくしてると思った」
工場で働く熊のうち冬眠するのは三分の一くらいだ。ほかの連中は頑丈であたたかい家に南部からくるばか高い食料をたっぷりたくわえて、冬の間も働くことができる。余裕のない貧乏熊は何万年も前と同じように、秋の間にせいぜい肥って冬眠するしかない。優秀な工員には手当が出るけどおれは枠から外れてばかりいる。山のような干鮭がもらえるんだ、と話していた年下の工員の得意顔を思い出すと今さらむらむら悔しい。
「結局さ、差がつく一方なんだよ。毎年冬眠組が寝てる間にみんなどんどんうまくなるんだからさ」
「わかる! わたしも今の制度は機会不均等を拡大させるだけだと思う。もっとずっと北の方に完全不冬眠制度を取り入れて生産効率を上げた黒曜石工房があるんだけど、兄さんはお前はうちの経営状況をわかってないって」
固い手ざわりの言葉が急に増えたので居心地が悪くなる。おれたちは同い年だけど、彼女は赤ん坊の頃以来まったく冬眠していないし、おれはもう十五回はやっている。たぶん五年か六年は遅れているはずだ。それでなくたってスグリは頭がいい。工場では兄のカズラと一緒に父親の補佐役をやっていて、兄に議論をふっかけたり、検査にきた目つきのするどい役人になにか冗談を言って笑わせたりしているのを遠くからときどき見かける。口いっぱいのねばねばした果汁がとつぜん子どもっぽい味に変わる。このままじいさんとばあさんになったらどれくらい差がつくんだろう。毎年五ヶ月ずつ冬眠するとして……と考え、計算が面倒くさくなってやめる。
「しばらく会えないけど、春祭りに一緒に蕗だんご食いにいこう」「いいよ」とスグリは言う。「でも、今年はわたしも冬眠するよ」おれはびっくりして種を飲みこんでしまう。種には毒があるのに。しかしおれはもう大人だし、小さな種ひとつだけだからきっとだいじょうぶだと思い直す。ゆとりのある上着でうまく隠しているが、言われてみればたしかに彼女の体つきはまるっこい。「ほんとに? じゃあ、夢で会える? スグリと」「うん。もぐり方がよくわからないけど」「赤ん坊の頃やっただろ」「ずっと前だしおぼえてない」スグリが珍しく弱気な顔をする。「おれ案内するよ、ていうか迎えにいく、慣れたら簡単だよ」
おれはこれまで見た夢のなかでもとっておきの夢について話してやる。ふつうは知り合いかせいぜい二、三代前までしか行けないけど、ごくまれにずっと深くまで降りていけるのだ。その夢のなかでおれは今の工場のあたりを四つん這いで走っていた。目の前の闇に逃げる子鹿の白い尻が浮かんでいた。夜空に白い切れ目ができたかと思うと丸く燃えあがり、地面がぐらぐらゆれた。ものすごい音がしてこわくなって子鹿と一緒に逃げた。逃げながら何かが焦げるような匂いをかいだ。
「ここに星が落ちた時の記憶だと思うんだ。星の焼ける匂いがしたんだ、すごいだろ。スグリもきっといい夢が見られる。ここで待ち合わせよう。春祭りの頃がいいな。でもなんで?」スグリはしばらく答えず、まるでおれの話から星の匂いがするみたいにフンフンと鼻を鳴らしている。「うーん、いい経験になると思って。父さんと兄さんが言ってた、わたしたち最後の冬眠世代かもしれないから、機会があるならしておくべきだって。これから科学がますます発展したら、熊は一生冬眠をしなくなる。そしたら夢にもぐる能力も失ってしまうから」最後の冬眠世代。ぜんぜんぴんと来ない。おれはたぶん来年も冬眠するし、再来年もきっとする。一生それをくり返すかもしれない。地下の冬眠室にもぐりこんで夢を見るのはけっこう好きだ。止まりそうで止まらない心臓の音に耳を傾けるのも。だけどスグリがどんどん遠くなる。ほかの幼なじみたちも、あとから生まれたガキさえおれを追い抜いていく。そういう寂しさをこらえてまであえて冬眠しようという趣向は、おれにはわからない。
「ごめん、無神経だったかも」スグリは実のなくなった枝をいじくりまわす。「ここで待ってる」
その夜今年はじめての大雪が降り、村じゅうがすっかり白くなる。
告示
村の長は秋分までに薪百把を城へ届けよ。熊の王は長き冬を眠らず、民と地とを見守りたもう。城に火を絶やしてはならぬ。王の慈悲にこたえよ。
冬眠がはじまる。はじめの二日ほどは現実と眠りの間を行ったり来たりしているが、だんだんと呼吸が遅く、脈拍が少なくなり、ある時眠りの底をつきやぶって夢に落ちていく。かがやく無数の金の糸が大きな意識の流れにいっせいにたなびき、ぷつぷつと小さな泡粒を吐きだしている。夏の川底に生える藻の群れにそっくりだ。
おれは彼女を探す。何日もなんの成果もない。仕方なく友人の糸をたぐって一緒に村を探索する。友人の祖母の記憶がもとになっているらしく、今の村よりずっと家が粗末で数も少ない。たいした娯楽もない。熊々は木の幹を殴って誰が一番深い爪跡を残せるか賭けをしていて、おれたちも参加して仲良く最下位になる。
一日の感覚がなくなった頃、ようやく彼女の糸を見つける。つかめば途切れてしまいそうなほど細く、しかしなめす前の鮭皮のようにきらめいているのでそれと気づく。春の約束だったのにスグリの夢の中は真冬で、吹雪がびゅうびゅう吹き荒れ、星の樹は真っ白に凍っている。きっと地面を伝って聞こえる本物の吹雪に気を取られすぎているのだ。雪のものすごい圧迫感とかじかむ指先から、彼女の経験が流れこんできていることがわかる。おれは冬を知らない。外の世界がこんなに厳しく寒くなるなんて知らない。スグリが凍えながら暮らした十何回の冬、おれはずっとあたたかく湿っぽい冬眠室で夢をむさぼっていた。もし起きていられたら、そばにいて手をにぎってやったのに。
スグリの耳をやさしくふさいでじっとしていると、雪は映画の早回しみたいに溶けてすっかり春になる。しっとりやわらかい草の上をおれたちははしゃいで駆けまわる。ほかにも熊がおおぜいいて、大きな布を巻きつけたような服の感じからずいぶん前の時代だとわかる。おれか彼女の先祖の記憶とつながったんだろう。向こうで何かがパンパンと鳴る。見ると村熊たちが穴のふちにずらり並んで星の樹の方へ尻を向け、真面目な顔でふんばっている。今度はポンという音がして、糞が勢いよく飛び出し穴の中へと落ちていくのがはっきり見える。これが年寄りの昔話に出てくる留め糞祭りかと納得する。夢で見るのははじめてだ。冬眠の間排泄を止めるために尻の穴近くで固く栓をしている留め糞を放ち、星の樹に捧げるとともに春の訪れを祝うのだ。おれたちはもてなされるまま昔ふうの蕗だんごやイラクサの和えものをたらふく食べ、陽気な音楽に合わせてでたらめに踊る。腹の中が草から出たガスでいっぱいになり、太鼓の音が腹にずんずん響いてもよおしてくると、ふたりで穴のふちへ行って熊々の列に尻を並べる。祭りは最高潮に達し、パンパンポパンプンパパンポンとひっきりなしの破裂音に包まれている。ふしぎと恥ずかしさはない。これは自然に感謝する儀式だ。おれとスグリは服の裾をまくりあげ、顔を見合わせてくすくす笑い、体内から祝砲が発射されるのをじっと待つ。
ステージにけばけばしい衣装をまとった熊が現れ、観客に笑顔をふりまく。熊は落ち着かない様子で何度も舞台袖に目をやり、手招きをするがだれも出てこない。しびれを切らした熊が滑稽な動きで地団駄を踏むとようやく三匹の猿が登場し、観客は大喜びで拍手する。
冬眠の実感が薄れないうちにここでわたし自身の所感も記しておきたい。昔の熊たちが冬眠中に見る夢を通って親しい相手や先祖の記憶に降りていったことはよく知られているが、身をもって体験する現代熊は今や非常に少ない。すごく妙な感覚である。いろいろなリスクや不便を承知で旧式の冬眠出産をやりとげただけでも、民俗学研究者としては大きな収穫だった。秋口に襲ってくるあのすさまじい食欲に大義名分ができるし、息子と冬眠室で過ごした数ヶ月間も悪くなかった。父の初恋に心臓を乱されるのは、少々、かなりむずがゆいが。それにうちがそんなに貧乏だったなんて知らなかった。父は結婚が遅く、子を持つのも遅く、わたしが成熊する前に亡くなった。
父がスグリという娘と見た夢、あれは貴重な手がかりになりそうだ。断片的ではあるが古代熊の記憶と思しき夢もあった。正当な資料として認められないとはいえ、研究のヒントとして活用しても文句は出まい。忘れないうちにすべて書きつけておかなくては。
息子のハルは今、頭からスカーフをすっぽりかぶり、木でできたおもちゃの養蜂セットで遊んでいるところ。ぶーん、ぶううううん、と蜜蜂の羽音を真似ている。ハルは本物の蜜蜂を見たことがない。この地域は寒すぎて養蜂に不向きだ。それなのに蜜蜂が大好きなのは、わたしと一緒に夢にもぐったからだった。きっとだれか南部に暮らした先祖の記憶だろう。ざわめく蜜蜂たち、それらの巻き起こす風、時間がひきのばされたみたいにたらたらと流れる黄金の蜂蜜、その甘い香りをわたしたちは夢見た。通信販売で養蜂セットを買ってやると、思ったとおりハルは夢中になった。来週にはふんぱつして買った百花蜜が届く。数え切れないほどたくさんの種類の花からとれた蜂蜜。いったいどんな味わいだろう。そうだ、それもこれもみんな書いておかねばならない。哺育器の技術がまた一歩前進したと先日の新聞記事にあった。この子が大きくなる頃には冬眠出産すら過去の遺物となり、夢で記憶を伝えるなど夢のまた夢になるだろうから。
あの留め糞祭りの夢以来、スグリとちっともつながれない。記憶の糸の出し方を忘れてしまったのかと思っておれから待ってみても、いつもの冬眠組が遊びにくるばかりだ。おれたちは鮭獲り競争をやり、何晩もぶっつづけでカード遊びをし、隻眼の熊と決闘して崖から転げ落ち、美しい笛の三重奏に涙を流す。ある日意識の流れにもぐろうとしてどうしても尻が浮いてしまい、春が近いことを悟る。ふつうの睡眠で見るような現実味のないつまらない夢を見ることが多くなり、うっすら目覚めている退屈な時間が長くなる。
冬眠室を出てまぶしい光のなかに分け入っていく。まだよろよろとしか歩けない。少しずつ意識がはっきりして、まわりがよく見えてくる。同じようにふらつきながら歩いている熊があちこちにいる。よくできたもので、冬眠組が目ざめる日には二日と差がない。おれは自分が星の樹へ向かっていることに気づく。あたりがだんだんにぎやかになる。星の樹のまわりにたくさんの屋台がたち、楽団の演奏に合わせてみんなが足を踏み鳴らす。春祭りの日だ。ちょうど間に合ってよかった。スグリはふたりで実を食べた日みたいに穴のふちに腰かけている。「おい、あの枝折れてるじゃねえか、村の大事な樹だぞ、だれだ折ったやつは」と酔っぱらったじいさんがくだを巻いているのが聞こえる。赤毛の頭がふっとこっちを向く。「ツブテ、痩せたねえ」「そっちこそ」いつも痩せた痩せたと言われるばかりだから、そっちこそって言えるのが新しい感じがする。スグリはなんだか小さくなって、首なんか鹿のように細いけれど、着ている薄手のシャツの花びらみたいな鱗模様が美しい。「あれきり会えないからどうしてるかと思った」「ふふ、へんなお祭りだった」夢とはいえ、隣で脱糞したのが恥ずかしくておれは顔が上げられない。スグリは意外とけろっとしている。と、スグリの陰からころころ太った赤ん坊がおぼつかない足取りで走りでてきて、自分の手をまるごと口に含みながらおれの顔を見てにこっと笑う。いやに切れ長の目だ。スグリは赤ん坊を抱きあげて「こっちにいようね」と脚の間にすっぽり抱える。「わたしの息子。名前はまだ」おれはなんて言ったらいいかわからなくなって、たっぷり間をつくったあとでやっと「すげえ」とつぶやく。スグリは赤ん坊の父親とどうやって出会ったかということや、しばらく仕事を休むこと、でも家族の協力ですぐに復帰できることなどを話すが、楽団の太鼓と目ざめたばかりの心臓がうるさくて話のところどころが聞こえない。
棒付き飴だよ、棒付き飴だよ、味はいろいろ、桑味、蕗味、ざりがに味、芹味、蟻味、イチイ味、ナナカマド味は季節限定、おみやげにぜひどうぞ。
秋がくる。おれは工場の帰りにスグリを誘ってまた星の樹へ行く。フブキも一緒だ。フブキはおれを見つけるとケタケタ笑いながらいちもくさんに走ってきて、かがんだおれの首にぎゅっとしがみつく。「大好きなツブテとお散歩うれしいね」とスグリはほほえむ。今日は今季いち押しの鱒皮ワンピースだ。フブキが離れてくれないのでそのまま抱きあげる。おれのなにがそんなにいいのだかわからない。フブキは楓の落ち葉に似た赤毛だ。はじめてスグリに会った時も同じように思ったことを思い出す。
スグリが工場に忘れものをしたので、フブキとふたりで先に星の樹へ向かう。おれはまた手当をもらえなかった。それで去年やったみたいに赤い実のついた枝を折り取って、スグリが来るまでの間実をかじって過ごす。フブキがおれと赤い実を何度も見比べる。少し吊りぎみの目は、父親の役人似だ。「食べるか? うまいぞ」枝を差し出すとフブキは小さな手で懸命に実をもぎとり、口に持っていこうとする。そこでわれに返り、すんでのところではたき落とす。フブキは驚いて甲高い声で泣きわめく。ぽろぽろぽろとまんまるい涙の粒があとからあとからこぼれる。「わるかった、わるかったよ、子どもには毒なんだ、あとで焼き栗買ってやるから」抱きしめるとおれの上着はフブキの涙でぐっしょり濡れて、そこにやわらかい秋の風がしみてくる。
ぼくはノートを閉じ、しっとりとした鹿革の表紙を撫でた。母の遺した研究ノートはぜんぶで三十六冊。どのページにも各地の冬眠文化に関するメモや、希少な冬眠経験を持つ熊へのインタビュー内容がびっしり書きこまれている。記念すべきこの一冊目は母自身が冬眠出産でぼくを産んだ頃の記録だ。代表的な著作である『ナダレの冬眠回想録』のもとにもなった。そこそこ売れたし、冬眠経験者はもうほとんどいないから、愛読者に出くわすとよく質問ぜめにされる。母が冬眠で見た夢を幼いぼくもまた見たはずだ、というのだ。今日もアルバイトに雇ったばかりの新熊にきらきらした目で尋ねられて、何か思い出せないかと久々にノートを開いてみたけれどやっぱりだめだった。すべては母の創作だと断じる読者もいる。夢を見た記憶を持たない以上、反論はできない。だけど熊生のそこかしこに夢の影を見つけることならある。たとえばぼくは今、めぐりめぐってどういうわけだか南部で養蜂場をやっている。それから、ノートをぱらぱらめくってページのつくる風に顔の毛を撫でられていると、食べたこともないねばねばした赤い実のうす甘さが舌にうかぶ。