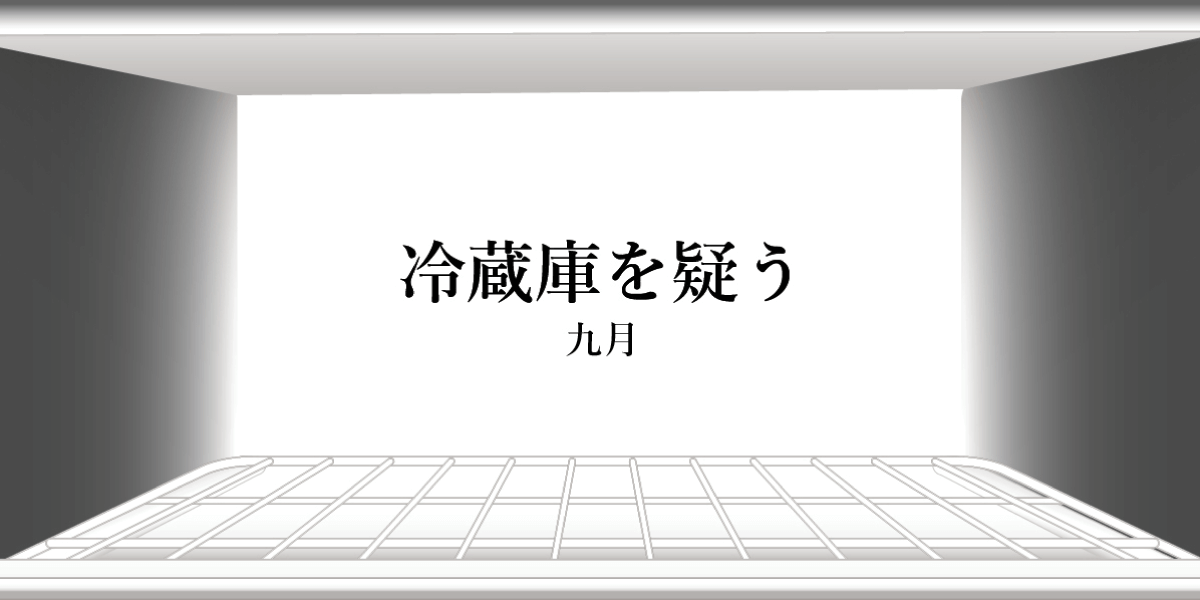先行公開日:2022.8.26 一般公開日:2022.10.1
九月「冷蔵庫を疑う」
10,760字
冷蔵庫を疑わない人生などあるのだろうか。
考えれば考えるほどに、冷蔵庫は珍奇だ。人間が発明し、生活で用いる多くの道具は、身体の延長と言われる。例えば掃除機や洗濯機は、人間が手で行う行為を、最大効率で代演するための道具だ。眼鏡や顕微鏡は目の機能を強化するものだし、フルートやトランペットは良い音の鳴る喉と言えよう。人間を囲む道具とは、身体を延長・拡張したものなのだ。
しかし、冷蔵庫はそれらと性質を異にする。人間はどんなに頑張っても、体のどこを使っても、物を冷やすことができないのだ。人間の身体は、何かを冷やす機能を持っていないのだ。それなのに、冷蔵庫は中にある物体を冷やすことができる。冷蔵庫は人間の出来ないことをやり遂げているのだ。人間が生み出した道具でありながら、冷蔵庫は人間の身体を離れている。これはいかにも珍奇だといえよう。
そんな珍奇な機能を持っているにも関わらず、冷蔵庫の仕掛けはあまりにも単純だ。電源を与えてやると、内部が冷える。ただそれだけだ。スイッチを入れるとか、ボタンを押すとか、ペダルを踏むとか、そういった煩雑な手順や機序をまるで持たない。目に見える動きもないし、聞こえる音だってほとんどない。冷蔵庫の中で何が起こっているのかは、常にあの扉によって隠匿されている。ゆえに、冷蔵庫は一つの大きな問題を持つ。すなわち、人間は目の前にある冷蔵庫が「内部を冷やす」という機能を全うしているかどうかを、扉を開けないことには確かめられないのだ。
冷蔵庫が故障したとき、外側から感知できる情報はない。ガスコンロのように火の付かなさを視認することもできないし、パソコンのようにエラーメッセージを表示してくれることもない。人間はいざ、冷蔵庫の中にある食物を取り出してはじめて発見する。中が室温と全く同じ温かさだ、どうやらこれは故障していたらしいと。
そのとき、目の前にあったのは果たして「冷蔵庫」だろうか。否、そんなはずがない。冷蔵庫とは内部を冷やす家電である。冷蔵の機能を一切失ったとき、それはもはや、「こいつ」としか呼びようのない大きな箱だ。そして「こいつ」を目にしたとき、人間ははじめて冷蔵庫の珍奇さを痛感する。中が冷えているのは、当たり前ではなかったのだ。
裏を返せば、目の前に「冷蔵庫らしきもの」があるとき、それが中身まで冷えた「冷蔵庫」であるのか、中身は常温の「こいつ」であるのか、扉を開くまでは判断ができないことになる。世の中にはあらかじめ確定した「冷蔵庫」など、存在しえない。世界には「冷蔵庫らしきもの」があるだけだ。扉を開いて、中身が冷えていることを確かめて、はじめてそれが「冷蔵庫」だとわかるのだ。
僕がこうした考察に辿り着いたのは中学生の時だった。
真夏の夜、苦しさに目覚めた僕は、お茶でも飲もうと台所へ向かった。ふと冷蔵庫を眺めたところ、一瞬のうちに上述の考察を終えたのだった。それはある種の神秘的な体験だった。全身の筋肉が熱を帯びて震えた。昨日まで「冷蔵庫」にしか見えていなかったそれが、途端に不気味な、全くの謎として立ち現れた。
僕は「それ」の扉に手をかけた。息が荒くなる。顎から零れる汗は熱帯夜のせいではない。膝が震える。今、自分は神秘に手を伸ばしている。そして、目の前の「それ」を疑った。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
「それ」は冷蔵庫だった。僕は全身の血が平熱に戻っていくのを感じた。安堵した。同時にどこかがっかりするものがあった。冷蔵庫らしきものが、冷蔵庫だった。そのごく当たり前の事実は、どこか無味乾燥としていて空っぽな、正しいというだけでそれ以上に何の意味ももたらさないものに思えた。
とはいえ、翌日も、翌々日も、そのまた次の日も、僕は親の目を盗んで冷蔵庫を疑った。先日冷蔵庫だったものが、今日もまた冷蔵庫だとは限らないからだ。しかし、僕の疑いに成果がもたらされることはなかった。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
事が動いたのは週末だった。両親が買い物に出かけ、好きなだけ冷蔵庫を疑う時間ができた。日中に疑うのは初めてだった。週末の高揚感に任せ、僕は何度も何度も何度も連続で冷蔵庫を疑った。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
ダン。
ダン。
ダン。
ダン。
ダン。
ダン。
二時間後のことだった。冷蔵庫が壊れた。
あの忌々しい冷気がとうとういなくなったのだ。だんだんに温くなる箱。もはや目の前にあるそれは冷蔵庫ではない、「こいつ」としか呼びようのないただの箱だった。体にあの神秘的な興奮が蘇るのを感じた。僕は大いなる学びを得た。冷蔵庫は、疑い続けると冷蔵庫ではなくなるのだ。
買い物帰りの両親が、もはや「こいつ」となってしまったただの箱に手をかけるのを半笑いで眺めた。二人が買ってきた生鮮食品にもはや居場所はない。母は天を仰ぎ、膨らんだレジ袋をそのままごみ袋の中に放り込んだ。父は時計に目をやり、今から電気屋に行くと言った。
新しい冷蔵庫が到着したのは二日後のことだった。先日のものよりも大きく、最新式のものだった。両親は、いつかは買い替えるものだったからとか、この機能があるからよいだとか、ヨーグルトでも作ってみようかだとか、冷蔵庫を冷蔵庫としてしか見なさない者特有のくだらない会話を繰り広げていた。
その日の夜、当然ながら僕は冷蔵庫を疑った。両親の目を盗み、ありったけの疑念をこめて、新参者のそいつを疑う。少し背が伸びたくらいで、銀色の光を放つくらいで、小さな音を立てて唸るくらいで、「冷蔵庫らしきもの」が当たり前に冷蔵庫として佇んでいる。その正体を暴かなければいけないと思った。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だった。
ダン。
中はきっちり冷えていた。買い直したであろう牛乳や卵が澄ました顔で並んでいた。僕はがっかりして扉を閉めた。きっちり機能していた「冷蔵庫」を見つめる。しかし、同時に思う。もう一度、疑ったならばどうなる? 疑う。開ける。冷えてる。冷蔵庫だ。ダン。冷蔵庫か。しかし、もう一度、疑ったならば? 疑う。開ける。冷えてる。冷蔵庫だ。ダン。疑う。開ける。冷えてる。冷蔵庫だ。ダン。疑う。開ける。冷えてる。冷蔵庫だ。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダンダンダダンダンダダンダンダン、ダンダンダダンダンダダンダンダン。ダンダンダンダダンダダンダンダダン、ダンダダンダダンダンダンダンダン。
一晩経たないうちに、冷蔵庫が壊れた。
僕は言いようのない幸福感に震え、とてもいい気分だったが、それは長くは続かなかった。
朝、目を覚ました父は、ぬるい牛乳を手にするなり大きな溜め息をついた。次いで目覚めた母は、うなだれるなり「簡単な朝食を買いに行く」と言い、近所のコンビニへ向かった。その間、父は家電量販店へ電話をかけていた。窓口が開くにはまだ朝が早かったのか、あるいは電話が混雑していたのか、父は舌打ちをしながらあれこれと何度も電話をかけ直していた。
帰ってきた母が、「こいつ」に手をかけるなり、しまった、冷凍食品は駄目だった、とこぼした。父が母を笑った。母はむっとした顔をして父を問い詰めた。父は「繋がらないのは自分のせいじゃない」という旨のことを早口で言った。それからしばらく、二人の会話はなくなった。母が「昨日の夜、工事してなかった?」と問いかけても、父はまるで返事をしなかった。
一連の光景は、冷蔵庫を疑わない決心をするには十分だった。冷蔵庫を疑うことは、家族に迷惑だったのだ。
それから僕は、冷蔵庫への疑いを、なるべく秘めて生活をするようになった。もちろん、冷蔵庫を全く疑わなかったわけではない。自分の家では疑わないこと、回数に制限をかけること、この二つをルールとして設けた。友達の家に行ったときには、二、三の疑いを付した。公民館でも少しばかり疑った。コンビニやスーパーでは、飲み物を選び損ねている人のふりをして、五回、六回、七回と繰り返し疑った。
しかしいずれも成果を得るには至らず、「冷蔵庫らしきもの」は常に、当たり前のように冷蔵庫だった。そんなつまらない日々の中にあっても、僕はあの歴史的高揚感を忘れることはなかった。冷蔵庫を疑い続け、とうとう冷蔵庫ではないものとするあの快楽は、僕の記憶の根底で深く強く息づいていた。
あの快楽へと焦がれていながら、ついに満たされないまま、僕の身長はぐんぐんと伸び、その後でだんだんに伸びが止まっていった。その間、親や教師から「やりたいことはないの?」と何度も聞かれた。そのたびに僕は言葉を濁した。「心行くまで冷蔵庫を疑いたい」と言うわけにはいかなかった。冷蔵庫が冷蔵庫に見えている彼らに、僕の抱えている疑いが理解されるとは思えなかった。
しかし、冷蔵庫を疑う行為が持つ引力を、僕が無視できるわけもなかった。何になりたいわけでもなかった。ただ僕は、冷蔵庫を疑うために必要な、時間と空間と孤独を手に入れたかった。高校を卒業したのち、僕は「役者になる」と適当な理由を付けて実家を飛び出した。一人暮らしを始めたかった。理由なら何でもよかった。
そして夢のような日々が始まった。東京の端、六畳一間でのアパート暮らし。
最初の一週間を、僕は「冷蔵庫らしきもの」の開閉のみに費やした。当然、役者になる気などさらさらなかった。やっと手に入れた暮らし、やっと手に入れた、心行くまで疑える「冷蔵庫らしきもの」なのだから、気が済むまで疑うほかなかった。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
開ける。
冷えてる。
冷蔵庫だ。
ダン。
昼夜を問わぬ僕の疑いに、その小さな冷蔵庫は耐え続けた。
ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。
なかなかしぶとく、根気があり、どれだけ疑われようとも冷蔵庫であろうとする姿には、ある種の矜持すら感じた。
ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。
とはいえ、疑われ続けることに耐えられる冷蔵庫など存在しない。
ダンダンダダンダンダダンダンダン、ダンダンダダンダンダダンダンダン。ダンダンダンダダンダダンダンダダン、ダンダダンダダンダンダンダンダン。ダンダンダダンダンダダンダンダン、ダンダンダダンダンダダンダンダン。ダンダンダンダダンダダンダンダダン、ダンダダンダダンダンダンダンダン。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン。
一週間が経ったとき、冷蔵庫は「こいつ」となった。僕は全身にあの濁流のような興奮と高揚感を感じた。ずっと求めていたのはこの感覚だったのだ。
僕はさらなる快楽が欲しくなった。もっと「冷蔵庫らしきもの」が要る。慌ててバイトに精を出した。働いては大小さまざまな「冷蔵庫らしきもの」を買い、疑っては「冷蔵庫」を「こいつ」にした。
瞬く間に半年が経ち、気付いた頃にはワンルームの一角は「こいつ」の山となっていた。どんな「冷蔵庫」も、しつこく疑っていれば「こいつ」になる。役にも立たず、機能もなく、ただ場所を取るだけの「こいつ」にはどこか可愛げがあった。部屋に「こいつ」が増えていくことが、僕には嬉しく感じられた。
そんな僕の暮らしについて、両親は演技の勉強をしているだとか、役者になるレッスンを受けているだとか、見当はずれな想像をしているようだった。その素朴さ、ナイーブさがとても愚かに思えた。僕は役者の勉強などは一つもせず、ただ欲望のままに冷蔵庫を疑い続けていたのだから。
ある夜、大変なことが起こった。山のように積み重なった「こいつ」のうち一つが、「冷蔵庫」に戻っていたのだ。冷蔵の機能などないはずの「こいつ」の中が、あろうことか外気よりも遥かに冷えているのだ。
裏切られたような怒りと失望が湧き起こった。感情に任せて、僕は「冷蔵庫」がもう一度「こいつ」に戻るまで開閉を繰り返した。
ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。
怒りのまま、言葉にもならぬ言葉を叫びながら、涙を流しながら、何度も何度も開閉した。
ダンダンダダンダンダダンダンダン、ダンダンダダンダンダダンダンダン。ダンダンダンダダンダダンダンダダン、ダンダダンダダンダンダンダンダン。ダンダンダンダン。ダンダンダンダン。
それでも「冷蔵庫」が「こいつ」に戻ることはなく、しだいに夜が明けていった。
ダンダンダンダン。ダンダンダンダン。ダンダダンダンダダンダンダンダンダダンダダダダダダン。ダンダダダンダダダンダダダダダダダンダダダンダダダンダダダダダダ。ダンダンダダンダンダダンダンダン、ダンダンダダンダンダダンダンダン。ダンダンダンダダンダダンダンダダン、ダンダダンダダンダンダンダンダン。
朝八時ごろ、隣人に「ドラムの練習はやめてください」と苦情を言われた。正直に事情を言うこともできず、僕は「ごめんなさい、ライブが近いのです、スタジオで練習します」などと適当な嘘をついた。
すると隣人は「やっぱりそうだと思いました。ああ、いや、そこまで怒っているわけではないんです。実は僕、ドラム講師をしていて。夜中じゅうずっと隣の部屋からいい感じのビートが聞こえてくるので、ちょっともう踊り出したくなって、寝るどころじゃなかったんですよ。あのビートの感じだと、踊れる感じのパンクロックとか、メロコアとかなのかな。ライブ、頑張ってくださいね」などと頓珍漢なことをつらつらと並べた。よくもまあそんなにも真実から遠いことを述べられるものだと思った。
九時ごろ、隣人が外出する音を確認したのち、僕は続きを始めた。開閉の音が再び鳴り響き、僕はやはり泣き叫んだ。スタジオになど行くわけがない。ライブなどするわけがない。メロコアなんて知らない。誰にも見せられるわけがない。僕はやはり泣きながら、何度も「冷蔵庫」を開閉した。
ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。ダン。
夕方になろうかという頃、開閉が報われ「冷蔵庫」はもう一度「こいつ」になった。僕はとても嬉しく、泣きながら笑った。
その晩、久しぶりに母から電話が来た。「最近どうしているの?」と柔らかい声がする。僕は勢いで「舞台の仕事が決まった」と言ってしまった。嬉しそうな母親の声に、少し暗い気持ちになった。一週間ほど間を空けてから、母親に「やっぱり監督と合わなくて」と伝えた。真剣に落ち込み、励ましてくれる母親の声を聞き、さらに暗い気持ちになった。自分があまりにも惨めな存在に思えた。親に嘘をつき、冷蔵庫への疑いに生活の全てを費やしているなど、言えるわけもない。
ふと部屋を見渡すと、役立たずの「こいつ」が、優しく慰めてくれるようにただそこに在った。冷蔵庫の形をしながら一切の機能を持たない「こいつ」は、僕の嘘にまみれた生活に丸ごと付き合ってくれているようだった。
僕はバイトをさらに増やし、寝る間を惜しんで働き、寝る間を惜しんで冷蔵庫を疑った。「冷蔵庫」が「こいつ」になる瞬間の喜びは何物にも代えがたい。「こいつ」はとうとう十八台になった。僕は部屋に入り切らなくなった「こいつ」をベランダやユニットバスに移動させた。
ある日、近所のリサイクルショップを通りかかったとき、興味深いものを見つけた。そこに並んでいたのは、見るからにとても古い「冷蔵庫らしきもの」だった。「使用25年、動作△」とある。一体、誰がどんな目的で購入するものなのだろう。いかにも中を冷やすことが出来なさそうなルックスをしている。もはや疑われるためだけに存在しているようにさえ思える。いずれにせよ、僕にはたまらなく魅力的に見えた。そんなにも古いものを疑えるなんて、そうそうない機会である。僕は迷うことなく、その「冷蔵庫らしきもの」を買った。
ワンルームの真ん中に置き、改めて対峙する。電源を入れると、ブウン、と低い音が鳴る。部屋に並ぶ「こいつ」たちと比較したとき、どう考えても明らかに古い。すると「こいつ」である可能性がある程度高いことになる。しかしブウン、と鳴る音から察すると、何らかの働きが行われていることは間違いない。冷えているのだろうか?
「冷蔵庫」なのか、「こいつ」なのか。はたまた僕も知らない三つ目の姿なのか。どのみち寿命が近いことは明白であり、数度の疑いの後には「こいつ」として存在することは予想された。問題は、今、このときにどうなのか、である。
高鳴る期待に、両手が細かく震える。決定的な疑いを、僕はまさに実行する。扉に手をかける。中には冷たい冬が生きているのか。それを僕が殺してしまうのか。もともと冬は死んでいて、死に続けるのみなのか。そして僕の手が、冷蔵庫を疑った。扉が音を立てて開く。次の瞬間、常温の風が頬をかすめた。
ダン。
「こいつ」だった。
「こいつ」は、それまでも「こいつ」で、これからも「こいつ」だった。ただの「こいつ」だった。冷蔵庫でもなければ、第三の選択肢でもなかった。これはすなわち、単なる「こいつ」でしかなかった。そのことに僕は苛立った。もし「冷蔵庫」だったならば、疑うことで「こいつ」へと変貌する瞬間に立ち会うこともできた。もし「冷蔵庫」でも「こいつ」でもない第三の在り方だったならば、それがどんなものかたんと検証したうえで、疑いに疑いを重ねて「こいつ」へと変えるまでだった。
しかし自分の目の前にあるのは、単なる「こいつ」以外のなにものでもなかった。これは「こいつ」でしかない。〇でも△でもない、まったくの×だった。くだらない。あまりにもくだらない。こんな古びた「冷蔵庫らしきもの」がはじめから「こいつ」であることに、いったいどんな意味があるのかが分からなかった。一通り悪態をついていたら、急にはっと目覚めるような感覚があった。そのとき初めて、自分が内心では「冷蔵庫」であることを望んでいたのだと気付いた。自分は冷蔵庫を疑いながらも、それが冷蔵庫であることを期待していたのだ。
瞬間、悟った。冷蔵庫を疑うという行為も、それを続けている僕も、どうしようもなくしみったれた存在だった。僕はただ生活から逃げ、嘘から逃げ、家族から逃げ、関わりから逃げ、真実から逃げ、人生から逃げ、仕事から逃げ、決定から逃げ、運命から逃げ、選択から逃げ、自分自身から逃げ、ただ冷蔵庫を開閉し、「こいつ」という、唯一自分が蔑まれようのない存在に共感と優越と安堵を見出そうとしていただけだった。僕の冷蔵庫への疑いは、もはや 生き延びるためだけの、あるいはあらゆる重みを伴って生きずに済むためだけの、何ともしみったれた自家発電的行為へと成り下がっていた。僕という存在は冷蔵庫を疑うという、あまりにも無意味な行為を通じ、あまりにも無意味な「こいつ」を生成し、それを通じて安心し続けることを手段かつ目的とした、まるごとあまりにも無意味な存在だった。
思えば中学生の頃には、もっと純粋に冷蔵庫を疑っていた気がする。いつからか、僕は「冷蔵庫」が「こいつ」に変わる瞬間の快楽に、あるいは取り憑かれ、あるいは逃避していた。つまり、僕が一番疑うべきは冷蔵庫ではなく、僕自身だったのだ。
僕はどうなってしまったのだろう。僕がいかに僕であるかを疑わねばならない。確かめねばならない。それにはどんな方法があるだろう。鏡を見ればよいのか、減った石鹸を見ればよいのか、生活によって出たごみを調べればよいのか。今すぐに自分を発見せねばならない。あるいはもはや発見できないことを確認せねばならない。
どうしたものかと見渡した部屋には、たくさんの「こいつ」だけがあった。冷蔵庫よりもずっと冷たい死が、部屋中に散乱していた。扉が開いたままのもの、閉じたもの、電気ケーブルが繋がったもの、繋がっていないもの、白いもの、銀色のもの、黒いもの、赤いもの、様々な「こいつ」が散らばっていた。それらはむせ返るほどに強烈な死と無意味の匂いを放っていた。
形状のみを見たとき、それらは「冷蔵庫らしきもの」と呼びえたかもしれない。しかし、それらが全て「こいつ」であることは疑うまでもなく明白だった。漂う死の匂いが、あらゆる疑いを受け付けないほどに確かだった。
そこでふと気が付いた。そもそも僕は冷蔵庫について「冷やす」ことを目的に用いたことがなかった。道具にとって、その目的に準じて使役されえないということは重大な問題である。内部を冷やすことを目的に生み出された冷蔵庫を、一切何を冷やすでもない目的のために、すなわち「疑う」などという純粋にして空虚、有名無実な目的のために消費しているとき、冷蔵庫は冷えている・冷えていないにかかわらず、あらかじめ死んでいたのだ。僕は冷蔵庫に食料品や飲料品を入れたことがなかった。一度たりともなかった。僕はこれらの「冷蔵庫らしきもの」たちを、ただ疑うためだけに集め、ただ疑うことで消費してきたのだった。
僕はしばらくただ呆然としていた。そこに漂うあらゆる死の気配が、空気を伝って肺に入ってきた。それを吐き出した。また吸った。また吐き出した。自分がだんだんにその死の気配と通じていくのを感じた。現実の全てが曖昧に遠ざかっていくような感覚になった。もはや、自分がなぜこのような暮らしをしてきたのか分からなくなった。自分自身を疑う。僕は僕を疑う。この光景のすべてを疑う。疑えば疑うほど全てが遠のいていき、僕は暗い所へと落ちていった。
三ヶ月が経った。部屋が広くなり、バイトをかなり減らした。
僕は演技の勉強を本格的に始めていた。冷蔵庫への疑いを忘れ、確かな人間になりたかった。劇団の練習会に参加するようになり、演劇人の知人が増えた。少しずつ自分が確かな存在へと生まれ変わっていくのを感じた。
演劇に興味があったわけではなかった。数年前に家を出る際、方便として、思いつきで「役者」と口にしただけだった。しかし、案外僕の役者としての筋は悪くないようで、顔つきや発声を褒められることも多く、早々に仕事を紹介してもらえることになった。
顔合わせに集合したスタジオは、とても綺麗だった。一面にさまざまな小道具・大道具が置いてある。机と椅子、大きなタンス、ホワイトボード、懐中電灯、ギター、おもちゃの銃、西部劇に出てきそうなカウボーイのテンガロンハット、時代劇に使うであろう旗のようなものなど、沢山の道具があった。その並びに、冷蔵庫が置いてあるのを見つけてしまった。
僕は自分に言い聞かせる。見てはいけない。疑ってはいけない。もう冷蔵庫を開閉してはならない。冷蔵庫へと足を運んではならない。冷蔵庫へと意識を向かわせてはならない。あれは冷蔵庫だ。ただの冷蔵庫だ。あれはただの冷蔵庫だ。僕はもう、人間になったのだ。「こいつ」ではない。冷蔵庫を疑う必要などない。
スタジオに劇団の主催者がやってきた。髪型は耳にかかるくらいのショートボブ、服装は上下黒のタイトスーツ、いかにも「出来る人」然とした確かな足取りだ。界隈では著名な、気鋭の演出家らしい。ゆっくりと口を開く。
「今日はよろしくお願いします。今回の話は即興劇をベースにしたいと思っています。皆、この場にある人や物と関わりながら、自由にやりたいことをやってみてください」
その瞬間、タガが外れた。僕は全速力で冷蔵庫に駆け寄った。
「うおおおおおお!」
その場にいる全員の目が僕を追いかける。生まれ変わった僕は心おきなく、「冷蔵庫らしきもの」を疑う。
ダン。
ダン。
ダン。
開閉の音がスタジオに反響する。
ダンダンダダン、ダンダンダダン、と鳴る。
何度も開閉する。そのたび音が鳴る。
ダンダンダンダン、ダンダンダンダン、ダンダダンダンダダンダンダンダンダダンダダダダダダン、と鳴る。
僕は開けることの心地よさに気を失いそうになり、閉めることの不安に目覚める。疑いは終わらない。終わることがない。疑いは繰り返され、疑いは鳴り響く。ダンダンダダン、ダンダンダダン、と鳴る。
ダンダダダンダダダンダダダダダダダンダダダンダダダンダダダダダダ。ダンダンダダンダンダダンダンダン、ダンダンダダンダンダダンダンダン。ダンダンダンダダンダダンダンダダン、ダンダダンダダンダンダンダンダン。
僕はやっと気付く。「冷蔵庫らしきもの」とは、「冷蔵庫」でも「こいつ」でもなく、楽器だったのだ。楽器だ。これは楽器だ。これは楽器なんだ。楽器だ。楽器なんだ。楽器だ。楽器なんだ。楽器だったんだ。楽器だ。楽器なんだ。これは楽器だった。楽器なんだ。楽器だ。楽器だ。楽器なんだ。楽器だ。楽器だったんだ。楽器だ。楽器なんだ。楽器だ。楽器なんだ。楽器だったんだ。楽器だ。楽器なんだ。楽器だった。楽器なんだ。楽器だったんだ。楽器だったんだ。楽器だったんだ。