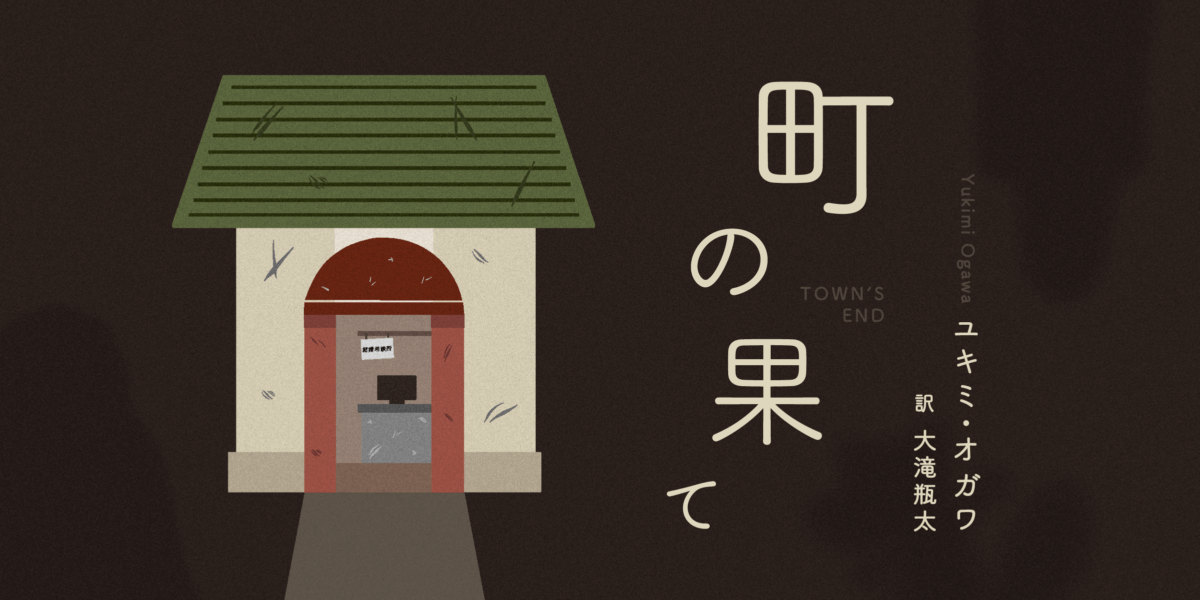先行公開日:2021.5.15 一般公開日:2021.6.25
ユキミ・オガワ「町の果て」
原題:Town’s End
翻訳・解説:大滝瓶太
10,271字
町の果てにある結婚相談所の受付で、思わず口元がひきつってしまった。「あの、もう一度おっしゃっていただけますか?」
「男が欲しいの」目の前の女性は繰り返した。「どうしても子どもを産みたいのよ」
わたしはパソコンを見ながら口角に指を当て、口元がヒクヒクしているのをバレないようにした。無駄な抵抗だった。「そうですか、ずいぶんはっきりおっしゃいますね。そうした類のご要望でございましたら、まずは男性と親しくなってからその旨をお伝えしてみてはいかがでしょうか」
「え、どうして?」
「男性が怖がってしまいます」
「そうなの? 知らなかったわ」
その女性は見たところ神経質で、かきあげた髪を一筋、マスクの紐といっしょに耳にかけていた。きっちりつけたマスクは不織布ではない、布製のむかしなつかしのものだ。「風邪をお召しでしょうか? それとも花粉症ですか?」
彼女は首を横に振った。毛量が多く、長く黒い髪はほとんど動かなかった。
古風な髪型とマスクの下は、まるで死装束みたいに白くて長いワンピースを着ていて、彼女の青白い肌には不気味だ。わたしは服についてアドバイスすべきか迷った。「その格好だと男性も怖がってしまいますよ。どうしてもという理由がなければマスクを外してください」
「え、そうなの? そう……」
この女性、キムラサエコは、遠くの地方の出身だという。それを理由に卒業した高校名を頑なに口にしたがらず、情報らしい情報を何も教えてくれなかった。どんな生活をしているのかはもちろん、歳はいくつなのかさえ教えてくれないけれど、見たところわたしと同い歳くらいだろう。三十代中頃とか、そのあたり。彼女は四ヶ月前にここで働きはじめてから初めてのクライアントになる。彼氏と別れ、都会からこの小さな町に去年帰郷してきたが、仕事は半年見つからなかった。生まれ故郷の町外れでようやっとこの結婚相談所の仕事を見つけたものの、他の選択肢などありはしなかった。
職場は社長の家の隣にある。彼はその家に住んでいるとはいうけれど、そんな気配は一切ない。社長と会ったことはなく、数週間前に痩せて背の高い人影を網戸に一度見かけただけだ。やりとりはメールでのみ行われ、顔を合わせるはおろか電話すら使用しない。
「だけどわたしがマスクをとったら、それこそ男が怖がって逃げてしまうわよ」キムラさんはいった。への字に曲がった眉のあいだに皺がよると、いかにも幸薄い女性といった雰囲気が醸し出された。「とにかく人間の精子が必要なの」
都会での五年間、わたしは英会話学校の受付係として働いた。そこでは数えきれないほど大量の、そして根も葉もないようないいかげんな愚痴が捌ききれないほどあふれていて、本心を顔に出さないように能面みたいな無表情でやりすごすスキルを身につけた。だけどそれはこの現状ではまったく役に立たなかった。「単にだれかと寝たいと?」
「ええ」回答は早かった。「コンドームなしで」
さすがにちょっと笑ってしまった。「そういうことでしたら、他を当たっていただけますか。ここは妻や夫を探しているひとが来る場所なんです。そういうコミュニティがあるSNSに登録されてみてはいかがでしょうか」
「SNSってなに?」
「コンドームは知っていてSNSは知らないんですか?」
「カップルが使っているのを見たことがあるわ。使い終わったら茂みに捨てていたかしら」
「じゃあスマホは持っていますか?」
「ないわ」
「持っていない?」わたしは半分疑いながらきいてみた。「パソコンは?」
「持ってないわ」
わたしは考えた。彼女の要望に応えるなら、スマホを持たせて然るべきサービスをググるように教えてあげたほうが楽だ。しかし彼女はこの仕事ではじめてのクライアントで、この職に就いてからの四ヶ月はこの小さな事務所を掃除する以外になにもすることがなかったのもあり、せっかく訪れた他人と会話するチャンスを逃したくなかった。
「プランのご案内は上の者に確認をとってからにはなりますが、」わたしはいった。「とりあえずこのパソコンを使っても構いませんし、SNSの使いかたはわたしが教えましょう。たぶんそれで──費用は通常の三分の一に抑えられます。許可が降りたら、そうなさいますか?」
キムラさんは眼を輝かせた。首がもげてしまうんじゃないかというほど彼女は熱心に頷いた。
*
わかったと社長からメールが返ってきた。キムラさんに固定電話で電話すると(出るまで時間がかかるけれど、切らずに待っていてほしいと彼女はいった)、翌日また来ると彼女はいった。そして彼女はやって来た。わたしたちは熟年層のユーザーが多いとおぼしきサイトを選び、彼女の素性を悟られず、かつ決して嘘にはならないメッセージをいくつか送った。一通のメッセージが返ってきた。この事務所を待ち合わせ場所にしてもいいと彼女にいった。男性にはピルを飲んでいると伝えるよう教えた。なんのピルかはいわなくていいとも添えた。
数日後、キムラさんは事務所に駆け込んでくるなりカウンター越しにわたしに抱きついてきた。
「ありがとう」という彼女が笑顔なのは肩越しにでもわかった。「彼はマスクを好いてくれたし、裸になっても顔をすっぽり隠せるものを持ってきてくれたの!」
「そ、そうですか、よかったです。でもそれじゃあ求めていた精子が手に入ったかわからないんじゃないですか?」わたしは彼女の背中を数回叩きながらいった。
「ちゃんと手に入ったわ。わたしたちにはちゃんとわかるの」
「わたしたちとは?」
「同胞よ」
「そうですか」
抱擁が終わり彼女は一歩下がると眉をひそめた。「どうなさいましたか?」わたしはたずねた。
「あなたは立ち入ったことを聞いてこなかったわね? わたしがすこし……変なのは、じぶんでもわかっていたから」
この一言でわたしの表情は緩んだ。「お気になさらず。あなたは大人の女性なのですから」
「ほんとうにありがとう。あなたのおかげよ」
「お役に立ててなによりです」
支払いはもう済んでいたけれど、彼女は個人的な感謝の意としてわたしに封筒をくれた。なかには使い古しのプリペイドカードが入っていた。総額でおよそ三万円になる。「多すぎます」わたしは首を横に振り、彼女に返そうとした。
キムラさんは首を横に振り、わたしにカードをしっかりと握らせた。「これはわたしたちがかき集めたすべて。わたしたちにとってすごく大事なステップだったし、その感謝に比べたら安いものよ。それに、お金なんてわたしたちには無用の長物だから」
「え?」間抜けな音がわたしの口唇からこぼれた。彼女のことばの意味がまったく理解できなかった。
キムラさんは微笑み、わたしの手を撫でさすった。「ありがとう」彼女はふたたびそういうと去っていった。
わたしは社長にメールで事の顛末を伝え、愚かにもプリペイドカードの一件も含めてすべて報告した。返信はたった一言だった。「わかった」
*
いったいなにをやらかしてしまったのか、数日後、また妙な客が受付に現れた。双子の兄弟だった。「あなたについて、いろいろとお話はうかがっています」左側がいった。「彼女たちを助けてくれたのはあなたでしょうか」
「はい、キムラさんのことでしたら、わたしが担当させていただきました。しかしあなたがたは幼すぎますね」もう能面はやめていた。
「ぼくたちはある女性を守っています」左側がいった。「彼女のところへ来てくれる方を探しています」右側はなにもしゃべらない。
「どこへ?」
「森のなかの神社です」
わたしはそこをうすぼんやりとおぼえていた。「太陽の神を祀っているところですか?」
「そこです」
「で、その女性は精子が必要だと?」
「はい」
笑うべきか叫ぶべきかわからなかった。「その女性をどこかのホテルに連れていけばいいのではないでしょうか? 見ず知らずのひとをあなたがたの住処に連れて行くのは簡単なことじゃないでしょ」
双子は互いを見つめ合い、それからまたわたしを見た。「彼女は体がとても弱いのです」
「体は弱いけれどセックスはできると?」
「神社でならできます」
「彼女は巫女ということでしょうか?」
左側はもうひとりを一瞥した。右側は肩をすくめただけでなにもしゃべらない。「なんといいますか……」おしゃべり担当が口を開いた。このときはじめてわたしから眼を背けた。
「……紹介した男性に危害を加えるつもりはないですよね?」
「まさか! サエが男性を傷つけましたか?」
わたしはちょっと考えた。この町で凶悪犯罪があったなんて聞いたことがなかったので、まぁ嘘をついている訳ではなさそうだ。「はい、わかりました。しかし、あなたがたの神社に男性を誘い出すには理由を作らなければなりません」
「何かいい方法はありますか?」左側はほっとしているようにも苛立っているようにも見えた。
わたしはパソコンを覗き込み、かなりがんばって考えてみた。「えーと、あなたがたのその女性っていうのは、巫女ってことでいいですよね」
「というと?」
「世の中にはアブノーマルなシチュエーションで興奮するという方がいます」わたしはいった。「そうした方々をターゲットにするなら、あなたがたは神社に閉じ込められた巫女がいると話してみてください。そしてそこに来た男性に、彼女がこういうのです。ここは聖なる場所だからそういう行為はできない、と。このシチュエーションが男性を欲情させます。どうしてもそこでしたくなって我慢できなくなり、彼女の身につけている衣服を引きちぎって……」
双子の兄弟は赤面した。「あの、はい、大丈夫です──わかりました。では募集広告を打つことはできますか?」彼は口ごもりがちにしゃべり、しゃべらない方はずっと足元を見ていた。
わたしはニヤッとした。「ええ、問題ないですよ。プランをその女性にお伝えし、明日また来てください。彼女のプロフィールとメッセージを準備しますので」
「わかりました、ありがとう」
彼らが去ったあと、わたしは社長の許可をとっていないことに気づいた。メールを送ると、「わかった」と返事があった。
*
双子は翌日にまたやって来て、シチュエーションを掻き立てるような巫女装束を用意したといった。わたしは声を出して笑い、計画にぴったりのサービスを探しはじめた。
「彼女はどんな容姿ですか?」
「きれいです」左側はそういうと顔を赤らめた。「スレンダーです。ちょっと目鼻立ちはきついですが、きれいです」
「クールビューティーって感じですか?」
「はい」
わたしは眉をひそめた。「あなたたちはほんとうに彼女が他の男と寝てもいいんですか?」
「どういう意味でしょうか?」
「じぶんが寝ようとは思わないのですか?」
双子はどちらも顔をいっそう真っ赤にした。「え、そんな。ぼくらは彼女の同胞じゃないんですよ。できるわけがないじゃないですか」
「へぇ」
キムラさんにしてもそうだったが、どういう意味で「同胞」ということばを使っているのか聞きたかった。しかし聞くのは賢い選択ではないように思えた。わたしは肩をすくめ、ググって二、三のサービスを見つけた。
数日後、狭い神社で事に及ぶスリルにご執心な男性からメッセージを受信した。男性が迷うといけないので事務所の電話を双子に使わせてあげた。しかしそんな必要はなかった。
彼らが落ち合った翌日、双子はよろこび勇んで事務所にやって来た。「彼女はとてもうれしがっていました。男性も満足だったそうです」
「しているところは見ましたか?」
「ま、まさか! 見てないですよ!」
わたしは笑った。
少年らは少し恥ずかしそうにしてから、小さな紫色の布袋をわたしに手渡した。なかには意味の取れない知らない文字が書かれた小さな木片が入っていた。
「証です」おしゃべり担当の少年が真面目な顔つきになった。「それはあらゆる事からあなたをお守りします。もう地震を心配しなくても大丈夫です」
「スピリチュアルな絵を売りつけようとしてきた女性も似たようなことをいっていました」
わたしは冗談のつもりだったけれど双子は笑わなかった。「それは本当に力があって、ぼくの知る限りでは彼女があなたがたの同胞に渡したことはありません。いいですか、決してひとに見せてはいけませんよ? それを喉から手が出るほど欲しがっている種族だっているんですから」
わたしはその記念品をぎゅっと握りしめた。「わかった。ありがとう」
彼らは微笑み、頷いた。「あなたには感謝しています。ぼくらは忘れません。世界には色褪せないものもありますから」
意味がよくわからず、わたしは首をかしげた。しかしすぐさま彼らは踵を返し、事務所を後にしていた。
*
おそらくわたしは彼らがなにをいっているのか詳しくきいておくべきだったのかもしれない。キムラさんにしろ双子にしろそうなのだけど、その後も変なクライアントが続々とやってきた。ある女性はキムラさんよりさらに顔色が悪く、着物を持ってきては支払いをそれで済ませたいと言い出した。その着物は見たことも触ったこともない繊維で織られていて、社長が許可したので着物払いを受け付けた。また別の女性は全身真っ黒なドレスを着ていて、東京の最果てにある山への行きかたを聞いてきた。この件に関してさすがにお代はけっこうですというと、彼女はわたしのおでこに触れ、「いつもあなたに神のご加護がありますように」といった。
そんなある日、ひとりの少女がやってきた。明らかにいままでのどのクライアントよりも幼かった。わたしはちょうど引き出しに入っていたチョコレートを彼女にあげた。
少女はチョコレートを食べると満面の笑みになった。「お返しになにをあげたらいい?」
「いいのよ。それを食べたら帰りなさい、あと五年経つまではここがどういうところか知らなくてもいいわ」
「でもわたし、ちゃんとおとなだよ。わたしたちの同胞ではそういう事になっているの。もう子どもを作れるんだから」
また同胞だ。「じゃあ、あなたたちの同胞の男の子とよろしくやればいいんじゃないの?」
彼女はチョコレートのついた指を舐めると眉をひそめた。「面倒なことは聞いてこないって評判だったんだけど」
「お相手を探して欲しくないなら、別に話さなくてもいいのよ」
少女はくすっと笑った。「わたし、あなたのこと好きよ。人間なんて大嫌いなんだけど」
「それは光栄ね」
少女は突然かしこまった。「一緒に来てください。そこでわたしがちゃんと成人していることを証明します」
「どう証明してくれるの?」
「ちゃんとします。でも、ここじゃできません」
少女はわたしを見つめた。彼女の茶色い瞳は名付けえない奇妙さで輝いていた。まるでわたしの瞳から脳へと何かが入ってくるような、そんな感覚があった。眼を背けようとしたけれどなぜかできなかった。
わたしは首を横にふった。「ここを離れちゃダメなの。仕事だから」
「終わってからは?」
「食材の買い出しに行かなくちゃいけない」
少女は微笑んだ。「いずれまた来るわ。そのときはわたしと来てくださいね」
そうして彼女は去っていった。チョコレートの香りを含んだ奇妙な匂いがあたりに漂っていて、わたしは窓を開けた。しかしそれはずっと消えずに残った。
わたしはその少女について社長にメールをした。いつものように、返信はたった一言だった。「やめろ」。これはどういう意味なのだろうとわたしは思った。知らないひとにチョコレートをあげたのがいけなかったのか、窓を開けてはいけなかったのか、それともそもそも幼い少女をここに入れてはいけなかったのか。
それともその少女について行ってはいけないという意味なのか。
*
次の日は休みだった。ちょっと洗濯をしたりネットサーフィンをしたり、日中を自堕落に過ごした。夕方になって夕飯のことを考えていると、醤油を切らしているのに気がついた。そんなはずはなかった。あと一食分くらいは残しておいたつもりだ。どう勘違いしていたんだろう?
ため息をついて車に乗った。隣町に住む叔母は余分に醤油を一本持っているかもしれない。もう部屋着に着替えていたし化粧はしていないし、髪もぼさぼさだったので、店に買いに行きたくはなかった。
エンジンをかける。陽はすっかり落ちて夜になっていた。数分後に車はトウモロコシ畑の狭い道を走っていた。あたりに街灯はなく、本当に真っ暗だった……
そのときバンパーに何かがぶつかった気がした。
わたしは急ブレーキを踏んだ。道には誰もいなかったので、猫かなにかの動物だと思った。なにか小さい動物だ。でも車をぶつけたことなんて一度もなかった。手が震えはじめていた。エンジンをつけヘッドライトを照らしたまま、運転席を降りて車を確認した。
バンパーになにかがぶつかった形跡はなかった。あたりを見回す。闇が広がっているばかりだ。車の前方をヘッドライトが照らしているだけで、目に見える異変は確認できなかった。
視界の端でなにかが動いた。
そっちを向いて闇の奥に目をこらした。なにかがトウモロコシ畑に飛び込もうとしていた。それからすすり泣く声が聞こえた。わたしは息をのんだ。
「あなたなの?」わたしは声をかけた。名前がわからなかった。そもそもきいた憶えがなかった。「あなたは……チョコレートをあげた……」
少女はふたたび泣きながら背の高いトウモロコシをくぐりぬけていく。「待って! 怪我をしているの?」わたしはそういって、彼女のあとを追いかけた。
やめろ
なにかが脈を打った。わたしの心臓の鼓動じゃない。着ていたポロシャツの胸ポケットにその拍動を感じた。
双子がくれた証だ。
しかし少女はもう一度すすり泣きはじめた。足を引きずっているような足音がした。
わたしは急いで彼女のあとに続いた。
*
どこまでもトウモロコシは続いていた。数は途中でわからなくなったが、それが無限に続いているのは頭のどこかでわかっていた。熟れたトウモロコシがあった。青いトウモロコシがあった。どれもが奇妙な周期で揺れ、脳に直接入ってきて眠りへといざなってくる。わたしは走った。呼吸は歌うようにリズムを刻むが、歌ではない。ところでわたしはなんで走っているのだろう?
*
トウモロコシ畑を抜けると小川にたどりついた。
あちこちで蛍が舞っていた。点々と飛び交う光がとうに萎れたアジサイに触れると、花は生命を吹き返し、青、紫、ピンクと薄明かりのなか生き生きと色づいてゆく。見上げると天の川が輝いていた。星の光を水面が弾き、小川が地上の天の川となった。
対岸には男が立っていた。ポケットに手を突っ込み、微笑んでいる。
「どうして?」わたしはそう声に出していた。「どうしてあなたがいるの?」
「迎えに来たよ」
「うそ」
彼は首を横に振り、悲しげな笑みを浮かべた。「ぼくがまちがっていたんだ。あの女のところに行くべきじゃなかった。きみと別れるべきじゃなかったんだ。ごめんね。ぼくが愛しているのはきみだけだ」
「うそ──うそよ……そんな」
元カレはポケットから手を出し、天の川を飛び越えてわたしの目の前に降り立った。彼はわたしの手をとった。「ごめんね。許してくれるかい?」
またしても脈を打った。心臓の鼓動じゃない。
「でも……」
やめろ
「お願い」彼はそういうとわたしにキスをした。
どうして違和感を抱かなかったのだろう? わたしたちは天の川の下でキスをしたことなんて一度もなかったし、川辺でキスをしたこともなかった。得体の知れない欲望が湧き上がった。心の奥深くに沈めていたものが、表面に浮上してきたような心地だった。それはわたしの実際の記憶としてある感情ではなく、もしかしたらわたしが無意識のうちに求めていた感情なのかもしれない。考えても無駄だった。世界はその中心にいるわたしたちを置き去りにして回っていた。彼の舌がわたしの舌を探っている。するとわたしは立っていられなくなった。彼の手は下の方へと降ってゆく……
「やめろといっただろ!」
わたしは息をのんで彼を突き飛ばした。彼とキスをしていたのだから、聞こえたのは彼の声ではなかった。もらった証がいままでで一番強く脈打ち、そして暖かく、白い光で照らされた空間に水飛沫が舞った。元カレは──元カレに似ているだれかは──よろめいて小川に落ちた。
するとあたりの光景は崩壊していき、やがてなにもなくなった──
意識が途切れる直前、よろめき倒れるわたしはだれかの腕に受け止められた。
*
瞼を開くとキムラさんがわたしを見下ろしていた。彼女は微笑み、わたしの手をさすっていた。「目が覚めたわ」と彼女はいった。
彼女のことばで周囲がざわついた。視界にいろんな顔が現れた。双子、着物の女性、そしてその他の担当したクライアントたちだ。
わたしは薄い布団に横たわっていた。あたりの様子はよく見えなかったけれど、天井のつくりからしておそらくは神社の本堂だった。わたしは双子を見た。
「あなたたちの住処?」
ふたりはうなずいた。上下逆さまにわたしを覗き込んでいる顔があった。とてもうつくしい顔だった。
「こんにちは、人間さん」
わたしは笑った。「こんにちは、女神様」キムラさんに支えられながら体を起こした。「これはどういうことなの?」
わたしは彼女にたずねた。
キムラさんはため息をつき、下を向いた。それからまた顔を上げ、こういった。「まず、わたしたちはあなたに危害を加えるつもりはないわ」
「あなたたちが襲ったのなら、もっと前に襲っていたでしょうね」
彼女はうなずき、マスクを取った。マスクの下には耳から耳まで裂けた大きな口があり、一目見るなりわたしは息を詰まらせた。
双子はひょこっと現れると宙返りし、着地すると二頭の狛犬になった。片方の口は塞がれていて、それがしゃべれない理由だったとわかった。着物の女性がくるりと身を翻すと、うつくしい鶴の姿になった。
他のみんなもそれに続いた。黒ずくめの女性は微笑むととても大きな翼を見せてくれた。雪女はきらめく氷の息を吹いた。わたしは首を振り、あきれて笑うしかなかった。「でもどうして人間とセックスしたがっていたの?」
わたしを気遣ったのか、キムラさんはマスクをつけなおした。「わたしたたちの数は減っているの。すぐにでも絶滅するでしょうね。そうならないように交配相手を見つけて子どもを産まないといけなかったのだけど、わたしたちの同胞には男がほとんどいなかったの。そこで差し当たっては人間の男で作ることにしたのよ。知ってるでしょ、わたしたちの遺伝子は強いから」
知らなかった。「そういうことだったのね」わたしは適当に話を合わせた。
「ごめんなさいね。あなたのことをあちこち言いふらすべきじゃなかったわ。まさかタヌキがおなじことをやろうとするなんて考えてもみなかった」
「タヌキ? それって……化けてひとを騙すっていう、あのタヌキ?」
「そうよ。たったいま、あなたが会ったのがタヌキ」
わたしはうなずいた。つまり、あれは彼ではなかったのだ。元カレとはとっくに別れていたし、わたしよりもかわいくて、お金持ちの女のところへいった。「タヌキはわたしを妊娠させようとしていたの?」
「ぼくたちにはにわかに信じられないことですね」狛犬の片方がすでに深い皺だらけの眉間にさらに皺を寄せた。「ぼくらのような動物型は人間型とは交配できないんです。それに、人間の男から精子を借りるのと、女性の子宮を勝手に使うのでは、ぜんぜん意味がちがいます」
周囲の他の妖怪たちが口々に同意した。
わたしは女神と対面して姿勢を正した。「どうもありがとうございました。きっとあなたがくれた証が助けてくれたんですね」
女神はうなずいた。「そうです。でもここにあなたを連れて来てくれた男性にもお礼をいったほうがいいですよ」
「だれがここへ?」
「さぁ、あれはだれだったのでしょう?」
女神はあたりを見回した。だれもこたえなかった。キムラさんは首を横に振る。「だれも彼が何者かはわかりません。おそらく人間だと」
胸がうずいた。「わたしとおなじくらいの年齢ですか? 日焼けして大柄でしたか?」
彼女は首を横に振った。「そうには見えなかったわ。痩せ型で、背が高くて、色白で。眼鏡はしていたっけ?」
ある者がしていたといい、ある者がしていなかったといった。わたしの期待が潰えた。どうやら元カレではないらしい。
それから車の音が聞こえた。神社の前に停まったようだ。双子が確認しにいってくれて、戻ってくるなりふたりは首を傾げた。「誰かが鳥居の前に停めていたんだけど、これがぼくらの台座に置かれていました」そういうとチェーンで繋がれた一対のキーを取り出した。
「わたしのキーだわ」
「運転手はもういませんでした」
キーを手に取り握りしめた。わずかにあたたかかった。するとあの声が思い出された。「やめろといっただろ!」
わたしはキムラさんと他の面々に微笑んだ。「それじゃあ帰ります。もうタヌキについていかないって約束します」
女神が厳かにうなずいた。「もしなにか困ったことがあったらここへいらしてください。わたしが留守でも双子はいつも鳥居にいますから」
「ありがとう。あと、子どもができたら教えてくださいね?」
キムラさんは驚いているようだった。「てっきりもうわたしたちに関わりたくないと思っていたわ」
わたしは笑った。「わたしが担当したクライアントのしあわせを見たくないような女に見えますか?」
*
帰り道に職場に立ち寄って社長にメールを送った。「ありがとうございました」と書いた。
数分後に返信があった。
「どうも」とそこには書かれていた。
※「町の果て」は2013年にStrange Horizonsに掲載された英語の原作小説「Town’s End」を大滝瓶太さんが日本語訳した作品です。原文はこちらから読むことができます。
解説──「魔境」へのいざない 大滝瓶太
ことばが先か、それとも物語が先か──小説を書くにおいて、そもそもなぜ書けてしまうのかまで遡って考えたなら、その問いがとりあえずの行き止まりになる。散文表現の問いの果てでは、ことばとモチーフが奇妙に捻れながら循環し、安易な批評を嘲笑うかのように煙に巻く。ことばの故郷(home)たる物語はことばに導かれて我々の世界へやってくるのだが、ともかく、そのように言語と物語が渾然一体となった結晶物を傑作と呼ぶらしいことはわかっている。小説家Yukimi Ogawaの描き出す世界はそんな魔境だ。
2012年にデビューして以来、SF/Fのフィールドで精力的に短編作品を発表する彼女の最大の特徴はその言語とモチーフにある。著作のすべては英語でのみ発表されている一方、日本民話や昔話に由来する数々の怪異譚で高い評価を受けていて、「母語が日本語の作家によって英語で書かれた純日本的な作品」と表面的にとらえると、そこにいささか奇妙な捩れを感じずにはいられない。Ogawa自身は「日本語で小説を書けなかったから英語で書いている」と語り、自身の手による日本語翻訳の予定はないという。その所以について、他者でしかない我々はせいぜい想像力をたくましくするしか思考の手立てはないが、そこに表現と言語の未だ明かされざる関係性が潜んでいると考えるのは、あながち的外れでもないだろう。
今回拙訳にて紹介した短編「町の果て」(原題“TOWN’S END”)は、リッチ・ホートンによる年刊SF・ファンタジー傑作選(The Year’s Best Science Fiction & Fantasy, Ed. Rich Horton, Prime Books, 2014)に収録された作品だ。結婚相談所に勤める人間の女性が、口裂け女をはじめとする女性怪異たちの性交渉の仲介をするという筋書きで、その語り口は平易なことばと現代日本のカジュアルな生活感で形成されている。
彼女らのやりとりには大なり小なり何らかの奇妙さが含まれており、主人公クライアントとからかい半分のユーモアをまじえて交流を重ねていくが、両者の価値観の決定的な差異として現れるのは「同胞(kin)」ということばだ。主人公はクライアントたちが口にすることのことばの意味を捉えあぐねており、「同胞」のコンテクストをめぐって物語が動き出す。
人間と怪異──その両者の存在ないし世界には遠い隔たりがあるように感じられるが、Ogawaの作品では両者が地続きで等価なものとして扱われている。彼女の作品では、我々が正常と感じる現代日本的価値観のオルタナティブな世界として怪異たちの世界があるわけではない。我々が異常におもえる存在のすべてはひとえに我々の観測点の問題でしかなく、ただ出会わなかったこと、見えてなかったことを理由にその特異さを感知しているに過ぎず、ほんとうははじめから我々が正常とみなす世界のなかにちゃんと存在している。本作の舞台となる「町の果て」とは、そんな共生・共存のリアリティが織りなす「魔境」だ。口裂け女をはじめとする妖怪たちの世界も、地上の天の川も、「ここではないどこか」ではなく「いまここにある世界」である。
ひるがえって、それは小説そのもののありかたでさえおなじではないだろうか。Ogawaの作品のように、日本語では書かれなかった日本文学は日本語読者にとっての魔境として存在している。母語から旅立つことによりその世界を発見したOgawaの作品世界を日本へと放つことができるなら、ぼくはよろこんでその共犯者になろう。
大滝瓶太
1986年生まれ。作家。2018年第1回阿波しらさぎ文学賞を受賞。現在は小説、文芸批評、書評、エッセイなど幅広い文筆活動を行なっている。『小説すばる』にて、書評「理系の読み方」を連載中。新作「ザムザの羽」が掲載されている『S-Fマガジン』2021年6月号は、SNSを中心に話題沸騰中。