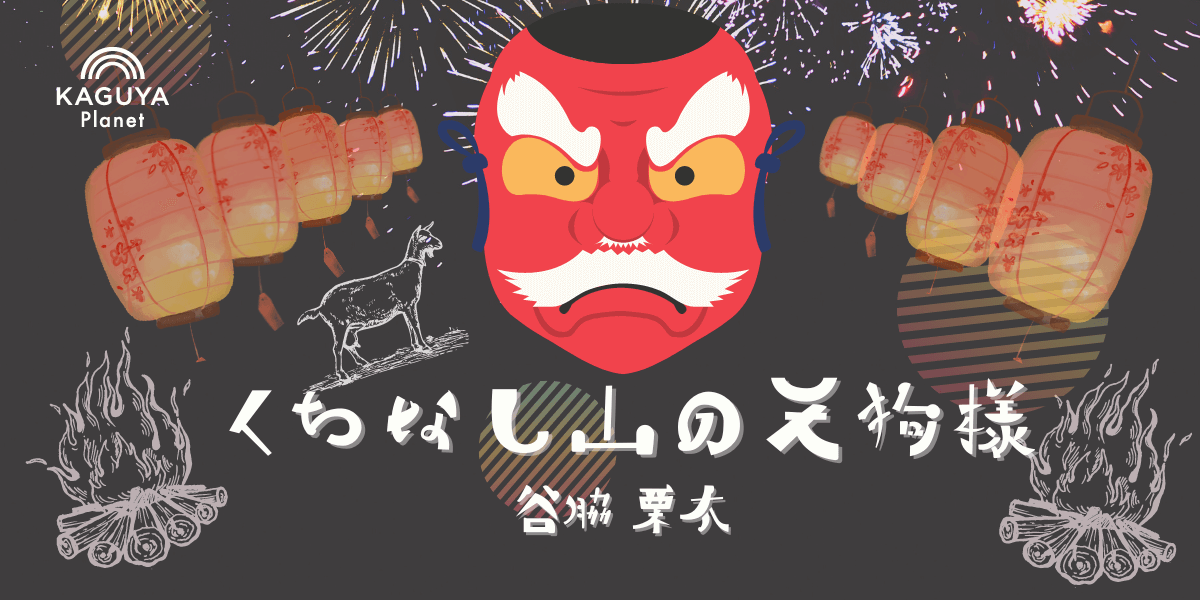先行公開日:2023.4.22 一般公開日:2023.5.20
谷脇栗太「くちなし山の天狗様」
5,827字
焚き火を囲んで山の子供たちが回る。跳ねる。笑う。木々の影からは闇の一族が這い出してきて、炎の精と手を取り踊る。明暗のゾートロープが子供たちの一瞬を切り取り、永遠に引き伸ばす。明・暗・明・暗・明・暗・明……
今宵の天狗様は立派な髭を生やした黒ヤギの皮を頭から被って、一年熟成させた乳酒に酔いしれている。木の葉の皿の上では野草で香り付けをしたヤギ肉が湯気を立てる。縞柄の洋服に身を包んだ子供たちは天狗様の手を引いて踊りの輪に誘う。ある子供は炎の翼で宙を舞う。ある子供は虎に変身して火の輪をくぐる。いつもまん丸な天狗様の目は細く垂れ下がって、顔の皺に隠れてしまう。縞々模様の子供が回る。跳ねる。笑う。街の灯ははるか遠く、風が吹けば消えてしまいそうなほど小さく――。
*
一面の緑の中に佇む臙脂色の屋根が、日の丸弁当の梅干しみたいに小さく見える。朝の放牧から戻らないハナコを探して尾根近くまで来てしまったが、一気に駆け下りれば給食までには余裕で間に合うはずだ。
匠が追い立てると、さっきまで崖の上で震えていたハナコは岩がちな斜面をぴょんぴょん器用に降ってゆく。その後に続いて、匠も岩場から岩場へ、ほとんど垂直落下するように跳び降りる。匠の半ズボンからすらりと伸びた足を覆う黒い縞模様は、着地のたびにバネのように収縮し、また地面を押し返す。くっきりと黒い帯状に見えるのは、そこだけ硬く変質した皮膚の上を艶やかな獣毛が覆っているからだ。
その様子を恨めしそうに睨みつけながら、丸尾は緩やかな斜面に尻餅をついて次の足場を探していた。匠が少し待ってやると、「なんや、嫌味か」とか「僕は置いて行け」とか口だけは威勢がいい。
「みんながタクみたいに恵まれてるわけとちゃうんやぞ」
半ベソで丸尾が叫ぶ。たしかに、匠はくちなし園の生徒の誰よりも濃い天狗痣を持ち、誰よりもその能力を引き出していた。丸尾はどちらかというとその逆で、いつも長袖と長ズボンで自信なさげに肌を覆っていて、運動神経も並以下だ。
「お前なあ、痣は使わな濃くならへんって先生も言うてたやろ。給食までに戻ろうぜ」
匠が促すと、丸尾は「余計なお世話ですー!」と舌を出す。
「せやけど今日は揚げパンの日やぞ。ええんか」
大好物の名前を出された丸尾は押し黙り、小さく肩を震わせている。匠は仕方なく丸尾のところまで戻り、小柄な体を斜面から引き剥がして肩に背負いあげる。それから足に力を込めて、岩場を降ったところでこちらを見上げているハナコを追いかける。
「あとお前、今日は放課後の小屋掃除、忘れんなよ」早生まれで小柄な丸尾に対して、匠はついつい弟に対するように接してしまう。園の中でも古株の匠は、教員たちからも同級生の保護者役を期待されることが多い。
くちなし園に預けられてもう五年になる。自分より子供っぽい同級生たちと寝食を共にするのはともかく、ヤギ達の世話をし、野山を駆け回る生活は嫌ではなかった。失踪した父親のせいで周囲から冷たい扱いを受けてきた里での生活を思えば、血縁や世間体に縛られない山の子供であることは匠にとって心の拠り所であり、天狗痣はその大切な徴だった。だから今日も、艶やかな縞模様をお天道様に見せつけるように山を駆け回る。ゴマ粒程にも見えない下界の家々を見下ろして。
「マル、それで野営会はどうするん」
匠は背中に負ぶった丸尾に問いかけるが、返事はない。肝心なところで顔を伏せる。すぐ逃げようとする。丸尾のこういうところがしばしば匠を苛立たせる。
くちなし園からさらにいくつか尾根を越えた合宿所で行われ、高学年だけが参加を許される野営会。園生たちの間ではある噂がまことしやかに囁かれている。山中に本物の天狗が棲んでいて、天狗痣に関する秘密の術を教わることができるというものだ。今年は二人にとって初めて野営会に参加できるチャンスだ。天狗がいるかどうかはともかく、天狗痣の秘術の噂には匠も惹かれるものがあった。しかし、このところずっとこんな調子の丸尾はどうだろうか。園の裏山で苦戦しているようでは、そもそも連れて行ってもらえないのではないか。その不安は丸尾本人からも伝わってくる。
「……花火する」丸尾は耳元をびゅんびゅん流れる風に紛れてしまいそうな声で同級生の背中に呟いた。
「僕は野営会で花火するためにくちなし園に入ったんや」
それきりまた黙り込む。五月の風や木々や光はおしゃべりで、トンビがピンヨロロ……と正午を告げる。
午後の授業中、匠と丸尾は机に突っ伏してよく眠った。担任の倉田先生がいつもより少しだけ小さな声で授業を進めたのは、今朝の捕り物を知っていたからだ。
神社の夏祭りであの花火を見つけたときの驚きを、丸尾はいつでも鮮明に思い出せる。テキ屋の男は手持ち花火を何本も指の間に挟み、パチンと指を鳴らして火を点けた。色とりどりの炎が紙の筒から吹き出したかと思うと、火花が小さな虎になって火の輪をくぐる。次の瞬間には無数の火の鳥になって夜空を明るく埋め尽くす。最前列にしゃがんでいた丸尾はその魔法に魅入られた。持たされたお小遣いを全部はたいて花火を買って帰ったが、祖父の家の庭ではどれもほんの短い間、ありきたりな火花を吐き散らしただけだった。泣きじゃくる丸尾の頭をポンポンと叩きながら、「天狗に化かされたな」と祖父は笑った。
「天狗のお山の野営会においで」
最後の火花が消える間際、虎や火の鳥のかわりに、花火を手渡した時のテキ屋のざらついた声と黒白の縞柄のぼろ着、火薬の匂いに混じる濃厚な土と草と獣の匂いが蘇った。
筋金入りの不登校だった丸尾がその後、全寮制のくちなし園に入ることになったのはまるっきりの偶然で、そこで天狗のような少年に出会ったのも想定外のことだ。今わかっているのは、野営会が半月後に迫っていて、お山のどこかにいるという天狗は丸尾をそこに招く気がなさそうだということ。長袖のシャツとズボンの下で、丸尾の縞模様は中途半端な赤茶色のまま成長をやめてしまった。
思い当たることはある。実習で市内を訪れた昨年の夏だ。園に食品を卸している商店の店主からの申し出で、売り場の一角を借りて販売実習をさせてもらうことになったのだ。園生たちはこの日のために用意した臙脂色のエプロンをつけて、あらかじめ考えていた短いフレーズでくちなし印のヤギ乳チーズやバターを宣伝した。物珍しさもあってか売れ行きは上々で、売り場作りに精を出した丸尾は鼻高々だった。
一方、里に降りる行事がもともと苦手な匠は、痣が目立たないようにと長ズボンを穿かされたことが癪に障ったようで、カーテンを閉め切った園バスの中で一人携帯ゲーム機をいじっていた。
「こんなんブジョクやと思わへんか」
自由時間に匠の様子を覗きに来た丸尾には、投げつけられた言葉の意味がよくわからなかった。ただ、匠だけが不機嫌でいることを許せないという幼稚な正義感が丸尾を行動させた。売上金が入った巾着から五百円玉を一枚取り出して匠の手に握らせ、エプロンを丸めて座席に放り投げて、休憩のときに見つけたゲームセンターに匠を引っ張っていった。
匠が鬱憤を晴らすようにめちゃくちゃに床を蹴るたびに、画面の中で「EXCELLENT!」の文字が躍る。膝までたくし上げた長ズボンの下の縞模様は、ピンクやブルーのライトの中で生々しさを失い、ボーダー柄のソックスに見える。次第に周囲に人が集まり、歓声が沸き起こる。なんやこいつ、ゲーセンでもカッコええんかい。声には出さずに丸尾は唇を尖らせた。
ところが、しばらくすると歓声の中に耳慣れない言葉が混じり始める。どうやら匠の縞のことを言っているらしい。それも好意からというより、侮蔑や嘲笑のニュアンスを込めた言葉であることは丸尾にもなんとなくわかった。人数は多くないが、子供の声も、大人の声もある。丸尾の背筋にヒヤリと冷たいものが走る。怖い。自分の腕にうっすらと現れ始めている痣は? 暗いから見えないだろうか? とにかく今すぐ逃げ出さなければ。
丸尾が一歩、二歩後ずさったとき、匠は突然踊るのをやめて振り返った。肩を激しく上下させながら周囲を睨みつける。ズボンの裾が膝からずり落ちる。目を真っ赤にした匠と視線が合いそうになって、丸尾はとっさに顔を伏せる。
一度「聞こえる」ようになってしまうと後には戻れない。丸尾がいつも長袖や長ズボンを選ぶのは野外作業のためもあるが、それだけじゃない。痣が丸尾を選ばなかったのではなく、丸尾が痣を選ばなかったのだ。そんなお前には野営会で天狗に会う資格はないと言われれば、そうかもしれないけれど。
「これはブジョクとちゃうんか」
それが声に出ていたらしく、ヤギたちがぽかんとした顔をこちらに向ける。窓から差し込む西日が小屋の中をオレンジ色に染めている。「なに見とんねや、ほらほら食うてまうぞ」ちりとりを叩いてヤギを囲いの外に追い立てる。ほうきに持ち替えてシャッ、シャッと糞を掃き集めようとするけれど、一人ではちりとりが滑ってしまう。
ふと見れば、小屋の出口に人影が立っている。一瞬匠かと思ったが、もっと長身で、顔は影で隠れているが縞柄のぼろ着に見覚えがあった。
「おじさん、天狗ですか?」
自分でも驚くほど大きな声で、思ってもみなかった言葉が口から飛び出す。
「子供の肌に模様つけてヤギみたいにして、面白いですか?」
黙ったままの男に対して、丸尾は腹の底からふつふつと怒りが湧いてくるのを感じた。
「じゃあ、僕の痣を消してもらうことってできますか? 僕のっていうか、僕とタクの――」
五時のチャイムが鳴る。丸尾は寝ぼけまなこで顔を上げる。教室はがらんとして、シャッ、シャッ、という音だけが響いている。教卓で倉田先生がマル付けをしているらしい。
「おはよう、よう寝てたね」
「先生、天狗やったんですか」
何寝ぼけてんのよ、と言いながら倉田先生は腕を頭の後ろに回して伸びをする。先生も伸びをしたりするのか、と丸尾は妙なところに感動を覚える。
「なぁ丸尾君。野営会のこと、言っときたかったんやけどね」ギクリと反応する丸尾の顔を覗き込むようにして、倉田はとっておきの「やさしい先生」の顔を作る。「そんなに心配せんでも、行きたい子は全員連れて行くし、行きたくなかったら行かんでもええ。せやけどね、どっちにしてもしゃんとしなさい。しゃんと」
両手で目をこすると、まぶたに溜まった涙が目のまわりに広がってひんやりする。頭にかかっていた靄が晴れてくるような気がする。一番に浮かんでくるのはムスっとした匠の顔。それで思い出す。
「あっ、小屋掃除!」
掃き掃除が粗方終わった頃、前髪に寝癖がついたままの丸尾が小屋に駆け込んで来た。「起こしてくれたらよかったのに!」と抗議する丸尾に匠はちりとりを放り投げる。糞をちりとりで受けながら、丸尾は匠の足をジロジロ観察する。
「何や、気持ち悪い」
「僕さっき、痣消してもらうように天狗にお願いしてしもた。勢い余って匠の分も。ごめん」
「はぁ? まだ寝ぼけてるんか」
「僕が普通の子供になるんやったらタクも普通になればいいって思ったんや、せやけどタクは痣なんかなくてもカッコええし、僕は痣あってもポンコツやし、意味ないやんって気づいて、夢やしほんまに消えることはないやろうけど、消えたらいいって思ってごめん」
「やめろやめろそういうの聞きたないねん、恥ずかしいやろ」匠は糞のついたほうきで丸尾の頭をバシバシしばく。丸尾は泣き笑いの顔でごめんごめんと繰り返す。あと十分もすると、青草を腹いっぱいに蓄えたヤギたちが午後の放牧から帰ってくる。
*
結局、その年の野営会は丸尾と匠たちの学年全員が参加し、全員で合宿所にたどり着くことができた。険しい山道を丸一日歩き通したのはやっぱり相当きつかったけれど、あの匠さえも途中から「もう帰りたい」と言い出したことが、いい意味で同級生たちを諦めの境地に導いた。痣があろうとなかろうと、子供たちは二本しかない自分の足で土を踏みしめていくほかなかった。
合宿所に待っていたのは天狗ではなく、焚き火を囲んで教わったのも天狗痣の秘儀ではなかった。「島本さん」という名で紹介されたおじいさんは体育の増岡先生の肩を借りてパイプ椅子に腰掛け、子供たちに昔話を語って聞かせた。
くちなし園ができるよりずっと昔、島本さんたち山の子供は不思議な力を持っていたという。梔子山の大天狗が存命で、里から引き取った戦災孤児を山で育てていた時代のことだ。大天狗は山で生きる術として子供たちに神通力の使い方を教え込み、子供たちはそれをよく吸収した。動物たちのように野山を跳ねまわり、炎や風を自在に操る子供もいた。
それを気味悪がったのは里の人間だ。議員に働きかけて、山の子供に縞柄の服を着せる決まりを作った。神通力を操る化け物がどこにいても、一目で見分けられるように。
「その時から、縞模様が山の子供の目印になったんです。私がちょうど皆さんと同じぐらいの歳のことです」ゆらゆら焚き火に照らされた一人ひとりの顔を見回しながら、島本さんは噛み含めるように言った。当時の里の人々が山の子供を何と呼んでいたのか、丸尾と匠にだけは見当がついた。
高齢だった大天狗はその後しばらくして山の土に還り、子供達も散り散りになった。そして時は流れる。「私たちのことを誰もが忘れてしまった頃に、梔子山に学校ができると聞いてびっくりしました。こんな山奥でまた子供たちに会えるのが本当に嬉しかった。天狗様も草葉の陰で喜んでらっしゃったんでしょう。山の子供の徴をみなさんにプレゼントして、今も守ってくれてるんやと思います」
最後の言葉は、手洗い場のちびた石鹸のように妙に滑らかに響いた。話し終えた島本さんはパイプ椅子に座ったまま深々と一礼する。ゆっくりと顔を上げると、それきりもう何を話すことも聞くこともないというような虚ろな表情で火を見つめた。
小さな焚き火に照らされていくつもの縞模様が回る。跳ねる。笑う。それは山でも街でもなく、子供でも大人でもない僕たちの徴だ。
一本だけ残しておいたテキ屋の花火はその夜もありきたりな火花を吐き散らすだけで、「やっぱり騙された!」と喚く丸尾を指さして匠は笑い転げている。丸尾はこれまでのすべてのことに本気で怒り、そのくせ妙に満ち足りてもいた。煙にかすむ目を擦りながら、匠も同じ気持ちだったらと思う。
もといもと「天狗と山羊と口を閉じて話す言葉たち」
東北に住んでいた頃、天狗伝説のある山の温泉地でカモシカに遭遇したことがある。目と目があっても怯むことなくピン! と立っていたカモシカからは、”ケモノばなれ”したオーラが感じられた。「ひょっとして、あれが……」などと考える余裕があれば(宿で酔っ払って眠らなければ)、私にも「くちなし山の天狗様」みたいな作品が書けたのだろうか。百遍生まれ変わっても無理である。
この物語に登場するのは、足首に天狗の徴をうけた少年たちだ。遠目には縞の靴下のように見える「それ」は、世間から離脱できる自由へのパスポートであると同時に、少年の足首を縛る鎖でもある。獣か人か、はたまた妖か。次元を超えた未来のあわいに(山羊とともに)漂う彼らの迷いは、共感できるようで常人よりもさらに深い。だからこそ、”一度聴こえるようになると、後へは戻れない”という一文が心を抉るのだ。ラストの飛び跳ねるしましまの美しいこと! 言葉のあふれるこちら側には、まだ来ないでと祈りたくなる。
三つのキーワードを使って別の物語を描くという今回の企画はそれ自体がとっても楽しかったが、谷脇さんの作品でも私の拙作の中でも、ヤギというキーワードがトリックスター的な性質を帯びていることに注目したい。くちなし山のヤギを透かせば、私の小説の中で尻が爆発するヤギに重ねることができるかもしれない。それが今回の企画のもう一つの面白さだし、私としては、谷脇さんと飲みに行ったら、ヤギの神秘で盛り上がれるってことがわかって、大変良かった!
谷脇栗太「くちなし山の天狗様」は、オンラインSF誌Kaguya PlanetとSF同人誌『SFG』のコラボ企画としてご執筆いただいた作品です。「ヤギ・野営・落下するしましま」という共通の三つのお題をもとに、谷脇栗太さんともといもとさんにSF短編小説を執筆していただきました。もといさんのSF短編小説は2023年5月に刊行予定の『SFG vol.5』に掲載されます。