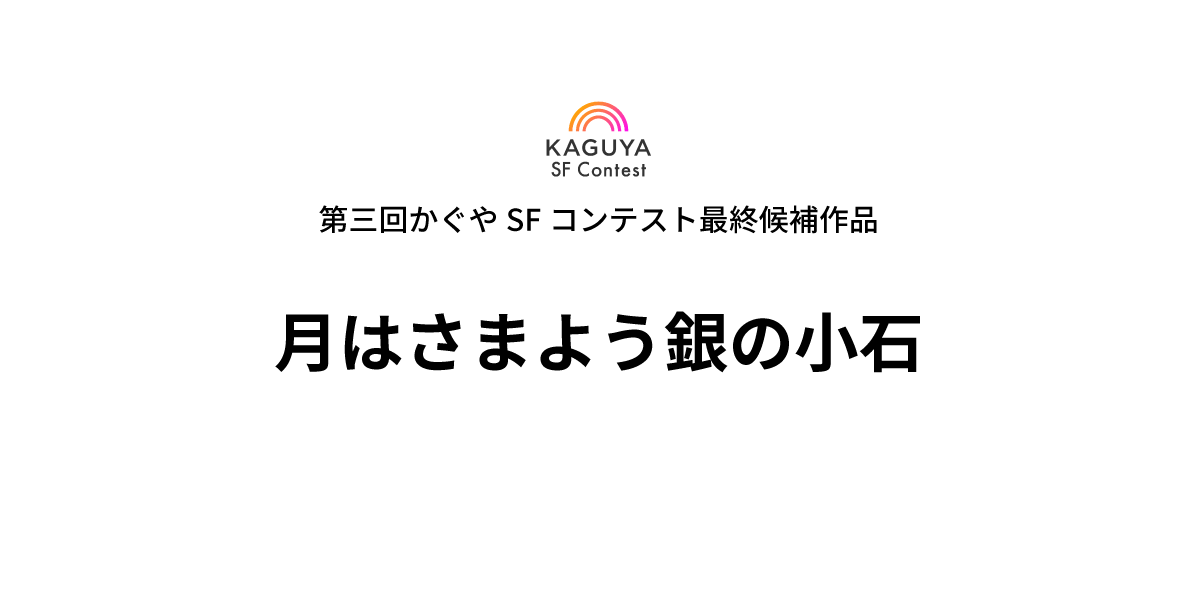第三回かぐやSFコンテスト最終候補作品
関元聡「月はさまよう銀の小石」
父が登板する試合を見に行ったことが、一度だけある。小学校に上がる前、確かオハイオ州のどこかだ。母が運転する薄桃色のハッチバックで丸一日かけて辿り着いたその球場は、平日だというのにほぼ満員で、母と僕はカラメルのかかったポップコーンを持って、初夏の日差しがかかる三塁側スタンドの隅に座った。
「先発よ」と母は言った。「パパがいちばん上手ってこと」
その年の父はまだ勝ち星がなかったけれど、防御率は悪くなかったと思う。でもブルペンから父が出てくると、球場全体が低くざわめき、それから息を潜めるように静まりかえった。たぶんその町の人々は父の姿を見るのが初めてだったのだろう。どこからか、「猿」と呟く声が聞こえた。
その声はさざ波のようにスタンド中に伝播し、僕は急に不安になって、隣に座る母を仰ぎ見た。母の横顔は逆光で陰になっていたけれど、冷たい表情をしていることはすぐに分かった。母は顎を引き、僕の手をぎゅっと握って、いつものように決然とした口調でこう言った。
「パパは猿じゃない。サピエンスが猿じゃないのと同じようにね」
その日の父は好調だった。六回と三分の一を投げ、十個の三振を奪って勝利投手となった。疎らな拍手の中、チームメイトと肩を叩き合うこともなく黙ってブルペンに戻っていった父の背中を、僕は今でもよく覚えている。
〈フランク・ミネダ〉が父の登録名だった。周囲にもそう名乗っていた。姓は母のもので、ファーストネームも母がつけた。この世界で生きていくには表向きの名前が必要で、だからそれは母が父へ贈った最初のプレゼントだったのかもしれない。でも父には本当の名前があった。家族――つまり母と僕にしか教えてはいけないことになっているから、僕がその名を誰かに話すことはないのだけれど。
父はロシア北部、ウラル山脈の麓にある小さな寒村で生まれた。北極圏の近く、針葉樹に覆われた深い森の奥にあるその村の人口は当時ですら百人もいなかったという。
そこは大昔に滅びたと思われていたネアンデルタール人の最後の集落だった。
ユネスコの科学調査団がこの村を発見して以来、村は国連とロシア科学アカデミーが保護区として共同管理している。でもそんなのは建前に過ぎない。その存在が世界に知られてすぐ、村にはよく人買いが現れた。当時の世界情勢は今以上に不安定だったし、父の一族は大抵のサピエンスより強靱な肉体を持っていたからだ。
父が村を出たのは十四才の頃だったという。
その後の父がどこで何をしてきたのか僕は知らない。何度も死にかけ、地を這うように世界中を旅した末に母と出会ったのだそうだ。プロポーズしたのは母からだった。猿と結婚するなんて、と顔をしかめた友人たちと絶縁し、グランマと大喧嘩して、ある寒い朝に母は僕を生んだ。その時父はこう叫んだそうだ。「俺は永遠の命を得た!」そして赤ん坊の僕を胸に抱いたまま、父は蹲るような格好でむせび泣いたという。
僕が歩けるようになるとすぐ、父は僕を森に連れていこうとした。かつて父の父が父にしたように。でも野生動物に出会うには遠出が必要で、ミネダ家の財政には負担が大き過ぎた。その代わり父は市民農園の一角を借りて、そこで様々な作物を育て始めた。トマトとかパプリカとか、そういうのだ。「パスタに入れようね」と母は穏やかに笑った。僕は小さな葉っぱが少しずつ大きくなっていくのが嬉しくて、喜んで畑を手伝った。
市民農園の横には公営のテニスコートがあり、畑には時々テニスボールが転がっていた。ある時父はそれを拾い、僕の顔をじっと見て、それから目を細めて空を見上げた。晴れた空に鳩が二羽飛んでいた。
「右と左、どっちがいい?」と父が尋ねた。何のことか分からず黙っていると、父は左の方が少し太ってるなと言って、いきなり大きく振りかぶった。瞬間、父の上半身がぐわっと盛り上がった。背中と肩と腕の筋肉が滑らかに連動して鞭のようにしなり、父の周りに綺麗な円を描いた。金属を弾くような高い音と同時にボールは青空を真っ直ぐ貫き、やがてぎゃっという悲鳴が聞こえて、灰色の塊が空から落ちるのが見えた。
テニスコート裏の街路樹の傍で鳩は息絶えていた。不思議と可哀想とは思わなかった。獲物の首を握って笑う父の顔はてかてか光っていて、僕は父を見上げ、笑い返した。
父は言った。
「お前にもできるはずだ。お前は俺の息子なんだから」
あの頃、僕はまだ世界というものを信じていた。だから地元球団のセレクションを受け、縦縞のユニフォームに袖を通した父を見た時、僕はただ誇らしい気持ちで一杯だった。
母はいつも言っていた。最終氷期があと千年長く続いていたら、今ここにいるのは彼らだったのかもしれないのよ。
母は人類学者だったから、その言葉はきっと正しい。ホモ・ネアンデルターレンシスはサピエンスの先祖ではなく、同じ先祖から枝分かれした兄弟ともいうべき存在なのだ。知性にも文化にも優劣はない。ただ地球史的な偶然だけが二つの種の命運を分けたのだ。
父は流暢に英語を話し、マナーに従って食事をし、音楽を奏で、そして野球を愛した。父にとって僕に野球を教えることは人生で最も大事なことらしく、試合のない日に僕たちはよく裏庭でキャッチボールをした。メジャーの公式球は僕にはまだ大き過ぎたけど、父は頑なに使い続けた。
父が投げるボールはどんな遠くからでも僕のミットの中心に狂いもなく収まった。まるで魔法のようだった。投げるとはどういうことか、肉体をどう使えば、より速く、より遠くへ、より正確に投げられるのか。父の教えるそれは近代野球における投球術とは全く異なっていたけれど、僕らにとっては自然だった。それは数万年もの間、絶えることなく父から子へと伝え継がれた、酷寒の森で生きるための技術そのものだった。
父の家系は代々〈投げ技〉の名手だったという。ある晩、夜空を見上げながら父は僕に言った。
見ろ、あそこに浮かんでいる丸い月を。あれは遠い昔に父祖の誰かが空に向かって投げた小石だ。それが未だに落ちることなく天を巡っているのだ。
僕はもうそんなお伽噺を信じる年ではなかったけれど、父の太い腕を見ていると、本当にそんなことがあったと信じられる気がした。
時は流れ、世界は変わる。いつしか級友たちは手足がすらりと伸びて、細めのジーンズを履きこなしている。それに気づいたのはいつだっただろう。同じものをバーチャルで試着し、結局買わずに諦めたのはいつだっただろう。
野球選手になりたかった訳じゃない。なのに、僕の体は思春期の始め頃には成長が止まり、代わりに肩や胸の筋肉が発達して、だんだんドワーフみたいな体形に変わっていった。眉上の骨がぐっと突き出し、眼窩が深い渓谷のように落ち窪んだ顔だちは、前髪を伸ばしても隠すことはできなかった。それは紛れもなく父の顔だ。アメリカで生まれ、サピエンスとして育ったけれど、僕には父と同じ血が流れているのだ。いつかのスタジアムでの記憶が蘇る。僕は猿じゃない。そんなことは分かっていた。
くすくすと笑う声が聞こえ、振り向くと、ずっと同じクラスだった幼馴染みがこっちを見て笑っていた。女の子たちが目を逸らした。急に息が苦しくなり、自分が恥ずかしく思えて、今すぐそこから逃げ出したかった。その日から部屋を出られなくなった。グランマがやってきて、父に何か言い、その時初めて父が声を荒らげるのを聞いた。
卒業式の朝、母は僕を強く抱きしめ、それからシカゴの大きな病院に連れていって、麻酔から目覚めた時には僕はもう自分ではない誰かに変わっていた。それを見た母は大粒の涙を流した。「ごめんね」とグランマが言った。僕は悔しいような、ほっとしたような気持ちで、ただ父に何と言えばいいか分からず、けれど家に帰るともうどこにも父の姿は見えなかった。
父が現役を引退したことはその夜のニュースで知った。
長いこと父とキャッチボールをしていなかったことに、その時、僕は気づいた。
そして薄桃色のハッチバックは同じ色のエアカーになり、母の相手も何度か変わって、僕は今、生まれ育ったこの町にいる。
暖かい夜だ。
薄灯りがともる部屋で母が安楽椅子に腰掛けている。僕は全身にパワーアシストを装着し、月のない裏庭に立っている。手にはメジャー公式球。昨日、息子がここで見つけたものだ。きっとあの頃失くしたものだろう。でも縫い目のあたりが黒く焦げていて、もしかしたら本当に宇宙から落ちてきたのかもしれないと僕は夢想する。
僕らは離れ離れになったけど、父の行方は世界中の誰もが知っていた。
テラフォーミングが進む火星への植民計画が本格化し、地球よりずっと寒いその惑星の開拓のために選ばれたのは父たちネアンデルタールの人々だった。ミッションの特性上、第一次火星植民団のメンバーは二度と地球に戻ることはない。父は僕や母を恨んだのか、それとも滅びゆく種族の最後の誇りなのか。父の真意を、僕はまだ測り切れずにいる。
そろそろ火星が南中する頃だ。
僕は背筋を伸ばし、赤い星に正対する。風が止み、ボールを握り直す。深呼吸を一つ。変則型ワインドアップモーション。片足を高々と上げ、そのまま上半身をぐっと捻る。パワーアシストが甲高いモーター音を響かせて、ギアにエネルギーをため込んでいく。
お前ならできる――と声がする。お前は、俺の息子なんだから。
ウラルの蒼い森を想う。赤茶けた砂の荒野を想う。七千万キロ先の父が僕の本当の名前を呼ぶ。このボールが父に届くかは分からない。届かなくてもいいと思う。どこにも届くことなく天を彷徨い、いつか誰かが見つけてくれればいいと思う。
大地を割らんばかりに足を踏みしめ、反対の足で蹴り飛ばす。空気を切り裂く音とともに弾けるように体が回転し、虚空に一瞬の真円を描く。
あの時と同じ軌道で白球が風を切り、真っ暗な宇宙へ吸い込まれていく。