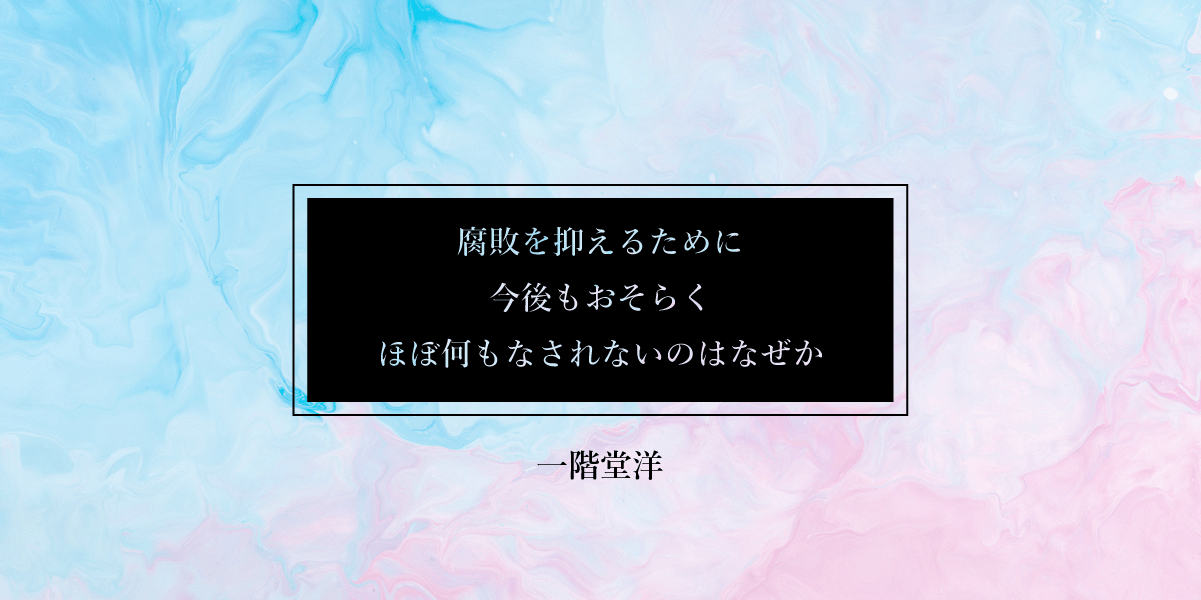先行公開日:2022.3.26 一般公開日:2022.4.30
一階堂洋「腐敗を抑えるために今後もおそらくほぼ何もなされないのはなぜか」
9,412字
北山にたなびく雲の青雲の星離れ行く月を離れて
万葉集
お父さんを冷やそうと思う、とふかふかの姉が言った。私は軽トラをコンビニに停めた。助手席に置かれているクリーム色のクッションを拾い上げる。これが姉だ。民家の屋根が夕日を反射した。
「冷やすって?」
「冷やすんだよ。体温を下げる。お父さんの体に休んでもらう。医学の進歩を待つ。エニー・クエスチョン?」
私は柔らかい姉をなでた。中にはスマートフォンと大量のバッテリーが入っている。イエロー大学だかブラウン大学だかにいる姉と繋がっている。彼女が笑えばこのクッションもそれらしく光る。制作者たる姉に言わせれば、この説明は間違っている。姉が笑ったと私が思い込むように、このクッションの発光パターンが定められている。姉は私の想像の中で笑う。
「それは誰がやろうって言ったわけ」
「お父さん」
少し待った。私はコンビニから車を出した。お父さん、前立腺だっけ? と聞いた。そう、とクッションが答えた。あんたも一度、前立腺の大きさと年齢のグラフって見たほうがいいよ、本当に面白いから。すぐに信号につかまる。日陰から街灯がつき始める。昨日よりもわずかに遅く夜が始まる。唐揚げ屋の角を曲がって、大学の構内に入る。姉は相変わらず病気の話をしている。
「姉さん、そろそろ黙らないと頭にアルミホイルを巻いてやるから」
姉は明るくなって笑った。残念、私はヘッドレスで動いてるんだ。
痩せた大学院生に発泡スチロールのケースと領収書を渡す。どうもとかいつもありがとうございますとか、そういう言葉が、せっけんのかすみたいにぼそぼそと語られた。今日も十二時すぎまで実験をするのだろう。彼は体を震わせた。確かに、ここはかなり寒かった。彼の足元に落ち葉が何枚か吹き溜まった。彼の靴がそれを踏み潰した。砕けた枯れ葉がアスファルトの溝を埋める。
「あの、年末って、その、何日までやってますか? マシンタイムが年末はあくので、できれば試料をお願いしたくて……」
客観的に言えば、彼は銭湯にでも入ってゆっくりすべきだった。誰かが彼を思いっきり抱きしめてやって、何も心配しなくていい、君の博論を読む人間は向こう百年で五人もいない、だから根を詰める必要はない、そう言って人体のぬくもりを思い出させてやったほうがよかった。しかし、そんなことをするやつは誰もいない。
「三島と本郷なら、三十日まではできます。でも、三十日は道路が混むので、いつもよりは時間がかかりますね」
彼はスマートフォンに目を落とした。必要ならお願いします、と言って帰っていった。少し待ってから、私も踵を返した。もう何棟か回る必要があった。どこにも同じような顔をした大学院生がいた。彼らは単に摩耗していた。ただ、いくら追い詰められ、私のようなコネで仕事にありつく運送屋に頭を下げるようになっても、彼らには情熱と目的があった。手の甲を突き刺して、なんとかこの世界に引っかかっていられるフックを見つけていた。いくら血が流れようと、そこには――そういってよければ――とりあえずの安心があった。
それで、と軽トラを転がしながら姉に聞いた。私はだんだん、状況がつかめてきていた。お父さん、そんなに具合が悪いんだっけ? まあね。若いがんは早いんだよ。病院はどこでやるの? 山梨に一件受け持ってくれるところがあって、地元だしさ。国道四号線はいつもより空いていた。誰もが信号機の定めに従っている。とにかく従っていれば目的地までつくことができた。私がやることって何? 一番近い親類だしさ、ちょっと書類書きに行って。息子にもセイハローしてよ。お金は大丈夫なの? 大丈夫。私は屋根付きの駐車場に車を停めた。すっかり日が暮れていた。空のずっと奥で飛行機がまたたく。空腹を感じなかった。足の小指がしびれたように冷たい。
「あのさ、姉さん」
姉が首をかしげるように光る。本当はどこからお金が出てるの? 姉は短く、実はAMEDから出てる、と言った。リスでもマウスでもブタでもサルでも成功してる実験。ちゃんと意識がはっきりしているときに同意をとってる。倫理審査も通ってる。何も問題ない、と続けた。私はクッションを持ち上げた。人のような暖かさがあった。車を出て狭いアパートまで歩く。部屋には朝の空気がこもっている。冷蔵庫が羽音を立てている。それがやけに大きく感じる。お父さんが生きる意味がわからない、と私はつぶやいた。
ベッドに腰掛ける。ダクダクゴーで『医療費問題』と検索する。インターネットのよいところは自分自身をいくらでも洗脳できるところだ。もう一度、私は姉に話しかけた。どうしてお父さんが生きながらえるべきなのか、私にはわからない。
それで私は本当にわからなくなる。
甲府までは二時間と少しでつく。県立病院の駐車場は空いていた。受付に行ったあと、何棟かたらい回しにされた。すいません、と若い事務員が言った。小児病棟を減らして、緩和ケアを増やしてるんですよ。それのせいで、混乱が……。そうでしょうね、と私は答えた。頭上のレールを、荷物が音もなく動いていった。
九階まで上がると、スクラブを着た若い男が事務的な手続きをした。革張りのソファの上に、名前の知らない日本人の描いた絵が飾ってあった。三人の老婆が糸を紡いでいる絵だった。ご親族の方ですね。隣の面会室で待っていてください。そして看護師はほほえみを浮かべた。面会室、そこのソファよりもずっと暖かいですから。私は彼に好意を持った。彼は小児科か産婦人科に転科したほうがよいと思った。少なくとも、この青年に死を見せ続けるのは犯罪に近いとすら思った。自分の触れるもの全てが――それがどんな因果に基づいているにせよ――死にゆく世界で、正気を保っていられる可能性は薄い。ご家族の方も来ているようですよ、と彼は言った。もう夕方だった。
面会室に入る。濃紺のブレザーを着た子供が座っている。スカートのプリーツが薄くなっている。これが姉の息子だ。彼は――便宜的にこう言うことにする――私を見た。そして目を逸らした。私は彼から少し離れたところに座った。会うのはいつぶりだろうか? 彼が人語を理解する前に会ったきりだったはずだ。机には細い花瓶が置いてあり、枯れかけた青い小さな花がさされていた。彼はリップクリームを唇に塗った。そこには儀式的なところがあった。そして言う。
「久しぶり」
かすれた声だ。私も同じような言葉を返した。この部屋には窓がなかった。ダイキンのエアコンが頭上で深い溜め息をついた。数秒の間があいた。彼は「あの人はもう別の部屋に入ったみたいだよ」と言葉を切った。そう、と私は答えた。最後に父と会ってからも、長い時間が経っていた。仲は悪くなかったはずだった。特筆するべきことが何も起きていないというだけで。これは私の墓碑銘に使えた。特筆するべきことが何も起きていない。
医者が二人、入ってくる。一人は三人の娘がいるようなタイプの白髪の医者だった。若い方の医者は、夏はテニス、冬はスノーボードで遊んできたような印象を受けた。彼らは、少し迷ってから、私の前に座った。
今日は誰も訪問に来ない予定ですし、あなた達に無用なプレッシャーを与えたくないんです、これは本当に重要ですから、と老医は小声で言った。紙を何枚か広げた。それに、このフロアは待合室が一番暖かいんです。誰もが寒さから逃げようとしている。
この技術で、がんの進行を極めて遅らせることができます。私達は斧を研ぐ時間をもてるようになるんです。若い医者は要点を押さえた説明をした。機械翻訳された参考論文のプリントまで手渡してくれた。ダドル、人工心肺、リポ蛋白。人体冷却による無期限の延命とは、と彼は話を総括した。私達が賢くなり続ける限り、不死の技術を含意します。彼の意見は確かに説得的だった。ストリングが感動的な背景音楽を流している気配すらあった。老医がクリップをいくつか渡してくれた。私は書類をまとめた。
「少し、読ませてください……もちろん、父の意見は尊重しますから……」
もちろんです、しかし、と若い医者は言った。合板の張られた机を指でトントンと叩いた。お父さんの容態はあまりよろしくありません。意識障害が出ています。明日には開始するのが望ましいです。命は待ってくれませんから。そして、彼は場違いな笑みを浮かべた。
「今のところ、まだ」
彼は席を立った。帰属が何個か書いてある名刺を渡してくれた。太田という名前だった。彼が出ていくと、老医も資料をまとめた。親指の付け根にやけどのような跡があった。指の毛まで白くなっていた。お初にお目にかかりましたね、と穏やかな声で言った。ええ、と私は答えた。
「ゲノム研究をしていたところが空いて、そこにベッドを運び込んでいます。器具は太田が搬入済みです」
少し間があった。「片付けたほうがいいということですよね、その、今の病室を」と訊いた。老医は、ええ、と答えた。すいませんが、お願いします。彼が部屋を出ていくと、姉の息子はスクールバッグを背負った。車で来てる? と尋ねた。私は頷く。
「あたしはあたしの荷物だけ回収してるから。家に泊まってもいいけど、晩ごはんはないから」
そういうと、靴下をぎゅっと引っ張り上げて、待合室を出ていった。私はナースステーションに寄った。さっき会ったのと同じ男に、父の病室を教えてもらう。奥のブースで「最近なにかしてる? いいケツになってない?」「あ? 分かります? 筋トレ始めたんですよ、ジム」と雑談が交わされていた。すみません、と彼が苦笑する。みっともない職場で……。私はほほえみを返す。彼女たちにはもっとしかるべき環境と職があるべきだった。少なくとも、緩和ケア病棟で鍛えた尻が役に立つことは考えられなかった。カウンターでトラの首ふり人形が揺れている。台座には睡眠導入剤の名前が書いてある。
父の病室は四人部屋だった。病室に特有の、調整された匂いがした。二つのベッドは間仕切りのカーテンの向こうに隠されている。父のベッドの向かいに寝ている老人が、私の方を見る。それからまたテレビに向き直る。手の甲に刺さった点滴から何が流れ込んでいるのか、私にはわからなかった。彼はなんとか生命をつなぎとめていた。
父のいたベッドには一つのしみもなかった。冷蔵庫にはみかんゼリーが二つ入っていた。ベッドサイドの小さなスツールに腰掛ける。窓からは町並みがよく見えた。たくさんの家族がいて、どの家も火を灯し始めていた。やがて森が始まり、そして山に溶け込んでいく。千代田湖の向こう、昇仙峡の遠く、釜無川が山脈への案内人に代わる。鋸歯が暗い青に食い込んでいる。私はその歯の名前を知っている。誰に教えてもらったのかは思い出せない。
看護師が来て、ああ、すみません、何かお困りごとはありますかと言った。いえ、と答えた。彼女はゴミ箱の中身をあけて、シーツを剥いだ。テレビを見ていた老人がうめく。彼女はちらりとそちらの方を見て、口角を少し上げた。それで老人は安心したみたいだった。私は彼女を好きになりかけた。全てが無意味にも思えた。彼女は笑顔を使うべきではなかった。私は彼女の首筋を見て、耳たぶを見て、それから手首を見た。どこにも何の痕も見つけられなかった。彼女に趣味はあるのだろうか? 黄色い花の香水を首筋に振ったり、ガラス玉の埋め込まれた金のイヤリングを付けたり、恋人の背中に爪を立てたりすることはあるのだろうか?
彼女は私に紙袋を手渡した。下着とか冷蔵庫の中のものとか、捨てちゃいますから。一応、全部持って帰ってください。私は従った。ごわごわしたタオルを詰める。これで父親の体が拭かれたのだろう。死を延期するためですらなく、引き伸ばされた死をできるだけ耐えられるようにするために。
「こっちにいらっしゃってからも、お孫さんはよく来てましたよ」
彼女を見た。
「すいません、ご迷惑をおかけすることが……」
微妙な間があった。彼女は「そんなことありませんよ」と会話を引き取った。ドアの方を振り返った。そして言う。心のケアは医療がいちばん苦手なことですし。言い争うつもりはなかった。父親の置いていった荷物の上に、私はゼリーを置いた。数枚の肌着とみかんゼリー。生き延びることで父親が所持し続けられるものがこれらだと思うと、気が狂いそうになった。私は立ち上がった。それに、と看護師は私に話しかけた。
「息子さんのおかげで、私は花の名前を七種類覚えました」
しかし、青くて小さい花の名前はどんな魔法の言葉にもならない。
軽トラに乗り込んだ。車内灯のスイッチを入れた。オレンジ色の光が書類に落ちる。若い医者にもらった資料は、専門用語が多すぎて、私にはほとんど理解できなかった。姉が接続に復帰して、「学歴を貸そうか」とくだらないことを言った。
「子供の育て方は専門分野外なんだろうね、姉さんは」
「だから専門家に一任したんだよ。少子化をどうかしたいなら勝手に育てりゃいい。私は産んだ。離婚したから一人産めばノルマは達成」
完全になめてる、と思いながら、「もし、子供に恨まれてたとしたら、とか考えない?」と訊いた。腸管細胞のターンオーバー期間を延長することは、腸内細菌叢によって腸が被るダメージとの釣り合いの下で考えなければならない、と論文は述べている。腸内細菌叢の代謝を温度によってコントロールすることの困難性、腸の完全滅菌が抱える技術的な課題、そして腸内細菌によって提供される希少な生成物を考慮に入れると、この問題の解決のためには新しい技術が必要になるだろう……。
「もう恨まれてるでしょ。だから『もし』とかは考えない。今、何の論文を読んでるの?」
「大腸の細胞がどうのとか、微生物がどうのとか」
ふかふか姉の腹がくるくると光った。もちろん、このクッションが腹に相当する部位を持つとしての話だ。つまんないよね、と姉は言う。
「体はどうでもいいんだよ。体は容器じゃん。筋肉が衰えるのが問題だから四肢を取り除きます、将来の義肢技術に期待します、そう言った口で、腸内フローラによる人体の腐敗は避けることができないっていうんだから、アホなんじゃないかと思う。要するにさ、論文を書きたいだけなんだよ。次の問題は何? 次は? 予算が取れるか? 本当に誰かを生かしたいとは思ってない」
姉の気をそらすために、年金が、と私はやけに実際的なことを尋ねる。お父さんに浪費されるんだろうね。浪費されてはいけないお金というものはないよ、と姉は反論する。それに、これはあんたにとっても不利な話じゃない。年金と補助金から維持費を除いてもちょっと余るんだから。
車内灯を消して、車を出す。あの人はこれを受け取る根拠があるんだよ、とクリーム色のクッションが光る。お父さんは薄給で頑張ってきた。湿布屋とかなんとか馬鹿にされてもきちんと医者をやってたと思うよ。歩道には誰もいない。皆が車の中に閉じこもって動いている。帰る場所に帰っている。ウィンカーがそれぞれのタイミングで光って、一斉に瞬いてはまたばらばらに戻っていく。月が雲の中を流れていく。結局、お父さんってなんで延命治療を望んでいるの?
「記憶がちょっとでも残っていればいいんだって」
「なんて?」
プリウスが音もなく急に割り込んでくる。危うくぶつかりそうになる。ハンドルの合成樹脂に爪を立てる。
「外が寒くなったらプールサイドの灼けたコンクリートのことを、暑くなったら水を吸った雪を踏み潰すことを思い出せるわけだよ。いろんなことを。お父さんはそういう記憶をもう六十年以上も集めてきた。頭の中で一年に二秒でもその記憶が発火する限り、お父さんは生きていたいんだと思うよ。冷却処理がいくらつらかろうと、記憶はまだまだたっぷりある」
「楽しいことが一つあったからって、つらいことが一つ消えるわけじゃない……」
その通り、とふわふわの姉はうれしそうに振動した。つらいことが一つあったからって、楽しいことが一つ消えるわけじゃない。ジャズでも流してあげようか。私は答えない。車の中はとても寒い。私はコンビニに寄って夕食を買った。
実家は昔と変わらなかった。とても小さい庭があって、狭い階段が二階に続いている。どこも綺麗に片付いていた。洗面所には細い椅子とディオールの化粧道具が置いてあった。子供が持つには早すぎるブランドだった。
私は弁当を温めずに食べた。息子は鍋でなにかのお茶を沸かしていた。壁には何枚かの写真が貼られている。フィルムカメラを芸術作品の作成以外に使えた最後の時代に撮られたものだ。若い頃の私が、ブロック塀の前に立ち、カメラに向かって眩しそうな顔を向けている。棒アイスを食べている。父親が持っていた銀色のカメラのことを思い出した。それのフラッシュが跳ね上がるときの、神聖な宝物を入れた小さな箱を開けるときのような音を覚えていた。ダイアルには色々なマークが書いてあって、父が見ていないすきにぐるぐる回して遊んでいた。安物のレリーズも父は持っていた。小学生の時、それを使って、夏休みの自由研究用に夜空を何十枚か撮った。薬の名前の書いてあるボールペンで、父が写真に写る黒い影をなぞる。これが八ヶ岳。そして彼はその山頂の名前を一つ一つつぶやく。私はそれを覚えている。姉の言葉のうち、正しいことが少なくとも一つある。私たちは色々なことを思い出せる。
「あたしはもう寝るから。布団は二階。お風呂に入るならバスタオルは勝手に使っていいよ」
水筒を持って彼が部屋を出る。いい看護師さんが看てくれたんだ、と私はつぶやいた。彼は私のことを見つめた。遠くで犬が鳴いた。犬は鳴くものだ。そうかな、と彼は返した。そして顔を背けた。
風呂には手すりが増設されていた。男の汗と塩素の臭いがした。電話が風呂場の外で鳴る。私はシャワーを止める。裸のまま通話をつなぐ。大学院生の声がする。明日の朝までに三島からサンプルを持ってきていただけますか? いい結晶ができているらしくて、どうしても年をまたいでデータを出したくないんです。分子の世界にも、年末という概念はあるのだろう。
「少し難しいです」
「三十日までは大丈夫って言ってたじゃないですか」
そうですね、と私は自分の非を認める。髪の毛から冷たくなった水が落ちる。浴室の床を伝っていく。
「でも、私にも用事があって……別の人を紹介したことがありましたよね、あの人はたぶん――」
彼は私の話を遮った。あなたがいいんです。そこにはどこか異様な響きがあった。あなたが持ってくるといいデータが取れるんです。短い沈黙。「きっと振動吸収バンパーにいいのを使っているからでしょう」と彼は続けた。いいですか、と私は彼に話した。曇った鏡を手のひらでぬぐった。私の顔が映って、またすぐ膜のような水滴の向こうに消えた。私はあなたのために生きているんじゃないんですよ。
彼は何も言い返さなかった。私は電話を切る。
数ページに渡る同意書の最後を見る。ボールペンで自分の名前を書く。これで父親はほとんど際限なく生き延びることができるようになった。四週間に一回だけ、体温が平熱まで上げられる。四時間半、本当の眠りに落ちる。それから意識が戻る。生存延長の確認が取られて、また冷たい低代謝の世界に滑り戻っていく。彼はそれを受けるに値する。その通り。
質素な朝食を摂って、私達は車に乗った。仕事の? と彼が訊いた。私は頷く。車が私達を病院に運んだ。
入ってすぐのソファに医者が座っていた。彼は正確に挨拶の言葉を述べた。私達は口々にどうもとか待たせてすいませんとか、そういうことを言った。彼は一番最後のページを見て、私の名前がしっかりと複写されているかを確かめた。「ありがとうございます」と彼は言った。
微妙な沈黙が広がる。さらさらした床をスニーカーで擦る。お疲れさまでしたと医者が続けた。明らかに、彼は私達が踵を返すのを待っていた。それを断る理由はどこにもなかった。「すいません」と少年が声をかけた。声は震えても濡れてもいなかった。
「見てもいいですか、その、祖父を」
いいですよ、と太田は言って、彼の体をつま先からつむじまで見た。そしてもう一度、まあ、いいですよ、と言った。スマホとかはやめてくださいね。じゃあ行きましょう。親御さんはどうしますか? 私は断った。そこには計画済みというような空気があった。
私はソファの前にある移動式の書棚を眺めて待つことにした。側板に『移動図書館』と書いた紙が貼ってあった。日本の作家に混ざって、チャールズ・ブコウスキーの文庫が置かれていた。小口が削られていた。昨日、病室で会った看護師が話しかけてきた。それ、私が選んだんですよ。図書室は遠いし、風邪でもひいたら大変ですから。そうですよね、と私はできるだけ曖昧にこたえた。
「太田ですか? お呼びしましょうか」
いえ、大丈夫です、と言って私は本を戻した。しばらくの間、どうでもいい雑談を彼女とした。仕事はきついでしょうと訊くと、あっさり「そうですね」と答えた。まあ、学生の時、実習の後に深夜までレポートを書いてた頃に比べたらマシです。きっと、慣れというのもあるんでしょうけど。人は何事にも慣れるわけですね、と私は言い添えた。本当にそうだといいなと思った。向こうからローファーの音が聞こえる。お子さん、元気に過ごせるといいですね、と看護師が言った。
息子は何も言わずに私の横を通り過ぎて、入り口のドアを抜けた。私は後を追う。エレベーターのボタンを押してやる。下向き矢印の感覚が指にはっきりと残る。彼は特に動揺していないように見えた。目を伏せている。彼はスマートフォンを取り出して、時間を見た。彼は何か言ったが、うまく聞き取れなかった。
エレベーターのかごが予想以上に早く迎えに来た。私は一階のボタンを押した。私達を吊っている紐が切れるところを想像した。その紐がいかに太かろうと、これまでそれが一度も起きたことがなかろうとも、とにかくそういうことは起こりえた。クイズ・今日は何の日か知っていますか? とエレベーターの液晶に表示されていた。今日は何の日なのだろう?
風呂に入れてやってたんだ、と彼がささやいた。そろそろあたし一人でもできるようになるはずだった。彼はそれから私の顔を見た。彼の体温と匂いを感じられた。ブラウスの襟の部分が少し黄色くなっていた。エレベーターが少しずつ遅くなっていく。目的地に近づいている。私のほうが先に目を逸らした。小さなチャイムが鳴る。そしてドアが開いた。もうしなくてもいいよ、と私はつぶやいた。
私達は病院の外に出た。彼に「送っていこうか」と持ちかけた。どこに? と彼は返した。私は何も言えなかった。空は白く曇っていて、影がどこにもできなかった。冬の静かな雨の予感がした。彼は駅の方に一人で歩いていった。私は駐車場から車を出した。甲府昭和インターチェンジから帰るのが一番いいとカーナビが言った。私はそれに従うことにした。
相模湖のパーキングエリアで軽トラを停めた。姉は何も言わなくなっていた。名前のない鳥たちが遠くで食料をついばんでいた。どっかのバカがクラクションをずっと鳴らしていた。あたりがどんどん寒くなってきている。私をここに引き止めるものが何もなかった。