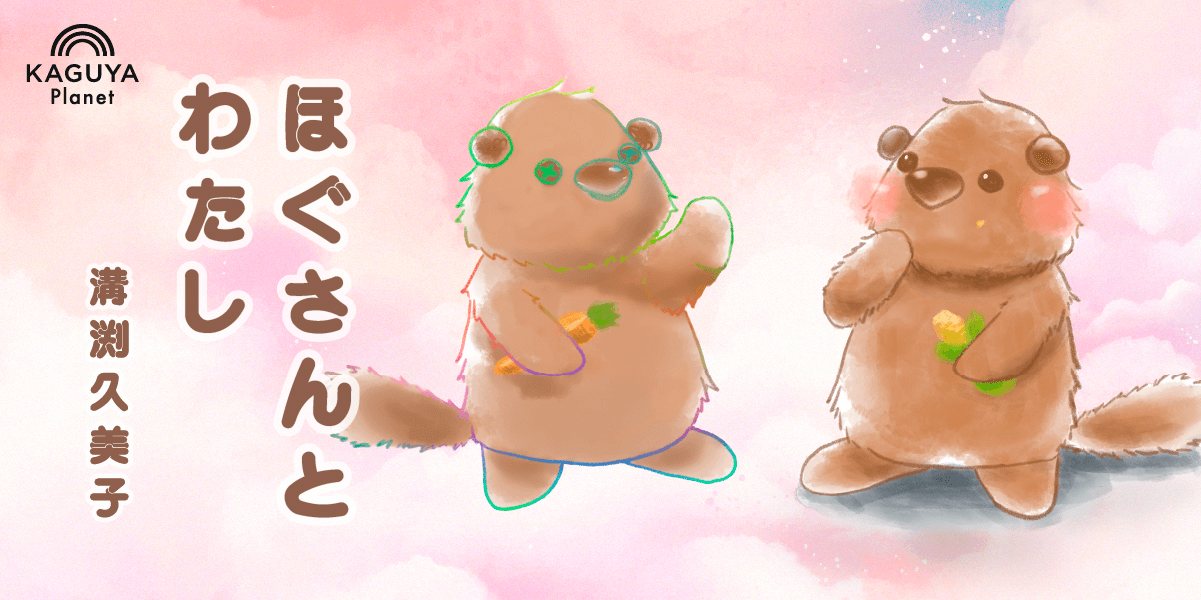先行公開日:2023.1.28 一般公開日:2023.3.4
溝渕久美子「ほぐさんとわたし」
6,757字
ぬいぐるみのほぐさんとわたしと、わたしたちに起こったできごとについて少し書こうと思う。ぬいぐるみと暮らしている人にとって何かの役に立つかもしれないし、役に立たないかもしれない。そんな話だ。
わたしがほぐさんと出会ったのは、今から15年ほど前――アメリカ・ペンシルバニア州にあるピッツバーグ大学に語学留学中のことだ。
平日は大学から徒歩5分ほどの場所にある古めかしい学生寮から語学学校に通い、休日には当時スクワーレルヒルズ地区にあったバーンズ&ノーブルに出かけた。この書店では書籍に加え、音楽メディアや文房具、玩具も扱っていて、店の片隅にはぬいぐるみのコーナーもあった。パステルカラーのユニコーンや、妙に肉感的な猫に混じって、陳列棚の片隅に15センチくらいの大きさの、茶色いぬいぐるみが5体ほど並んでいた。ずんぐりした体型で、クマのようにもリスのようにも見えたけれど、何の生き物を模したものなのかさっぱりわからなかった。ささやかな丸い耳や黒いプラスチック製の小さな目がなんとも素朴な風貌だった。思わず手に取ったものの、値札を見ると日本円に換算して1000円少ししたので、そのまま棚に戻した。
通学をはじめて少しした1月の第3週の火曜日の課題でGroundhog Dayなるものについて調べる課題が出た。他の課題や予習もあったので、さっさとすませようと思ってWikipediaを見てみた。
Groundhog Day――グラウンドホグデーとは、ペンシルバニア州のパンクサトーニーという町で毎年2月2日に行われる行事のことだ。ウッドチャックとも呼ばれる、プレーリードッグの親戚筋にあたる齧歯類の生き物・グラウンドホグは秋の終わりごろから冬眠に入る。伝承によると、グラウンドホグは2月2日に冬眠から目ざめて巣穴から姿を見せ、その際、自分の影を見て怯えれば巣に戻り、影を見ることがなければ再び地上での生活を始めるという。それを人間たちは「あと6週間冬が続く」もしくは「もう春だ」という〈予言〉に読みかえるのだ。
パンクサトーニーでは2月2日の明け方から町を挙げたイベントが開かれる。地元のクラブが〈フィル〉という名前のグラウンドホグの〈予言〉を聞き、人々はその結果に一喜一憂する。日本では『恋はデジャヴ』というタイトルがつけられたタイムループもの映画の名作Groundhog Dayは、この行事を題材にした物語だ。
課題の調べものをしながら愛嬌あるグラウンドホグの画像を何枚も目にしていくうちに、わたしはこの生き物をすっかり気に入ってしまった。バーンズ&ノーブルで売っていたぬいぐるみがグラウンドホグであることにも気づき、すぐにスクワーレルヒルズへ向かってあの小さな茶色い子を一体お迎えした。名前は迷わず〈ほぐ〉にした。
ほぐさんはうちに来た翌日にはもう話し始めた。最初はNHKで放送していた『できるかな』のゴン太くんのような声を上げていたのだけれど、すぐにしっかりとした日本語を使うようになった。わたしがネットで日本のコンテンツを見ているのをそばで眺めているうちに憶えたらしい。製造から販売までの過程で身につけた英語も話せたようだけれど、わたしのことを考えて日本語で話してくれた。そのうちに、ほぐさんの好物がニンジンやトウモロコシだということや、おなかを触るときは一言断ってほしいと思っていること、子供扱いをされると怒るということがわかってきた。
語学学校でアジア圏出身の友人はできたものの、アメリカでの暮らしが心細かったわたしにとって、ほぐさんは大切な相棒になった。わたしはほぐさんをリュックサックやトートバッグに入れて外出をした。学校にも連れて行ったし、お茶や食事をするときも一緒だった。
当時、わたしは勉強や読書をするためにピッツバーグ大学と寮との間に位置するキバハン・カフェをよく使っていた。フォーブスアベニューとサウスクレイグストリートの交差点の角にあったこの店は、向かいのスターバックスのようなチェーン店ではなく、どこか文化的な雰囲気の小ぢんまりとしたカフェで、値段も比較的安かった。
2月の終わりごろ、いつものようにわたしはほぐさんとキバハンに入った。ホットコーヒーとハムサンドを買ってロフト席に上がり、ときたまほぐさんに声をかけながら食事をした。食後に本を読んでいると、誰かに日本語で声をかけられた。
「すみません、あなたは日本人ですか?」
顔を上げると、アニメ『カウボーイビバップ』のTシャツを着て丸眼鏡をかけた若い白人男性が、店のロゴが入ったマグカップを片手に立っていた。綿あめのようなカーリーヘアが胸にプリントされたスパイク・スピーゲルとダブった。
「はい」
「あなたと少し話したいです」
この人はたぶん日本のポピュラーカルチャー好きが高じて日本語を学んでいて、語学力を鍛えるために日本語で会話をしたいのだろう。外国で旅行をしたり生活をしたりしていると、わりとよくある話だ。わたしはそんなことを考え、本を置いて「どうぞ」と向かいの席を手で示した。ほぐさんを片付けようとすると、その若い男は――けっきょくわたしはこの人の名前を聞きそびれてしまったので、仮にスパイクとしておく――「そのままで」とこちらを制した。
スパイクは椅子に腰を下ろし、ここからは英語で話してもいいかとわたしに訊ねた。日本語は高校生の頃から勉強していて日常会話は問題ないけれど、少しこみいった話になるからと。わたしは頷いた。
すると、彼は膝に乗せていたリュックサックからいきなりぬいぐるみを取り出した。ほぐさんの倍ほどの大きさの、クリーム色のボア生地のクマだった。
「これは僕のパットです。5歳の誕生日に母が買ってくれました。母はひとりで僕を育てなければならなかったので、仕事でいっしょにいられない間、僕が寂しくないようにって。もう20年ほどのつきあいになります」
パットは中の綿がすっかりへたって平たくなっていた。右腕と左耳とマズルそれぞれのつけ根に修繕のあとがあった。もともとは真っ白だったんじゃないかと思う。
「僕はこのぬいぐるみと話せます。あなたもそうでしょう?」
予想外の展開にわたしが言葉を失っていると、スパイクは「さっきその子に話しかけてたじゃないですか。あそこで見てました」と、テーブルの上のほぐさんと近くの席に目をやった。
「もちろん、ぬいぐるみは話しません。ただのオブジェクトですから。すべて僕たちのイマジネーションです。僕は子供の頃から人づきあいが苦手だったけれど、パットには何でも話すことができた。パットがどんな子か細かく設定を作って、僕たちは想像の世界に遊んだ。でも、それがたいへんな事態を生んでいるのです。僕は僕と同じような人を見つけるたびに、それを伝えています」
スパイクはマグカップを口に運んで、ピッツバーグ大学のすぐ隣にある演劇やコンピューターサイエンスで有名な大学の名を告げた。
「僕はそこで物理学、その中でも宇宙論を専攻しています」
「そのことがぬいぐるみと何の関係があるのですか?」
「あります。ここからは宇宙論の話になります」
スパイクはパットを膝の上で抱えなおして、一度撫でた。
「パラレルユニバース——日本語では何と呼びますか?」
「ええと、〈並行世界〉とか〈並行宇宙〉とかかな?」
スパイクは自分の脳に刻みつけるように日本語で「並行世界、並行宇宙」と三度繰り返したあと、再び英語で続けた。
「ぬいぐるみが話すという人間のイマジネーションは、パラレルユニバースを作りだします。パラレルユニバースは量子ゆらぎによって生成されるのですが、人間のイマジネーションは量子ゆらぎの方向を左右することができます。おそらくそうやって生成したと思われるパラレルユニバースの存在を突きとめました。僕が〈ぬいぐるみバース〉と呼んでいるものです」
今度はわたしが〈ぬいぐるみバース〉と3回繰り返す羽目になった。その後に、何と続ければいいかわからなかったからだ。
「そこで暮らすぬいぐるみたちは人間が自分たちに愛情を注ぐ世界を想像し、僕たちのイマジネーションとのバランスによってふたつの世界が保たれているのです」
それからスパイクは〈ぬいぐるみバース〉というアイデアに至ったいきさつについて説明してくれた。リュックサックからノートを取り出して数式や図を書いてくれたりもした。しかし、わたしは宇宙論の門外漢で、ただでさえ難しい話を英語で聞かされたので、正直あまり理解できなかった。そもそも、もう15年も前のことだからよく覚えていないところも多いけれど、スパイクが話したのはだいたいこういう内容だ。
世界が常に別の世界と対になっているという前提があって、その前提からわたしたちの世界を見たときに、ぬいぐるみに一方的に愛情を注ぎ続けるわたしたち人間の様子から、逆にぬいぐるみから人間に愛情を注ぐもうひとつの世界の存在を推論することができる。世界はそういう分岐を何度も経験していて、スパイクが言うところの〈ぬいぐるみバース〉の生成はその中でもっとも近い分岐であり、それは量子ゆらぎ――要するに何かの拍子で生まれた。
「何かの拍子って?」
「それは僕にもわかりません。新しいぬいぐるみを買ってもらった5歳の子供の強い喜びかもしれないし、幼い頃の夏休みにビーチにぬいぐるみを置き忘れてしまった老人の淡いノスタルジーかもしれない。でも、それはどうでもいいことなんです。世界の生成のタイミングは完全にランダムな確率現象であって、どれが作用するかなんて理由はないのだから。ただ一つ確実に言えることは、そうやってできてしまった世界だから、人間のぬいぐるみに対するイマジネーションが潰えてしまうと、ふたつの世界は――アナイアレーションは日本語で?」
一般的には消滅や全滅という意味だ。でも、宇宙論の話をしているのだから、たぶん少し違うはずだ。わたしは念のためにその場で電子辞書を引いた。一般的な用法の下の方に、物理学用語として〈対消滅〉という言葉があった。いかにも不吉な字面だ。わたしはスパイクにその言葉を教えるのも忘れて、彼に訊いた。
「〈アナイアレーション〉って、どういうことですか?」
「あなたやわたしのような人間が、ぬいぐるみは話すのだという前提のもと、ぬいぐるみに話しかけて愛情を注ぎ続けなければ、こちらとあちらの世界のバランスが崩れ――」
スパイクはそこで一度言葉を切り、マグカップの中のものを飲み干した。そして、ヘーゼルナッツ色の瞳をまっすぐわたしに向けて言った。
「そこで両方の世界は崩壊します」
スパイクはテーブルの上のものをすべて払いのけるような仕草をしながら、真面目な顔つきで「アナイアレーション」と呟いた。
「世界が崩壊するって、どうなるんですか? ぜんぶなくなっちゃうの?」
「基本的には〈ぬいぐるみバース〉が生成される前の世界に戻ります。ふたつの世界の分岐後に、それぞれの世界で対になってできあがってきた様々なものが消滅します」
「それって――」
「僕たちの世界の大半のものが――主にぬいぐるみやそれを愛する僕たちや、それらに関わるすべてのものです。ただ、それは実際にそうなってみないと、どれくらいの範囲に及ぶかはわからない。何が何とどんなつながりを持っていて、どういう影響が出るかなんて、誰にも知り得ないことですから。そもそも〈ぬいぐるみバース〉がいつ生成されたのかも定かではないのだし」
スパイクは大きく息を吐いた。こんなに恐ろしいことってあるだろうか、とでも言うように。
「だから、僕たちはぬいぐるみと話し続けなければならない。そうやってこちらの世界と〈ぬいぐるみバース〉のつりあいを取る力のことを、僕は〈Psychophysical Anti-Annihilation Thrust効果〉、略して〈PAT効果〉と名づけました」
スパイクの膝の上に座っているクマのパットが、プラスチック製の茶色い目を輝かせて得意げな顔をしていた。
「僕はこの子と、あなたはその――」
「グラウンドホグのほぐさん」
「――ほぐさんと。〈PAT効果〉を維持することが僕たちぬいぐるみを愛する者の使命なのです」
Tシャツにプリントされたスパイク・スピーゲルが、「おい、わかったか」と念を押すようにこちらを見すえていた。わたしは力なく何度か頷いた。
あらかた話が終わると、スパイクがほぐさんを触りたいと言ったので、少し持たせてあげた。彼はそれまでの硬い表情が嘘だったかのように顔をほころばせ、ほぐさんを撫でまわしながら日本語で「かわいい」と弾んだ声を上げた。
スパイクと別れたあと、わたしは聞いてはいけない話を聞いてしまったような気持ちで、アパートに帰った。しかし、夕飯を食べ、シャワーを浴びて、一晩寝ると、スパイクはただのぬいぐるみ好きの成人男性で、内心それを恥ずかしいと思っている自分を正当化しようとして〈ぬいぐるみバース〉だの〈対消滅〉だの〈PAT効果〉だのを持ち出しているだけだと思いなおした。
語学学校へ行くためにアパートの階段を降りていって、二階から一階への階段にさしかかったとき、部屋に電子辞書を忘れたような気がして足を止めた。ファスナーを開けてリュックサックを探っているうちに、ほぐさんが中から滑り落ちてしまった。わたしが声を上げる間もなく、丸々としたほぐさんは階段を転がっていって、玄関ホールの床にぶつかり、そのいきおいで壁際まで跳ね飛んだ。わたしは慌てて階段を駆け下り、ほぐさんを拾い上げた。「ほぐさん、ごめん!」
そのとき、頭の上に何かが落ちてきたような気がして、顔を上げた。壁を覆う小さなモザイクタイルのうち天井に近い部分の数枚がはがれていた。わたしはすぐに壁から離れた。
――アナイアレーション。
漆喰の地肌を眺めながら、スパイクの言葉を反芻して身震いした。
その1ヶ月後に帰国するまでの間、わたしは何度もキバハンに通ったけれど、スパイクに会うことは二度となかった。わたしはほぐさんをどこかに置き忘れたり、落としたりしないように慎重に取り扱った。
日本に戻るのに合わせて、今の夫となる男とともに暮らし始めた。彼もわたしやスパイクと同じ類の人間だったので助かった。もし、彼がぬいぐるみを憎み、めちゃくちゃに破壊するような人間であれば、〈PAT効果〉がわたしと相殺されるところだった。
〈ぬいぐるみバース〉や〈PAT効果〉のことをすぐに教えたほうがよかったのだけれど、話が話なだけになかなか切り出せなかった。そうやってピッツバーグでの出来事について黙ったまま平穏無事に暮らしているうちに、わたしの記憶や思考を他のものが占めるようになり、やがて日常的にあまり意識にのぼらなくなった。その間、わたしたちはほぐさんに家族の一員として2人分の愛情を注ぎ、スマホには思い出の写真がたまっていった。
3年ほど経った頃、夕飯どきに並行世界を扱った映画の話題になり、ふと〈ぬいぐるみバース〉のことを夫に話してみようと思い立った。
「そういう並行世界がないって証明することはできないし、仮にほぐさんがわたしたちに熱心に語りかけている世界があったら、それは楽しいだろうから、確かにそちらの世界も守りたくなるね」
そう笑ったきり、夫は一切口を挟まずに真剣に耳を傾けていた。しかし、わたしが語り終わるや否や、ほぐさんのおなかを触りながら、心底不思議そうにこんなことを言った。
「でもさ、わたしたちがほぐさんと話すのって、ほぐさんがかわいいからでしょ?」
夫はほぐさんに向かって「だよね?」と語りかけた。ほぐさんは黒いつぶらな瞳で夫を見つめながら、「そうだよ」と答えた。夫の声で。
確かにその通りだ。〈ぬいぐるみバース〉や〈PAT効果〉のことを知らなくても、わたしたちはふわふわでもふもふでころころのぬいぐるみを見れば、思わず話しかけ、撫でてみたくなる。わたしが3年の間〈ぬいぐるみバース〉についてさほど気を払わなくても取り返しのつかない事態にならなかったのは、けっきょくはそういうことなのだ。わたしたちはそうしたいからそうしていて、それじたいに何ものにも代えがたい価値がある。わたしとほぐさんとの会話が自動的に両方の世界を救うことに作用するのだとすれば、きっとそれはちょっとしたおまけみたいなものなのだろう。
というわけで、今もほぐさんはわたしといっしょに健やかに暮らしている。ときたまわたしはあちらの世界のほぐさんがわたしに熱心に話しかけている様を想像し、少し照れくさくなっては以前よりもくたびれてしまった目の前の丸いおなかに触れて、その柔らかさをいっそう愛おしく思うのだ。