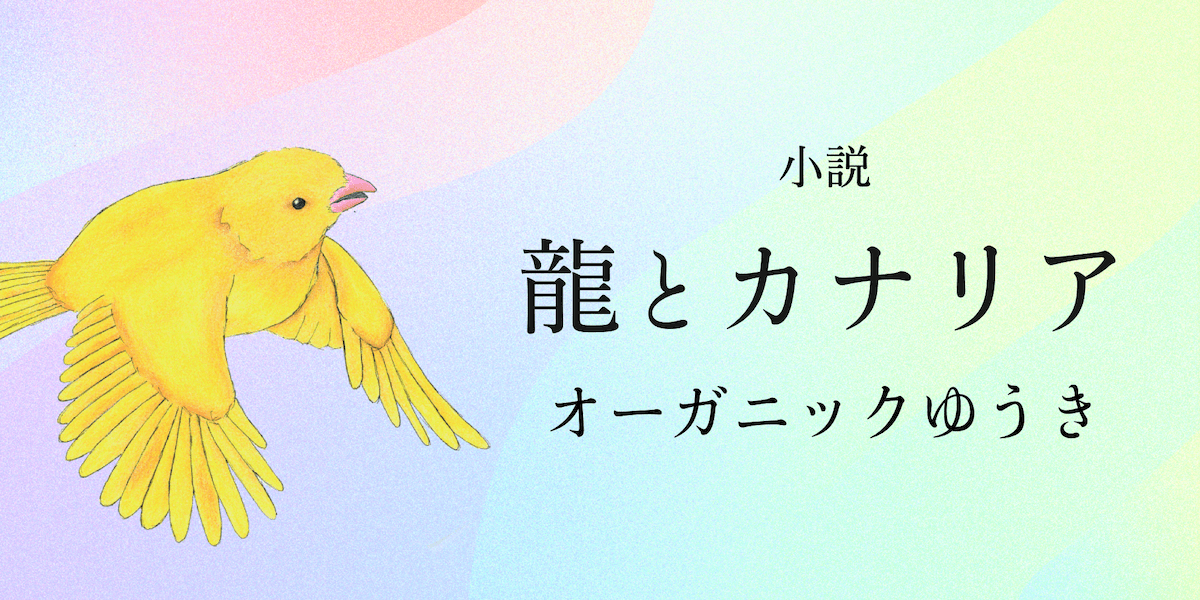オーガニックゆうき「龍とカナリア」前半を公開!
社会評論社より2020年12月25日(金)に発売される井上彼方編『社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本』に、オーガニックゆうきのSF中編小説「龍とカナリア」が掲載される。「龍とカナリア」は、『入れ子の水は月に轢かれ』(2018) で第8回アガサ・クリスティー賞を受賞したオーガニックゆうきによるSF作品。龍神の加護を受ける島を舞台に、登場人物の“からだ”や生き方を通して伝統と社会が持つ多面性を描き出す優れたジェンダーSFだ。
『社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本』の編著者である井上彼方は、バゴプラが主催した第一回かぐやSFコンテストで審査員を務めた。また、SF短編小説の定期掲載プロジェクト“Kaguya Planet”ではコーディネーターを務める。『社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本』では、要友紀子、鈴木 みのり、下山田志帆、インベカヲリ★、依田那美紀、そしてオーガニックゆうきと共に、フェミニズムを前提の価値観として、個人的なものであり社会的なものでもある「からだ」をテーマに、他者とのつながりを模索している。
バゴプラでは、オーガニックゆうき初のSF中編小説「龍とカナリア」の前半部分を特別公開。オーガニックゆうきが描き出した独特の世界観に浸りつつ、12月25日(土)の発売に備えていただきたい。
オーガニックゆうき「龍とカナリア」(前半)
井上彼方 編『社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本』収録
9,476字(本編15,847字)
イラスト 井上彼方
僕らの暮らす島には龍がいる。
龍は僕らに恵みをもたらしてくれる。龍と共にある者は、その魂に平穏を、勇気を、慈愛を宿す。そして龍の加護を受けた民とその島は、永久の幸せを築ける――この島の伝説を、僕は何も疑わず信じていた。
僕らの島は、食べ物に困らないほどの豊かな自然の恵みがあって、太陽は一年中暖かく照らしてくれる。地上には父さんが漁に出る海が広がっているし、暑さと争いを防ぐために掘られた地下居住地帯には、母さんや祖母のヒジャが機織りをする家がある。だから、僕は島の生活に不満なんて感じていない。
大人と言われる十五になるまで、あと一年。島での日常は龍神様に守られ、この幸せはいつまでも続く――無邪気に僕はそう信じていた。
ゼーシャが帰ってきたと知ったのは、狩りの修行中のことだった。
今年の夏、ゼーシャは十八の齢になったとヒジャ婆は教えてくれた。島民なら誰もが十五の時に「洗礼の儀」を受ける。ゼーシャが島を出たのは洗礼の年だったから、あれから三年が経ったということになる。
「洗礼の儀」というのは、僕ら十五未満の子どもが一人前の大人になったと認められるために行われる儀式だ。十五になった子どもだけが島の聖域に集められ、何かをやるらしい。僕はまだ十四だから、洗礼の儀がどういうものなのかを知らない。唯一分かっていることは、どうやら洗礼の儀では、僕ら子どもは、これまでどれほど修行を積んできたかが試されるということだった。そして洗礼に失敗した島民は、島を離れることもあると僕は知っていた。なぜなら洗礼の儀を失敗したその当事者こそ、ゼーシャだったからだ。
ゼーシャは、とても頭が良かった。必要なのは武術よりも知識だと言い、いつか医者の役目をきちんと果たせるようにと、誰よりも努力をしていたと思う。泥で湿ったシイタケのような、イシャナカシグサやハンダンマなどの薬草の臭いが全身から滲み出ていたし、山羊の革で出来たカビ臭い医学辞典を寝る間も惜しまず読みふけっていた。だから、ゼーシャが洗礼の儀を失敗したと知った時、僕は言葉を失った。
ゼーシャの洗礼の儀が終わった夜、僕は両親とヒジャ婆と一緒に、黙って夕食のテーブルについていた。みんなゼーシャの帰りを静かに待っていた。大人になるっていう儀式はこんなにみんなが大真面目になっちゃうほどの一大事なのかと、僕は驚いていた。誰も一言も喋らない時間が刻々と過ぎていく。母さんは落ち着かない様子で自分の手の甲の入れ墨を何度も擦る。漁から戻った父さんは身体も拭かずに、帰宅するさますぐに食卓に座った。父さんの汗と腋から滲み出る乾燥したタマネギみたいな体臭は、閉め切った地下団地の一室に充満した。マミナッツのスープが煮込まれ続けていて、このままじゃただでさえ糸のように細い具材が消えて無くなってしまうとハラハラした。お腹が空きすぎて僕の乾いた口からは胃液の臭いがしていた。家中、僕ら一家の汗とスープの蒸気で満ちて、屋根裏では僕と同じく腹を空かせたヤーネズミの暴れる音が響く。ゼーシャ、早く帰ってきてくれと何度願ったことだろう。
ゼーシャが帰ってきて、僕は真っ先に玄関に走っていった。ゼーシャは真っ赤な衣装に身を包んでいた。僕が近づくと、ゼーシャはいつものキスを拒んだ。戸惑っている僕に目も合わさずに自分の部屋へ向かっていく。僕を横切ったゼーシャからは、今まで嗅いだことのない、強烈な血の臭いがした(あの血の臭いがする獣を、僕は未だに知らない)。ゼーシャの着ていた服が真っ赤なのは、その獣の血を被っているからだった。慌てて小走りできた母さんが「おかえり」と言う前に、「ダメだった」とゼーシャは言った。母さんは、臆病なハブトカゲのように固まってしまって、地下へ降りていくゼーシャの後ろ姿を見送ると泣き出してしまった。父さんは黙ったままテーブルから動かなかった。誰もスープの火を止めない。お願い、ヒジャ婆、いつまでも鍋を煮出さないで、具材が無くなってしまうよ、だから火を止めて、お願い……。僕は悪夢にうなされるような声を出していたと思う。こんな気持ちは嫌だ、なんだか、悲しいし息が詰まる。お願いだから、誰かゼーシャを、母さんを、父さんを、ヒジャ婆を止めて――
あの夜のことを思い出すことは、なんだか僕を後ろめたい気持ちにさせる。だって、僕の家族を不気味に感じてしまった出来ごとだから。家族は一番守るべきものだし、信頼しなきゃいけないって、ミミ先生も言っていた。なのに僕は、ゼーシャも、黙りこくる父さんも、泣きじゃくる母さんも、スープに手を付けないヒジャ婆も、みんなを別人のように感じた。あの日の僕は、先生の言いつけを守れない子になってしまっていた。僕たち子どもが、必ず毎晩飲まなければならないニライの実の種も飲み忘れそうになるほどに、僕はゼーシャと家族の反応に戸惑った。
ゼーシャはそれから部屋に引きこもってしまった。僕ら家族と顔を合わせないように過ごして、二ヶ月は過ぎていったと思う。ある夜、首長を筆頭にして島の偉そうな大人たちがゼーシャを訪ねてきた。両親は大人たちと一緒に地下へ向かう。ゼーシャだ、ゼーシャに会いに行くんだ。僕が身を乗り出すと、ヒジャ婆の腕が伸びてきた。「ここで待とうね」と耳打ちして、ぎゅうっと僕を抱きしめる。どうして僕を止めるのヒジャ婆、僕には分かるんだ。ゼーシャは助けを求めてる。大人たちがみんなゼーシャを連れてどこかへいってしまうんだ。泣くだけじゃダメだよ、ヒジャ婆。父さんも母さんも、みんなを追い返さないなんておかしいよ。
やがて大人たちに引きつれられ、ゼーシャは一階に上がってきた。居間で両親と抱擁したあと、僕とヒジャ婆の元へと歩み寄る。
痩せた身体を屈めたゼーシャの目は、泣きはらして真っ赤に腫れていた。
「ああ、ヒジャ、お願い泣かないで。チャコ、ちゃんと修行するのよ、好き嫌いせずなんでも食べて……龍神様のご加護を」
ひしっと僕とヒジャ婆を抱き寄せて、ゼーシャは僕にしか聞こえない声で言った。
「チャコ、どうか私のようにならないで」
家を出ていくゼーシャに向かって自分でも何がなんだか分からないことを叫んでいた。ゼーシャは龍神様のご加護を、と繰り返し言いながら、大人たちと一緒に牛車に乗る。ゆっくりと夜道を走る車を僕は追いかけようとしたが、大人たちに止められた。母さんが僕の腕を引っ張り、ゼーシャは巡礼者になったのだ、島の外へ出て旅をする宿命を受けたのだと嗚咽しながら言った。神聖な旅なのだ、だから邪魔をしてはいけない。ゼーシャの旅を僕たちは見守ることしかできない――居住地帯の蒸気が靄がかかったように立ち込めるなか、車はゆっくりと僕らを離れていく。ぴしゃぴしゃと地面に溜まった水たまりを踏み、小さな水飛沫を上げる。僕は車の姿が見えなくなるまで何度もゼーシャの名を呼び続けた。
島の子供は、生まれたその日にすぐ龍神様の信託を受けて、医者・海人・門番・狩人いずれかの役割を与えられる。それぞれ火・水・風・土の属性だ。医者は島民の命を守る役目、海人は漁へ出て海を守る、門番は役人や商人や伝統職人など島の政治・経済・文化を守る。そして狩人は文字通り、山で狩りをし、島民の命はもちろん島の動植物を守るのだ。
狩人の才を持つ幼子は、一番厳しい修行を課される。なんせ他の島民には禁域となっている山へ、みんなの食料を狩りにいかなければならないからだ。そもそも山の探索は命の危険が伴う。どういう動植物が危険で、怪我をした場合どうするか、怪我をしないために日頃どう身体を鍛えるか、狩りの道具(火薬はもちろん、銃や弓、剣なども貴重なので、修行では基本的に縄や小型ナイフ、たまに銛を使った実践訓練をする)はどう扱うか。膨大な知識量と体力と実践に伴った経験……とにかく求められることが山積みだ。一つでも多くのことを十五までに覚えなくちゃならない。
自慢じゃないが、僕の狩人としてのセンスはかなりのものだと思う。このチームのなかでは誰よりも身体は小さいし力はないけれど、身軽だしすばしっこい。それに僕は鼻が利く。果物が熟れた臭いや、動物の糞尿の臭いは敏感に察知できる。そして、狩りの最後の務めである「綾取りの舞」――狩った獲物に祈りを捧げながら肉を捌く武術だ――僕は誰よりも美しく祈り、踊れ、捌けるという自信がある。年上のイロハは、今年十五の洗礼を受けるのに、獲物の血でナイフを滑らせる。メヤなんて、血を見るだけで悲鳴を上げる始末だ。
その日も、僕は森の中を一目散に駆けていった。少し前に降った豪雨で足元は滑りやすくなっている。泥濘を走るよりも、木々を飛び移ったほうが早く目標に到達できる。僕は何百本の毛が生えたアジマルの木の蔦を掴んで、枝という枝を飛び回った。降ったばかりの雨が足に染みるのが心地良い。雨粒がもたらす滑りがさらに僕を加速させる。周囲の葉っぱの甘い臭いがより僕の興奮を掻き立てた。滑走しながら細長く映る視界の端に、木々の間から見える空が、時々眩しく煌めく。加速していくほど、緑色の星空が永遠に続いていくかのような感覚になっていく。
「チャコはまるで瑠璃鳥が飛ぶように移動するね。お見事!」
ミミ先生の声が聞こえる。瑠璃鳥は青色に羽が煌めく鳥だ。目にも留まらぬ速さで川に潜る、鳥類随一のハンター。僕は嬉しくてたまらなくなった。もっと早く! 誰よりも先に獲物を見つけるのは、僕なんだ!
「でも、勢い余って見失っているよ!」
背後から、投げ縄の音がした。続いて僕の左側から人影が伸びてくる。酸っぱい干しぶどうのような匂い――イロハだ!
「チャコ、甘いわね!」僕が木の幹を慌てて蹴って飛んだ瞬間、イロハの声を発した影が地面へ急降下していく。僕はただ目の前で、ヤマイノシシを模した藁人形が、イロハに喉元を切り裂かれる様子を眺めるしかなかった。
「そこまで! イロハ!」
ミミ先生の号令が響く。次々と目標の人形の周りに、狩人の見習いの八人の子どもが集まってきた。みんな息が上がっている。
「あー! 悔しい!!」
先を越されて地団駄を踏んでいる僕を、イロハは得意げに見下ろしてきた。イロハの右手には藁人形の首がぶら下がっていて、よく日に焼けた腕からは大粒の汗が滴っていた。
「これで七勝六敗ね。私の一つ勝ち」ふっふーんとイロハは鼻を鳴らした。
「イロハちゃん、すごーい。私なんて、走るので精いっぱい」
ぜえぜえと息をしながらメヤがよろめいている。全身が泥にまみれ、編み込まれた髪には木の枝や葉っぱが刺さって針山のようになっている。メヤはこの狩人の見習い班のなかで一番年下の九歳だ。ただでさえ小さい身体の上に、実践の経験は圧倒的に少ない。それでも必死に食らいついている。ちなみに、僕の身体はメヤより頭一つ分小さい。
「はーい、朝の訓練はここまで。柔軟と片付けをしたら、お昼にしましょう。ニライの実を忘れた子は言ってねー」ミミ先生の声だ。
しばらくして、休憩がてら木の実を食べていると、ミミ先生がイロハに声をかけた。
「イロハ、今夜洗礼の儀よね。打ち合わせのこととか聞いている?」
「いえ、まだですけど……」
「舞の準備もあるし、そろそろ参加者で顔合わせくらいはしておいた方がいいと思うんだけどなあ。村長は何も言ってない?」
ええ、と言葉を濁してイロハは黙った。ミミ先生は訝しげな表情をしたが、
「まあ、そのうち打ち合わせするだろうから、イロハは練習も本番も無理しすぎないようにね。きっと素敵な洗礼を受けられるわよ。龍神様のご加護のあらんことを」そう言って他の見習いのところへ行った。
イロハはどこか不安げな様子でいる。メヤが心配そうに見ていた。
「イロハちゃん、どうかしたの?」
「え? ああ、ううん。何でもないの」
「水臭いなあ。何でもないって顔をしてないっての」
僕が横槍を入れると、イロハはムッとして何かを言いかけて唇を噛んだ。(言えるわけないじゃない)、そう口ごもったような気がする。
「ニライの実も今日で最後かあ。思えば一五年ってあっという間ね」
イロハは竹の弁当箱からニライの実を取り出した。僕らが生まれるずっと昔は、ニライの実はザクロと呼ばれていたらしい。僕らが食べているよりももっとずっと実は小さくて、小さな粒がぎっしりと詰まった果物だったらしい。一粒の大きさは小指の爪ほどの大きさだなんて、今じゃあ考えられない形状だけど、昔の写真を見たら、たしかに皮の厚さや、実の赤さ、真ん中にある柔らかくて大きな種などは、かつての遺伝子を引き継いでいそうだ。現代のニライの実の形は、むしろ絶滅した島バナナという果物にかなり似ている。バナナは独特の腐った臭いがしたそうだけど、ニライの実はみずみずしくて甘みが強い。僕の大好物でもある。
「洗礼の儀って、自分の好きな衣装を選べるんだよね。いいなあ」メヤは目を輝かせた。
「この島はなんつーか、お洒落しても仕方ないからね。せっかくのお洋服が臭っちゃうし。ほんっと、お祭りのときくらいよねー。島の外ではいろんな格好をした人が街を歩いてるんだって」イロハはため息を吐きながらメヤの髪を解き始めた。
「なんだ、イロハは外の世界が好きなのか?」僕はニライの実を頬張ってイロハに聞く。
「別に好きとかじゃなくて。でもあんたくらいじゃない、手放しに島が好きな子どもって」
「島の外って、私すごく憧れるんだあ」顔を赤らめながらメヤが言った。
「あ、あの……お母さんには秘密にしておいてほしいんだけど……。わたし、島の外に行ってみたいの……すごく大きな工業地帯があるんだよ……」
メヤの髪の草を抜いていたイロハは、目を丸くした。
「へえ、メヤ意外。大人しいから、島で落ち着きたいって思っているんだとばかり」
「コウギョウチタイってなんだあ?」
「チャコってば、そんなことも知らないの? 外の世界には、工場とか、機械とか、電子機器とかがたくさんあるのよ。こんな竹筒とか使わないで、水筒とかお弁当とかはプラスチックってやつで包めるのよ。保温もできるし、氷も溶けないまま運べるんだよ? ただ、この島では、プラスチックは龍神様の教えに反するから使っちゃだめなのよね。便利なのは羨ましいけど、自然の教えに反するのには私はやっぱり抵抗ある」
「なんで龍神様の教えに反するんだ? 便利なものなら使いたいのに」
「グソー送りができないからだよ。外の世界の人たちはプラスチックを、毎日少しずつ食べているんだって。私たちがニライの実を毎日食べているみたいに」本当に外に憧れているんだろう、メヤは嬉しそうに母親から聞いた話をし始めた。
「外の世界では、この島のグソー送りみたいに、亡くなった人を火にくべたり、海に返したり、風に吹かせたり、土に埋めたりしないの。みんな身体が腐らないから、何百年も眠ったように横たわってるの。私たちは死んだらまた生まれるために龍神様の元へ帰るでしょう? 身体が腐らなかったら自然に帰れないから、この島はプラスチックを生活に取り入れないようにしてるんだよ」
「身体が腐らないって本当かよ。プラスチックは身体まで変えちゃうのか」
「でもね、みんなすごく長生きするみたいだよ。それに、とっても綺麗なんだって。ゴミとか、臭いとか、動物の死骸とかが無くて。みんな幸せに暮らしてるって……」
「はーい、みんなニライの実は食べた? ちゃんと種も飲み込むのよー。そろそろ村に戻って、果樹園のお手伝いに行くわよー。儀式の果物の刈り入れよー」
ミミ先生の声がした。なんだよ午後は農業かよーと周りの見習いたちのボヤキが聞こえる。僕ら三人はおしゃべりを中断して、慌てて食べかけの果物を飲み込んだ。
太陽が空の一番高いところに上っている。ジリジリと僕らの肌と赤土の地面を照らして、時々大きな雲に隠れたりしていた。
僕らは切り立った崖の上で整列していた。村を目指して、一斉に崖の上から飛び降りる。ひゅっと風が耳元を走っていく。
バババッ――腰の鞄から、僕の背丈の倍ほどの傘が二つ伸びた。傘が垂直に伸びていくのを助けるよう、僕はお腹にぐっと力を入れて上体を起こす。やがて二つの傘は耳の横でピーンと立ち上がり、くるくると回転しながら膨らんでいく。もこもこと、空気を集めてまん丸く膨らんでいく様子は母さんが焼いてくれるパンナ(白い餅のような柔らかい食べ物だ)に似ている。二つの傘はある程度膨らむと徐々に回転が遅くなっていく。傘の回転が遅くなるにつれ、僕の下降もゆっくりとスピードを落とす。もう充分に空気を吸い込んだだろう、僕は横に伸ばしていた腕を下ろし傘の柄を握りしめた。頭上では歯車と歯車が噛み合うように、二つの緑色の傘が同じ速度で回転している。「点呼」の声がずっと後ろの方から聞こえてきた。僕の番が回ってきて、高らかに3と叫ぶ。肺の中に谷から吹く潮風の空気が満ちた。8(メヤだ)の番号の声が聞こえる。全員無事に飛んでいる。僕は身体を回転させ、天を仰いだ。
十六の傘がくるくると降りてくる。赤、青、黄色、白、紫、黒、桃、橙……空を背景にして色とりどりの傘が回転する様子は万華鏡のようだ。陽の光を浴びて、潮風を受けた傘が踊る。鳥のように、仲間と一緒に飛ぶ。ああ、そうだ――。
今更気づくなんて遅いかもしれないけれど、僕はこの時間が大好きなんだ。イロハとメヤが、ちゃんと地上を見ろと僕に注意してくる。大丈夫、怪我しても知らないからね、と言い合いながら、僕らは笑い合う。風を受けて、ただ一緒に飛ぶ。僕は、この時間が永遠に続けばいいのにと思った。大人になるための修行だとか、来年くる洗礼の儀とか、そんなことなんてどうでも良いような気がしてくる。僕らはただ、僕らの居場所を目指して飛ぶ。それが僕の望む幸せで、求めている世界なんだって、そう思いたかった。
地下居住地帯は蒸し暑いし臭いという人もいるけれど、僕はこの島の暮らしは大好きだ。ずっと昔にあった戦争の体験から、この島の人々はいつかまた同じような争いが起きても一人でも多く助かるようにと地下に巨大な防空壕を作った。一つの防空壕は、一周するのに僕の足で一時間はゆうにかかる。各ブロックごとにまちまちだけど、高さは平均してだいたい五階建ての家の高さくらいあって、天井には換気や水道の太いパイプが何本も走っている。このブロックがいくつもの通路同士で繋がっているのが地下居住地帯だ。蟻塚のような作りと要塞のような見た目も相まって、秘密基地みたいだ。ブロック同士を繋げる通路には、商店街が立ち並んで、いろんな食べ物の臭いや島民の生活臭が充満している。
僕の家は地下団地と言われる、二階建ての一軒家が立ち並ぶブロックの一角にある。島で一番人口の多い居住ブロックだからか、四方を商店街の通路で囲まれている。どうやら僕たち島民は臭うらしいけれど(メヤは本当に毎日、この臭いの愚痴を言う!)、それは団地の強烈な生活臭の影響が大きい。知り合ったばかりの時、僕はよくメヤから風呂の石鹸はなにを使っているのかとか、修行着(母さんが作るバシュの葉の織物の作務衣だ)は換気口の前で干せとか言われた。メヤに言われたとおりに体は隅々まで洗っているし、作務衣も臭いがしないように気をつけてはいる。けれど、僕からすればメヤがそんなに臭いを気にすることの方が少し不思議だった。
メヤの体からは、たしかに島民独特のカビ臭さや、酸っぱい臭いはする。けれど、僕やイロハのように自然と香ってこない。僕でも気をつけて嗅がなければ気づかないくらいで、無臭と言った方が近い。訓練が終わればメヤはその場で作務衣を脱いで持参した水筒の水をかけて身体を拭く。体を拭くための水を持ち歩いているのだ。聞くと、商店街の消毒用のアルカリ水を少し混ぜていると言う。これで体臭を抑えられるのだと八百屋をしている母親に教えてもらったらしい。
眼下に広がる地上の果樹園を眺めながら、僕は隣を飛ぶメヤを見ていた。強烈な風を受けてもなお、メヤの臭いはわずかにしか僕の鼻に届かない。メヤはなんで外の世界に憧れるんだろう。メヤは外の世界はキレイだと言っていた。外は肉体が腐らない世界なんだって。たしかに島の生活は腐敗臭が立ち込めている。でも僕は、この島の臭いは嫌いじゃない。それにむしろ、その臭いの濃い我が家に帰るととっても安心するほどに、この臭いを好んでいる。母さんのハジチ(織物の紋様が掘られた刺青)が掘られた手からは、ふやけたバシュの臭いがする。父さんは魚と汗の臭いを常に出しているし、ヒジャ婆の髪からは、酸化した油とシナモンが混ざったような臭いがする。この家に、家族みんなの臭いが立ち込めているということは、みんながそれぞれの勤めをきちんと行っているという証だと僕は思う。そうして龍神様のご加護を受けて、幸せに暮らしているんだ。だから、僕はメヤの気持ちが分からない。この島で生きることから逃れたいという気持ちは僕にはないから。
そう言えば、ゼーシャはどんな臭いだっただろう。
勉強熱心だったから、インクとか、辞書のカビの臭いだったか……。僕の記憶には、あの洗礼の儀の衣装から臭った得体のしれない獣の臭いが「ゼーシャの記憶」として染みついてしまっていた。あの血の臭い、本当に心当たりがない。あんなに服に染み付くほどにじむなんて。洗礼の儀では、龍神様が出てきて闘うとか、そういう儀式をするのだろうか……。まさかね。僕は思わず一人笑いし、今しがた浮かんだ考えに頭を振った。龍神様が現れたりなんかしたら、毎年洗礼のたびに死者が出てもおかしくないじゃないか――
「!」
ミミ先生の叫び声がした。直後、頭上から数発の破裂音が轟く。視界が大きく揺らいだかと思うと、右肩に激痛が走った。ドン、と衝撃音が続く。身体が大きく傾いた時、やっと僕は身体がパラシュートの浮きを失って急降下していると気づいた。二つの傘は大きな穴が空いてコントロールを失った凧のように暴れている。火薬の臭いが鼻を突く。まともに息ができない。周囲では銃撃音のような乾いた音が数発続いている。僕の身体は相変わらず落ち続けている。どうすればいい――混乱のなか、視界を覆っていた白煙が徐々に薄らいでいく。何か黒い影が近づいていた。
グワン、と風を切る音を立てて大きな凧が現れた。トンボのような形をした凧が僕の周りを旋回する。トンボにはマスクをつけた、僕がこれまで見たことがない黒い異国の民族衣装を着た人物が乗っていた。マスクには青い信号機のように光ったレンズが付いて、鳥のような嘴が伸びている。僕はしばらくその人物に見とれてしまったけれど、すぐにトンボの腹のあたりに銃がつけられているのに気づいた。謎の人間は、僕を助けようと言わんばかりに腕を伸ばしてくる。僕は咄嗟にその手を払った。
「お前! よくも、みんなをッ!」
黒服の人物は黙っている。やがて口元に手を伸ばし、顔を覆っていたマスクを剥いだ。
僕はあまりの光景に声を失った。髪が短くなって、体格も違うけれど間違いない。
僕に腕を差し伸べてきているのは、紛れもない――ゼーシャだった。
もう地面までそんなにないだろう、僕は酸欠状態になりかけていた。遠くで誰かが僕の名前を呼んでいる。かすかに、本当にかすかだけど懐かしい匂いがする。オクヒマワリの花みたいな湿気の籠もった匂い。
ゼーシャ、本当にゼーシャなのか。
やがて僕は意識を失った。海に投げられた石のように、僕は広い空を落ちていった――
1992年生まれ。小説家。デビュー作『
オーガニックゆうき「龍とカナリア」の全編を収録した『社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本』(井上彼方 編, 社会評論社) は、2020年12月25日(金) 発売。Amazonで予約受付中。
オーガニックゆうきのデビュー作『