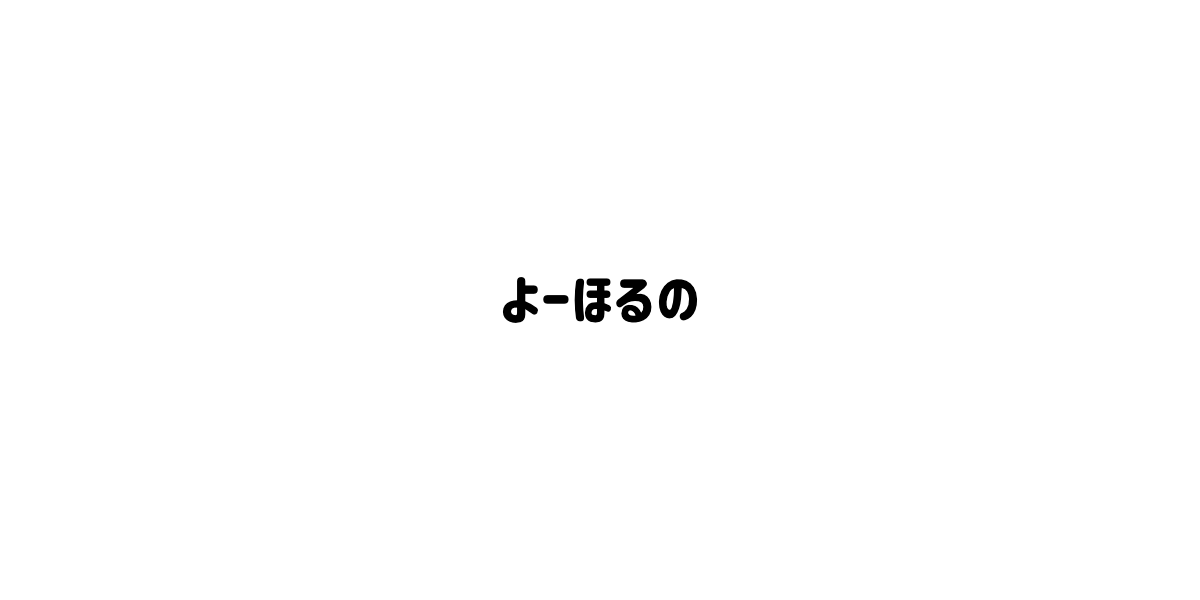よーほるのむらめぎむまのくがみちぬくもやをるやにぺかみむるかも
私は手を止めます。私は顔をあげます。黒板は右側から差した日の光が白っぽけて反射していて、教室の左側にいる私には見にくいので、体を傾けて、その文字列を確かめます。
それはむかしの清い王が作った歌なのでした。黒板の上下が短いのと先生の字が大きいのとで、三行に分けられたその歌と清い王の名前を、私はノートに一行に書き写します。そしてそこから動けなくなる。
先生が説明をしています。一四〇〇年前の、むかしここいらが一面野原であったころ、むまで出かけて草を踏んだ歌だといいます。むまは馬です。むかしのことですから蹄鉄をしない、肩の低い国産馬で、乗る人の足は露で濡れましたし、むまの蹄の裏は草の汁で悪くなりました。そして、これは、清い王一人だけで行ったのではないのでした。清い王は一番の親しい友人と行き、朝焼けの赤みの残る野原を二人で踏みしめたのでした。
先生の言葉をノートに書きとめる音がそこここでします。私も書きとめねば、と思うのですが、ノートに書き写したその歌を見つめたまま動けない。だって、その歌は私の歌なのです。作った人は一四〇〇年前の王様、私はむまに乗ったことがない、そうでしょう、だけれど、この気持ちは私のものなのです。私のことがそこに書かれてあるのです。私の気持ちは、こんなところにあったのです。今まで何度も見ていたはずなのに、気がつかなかった。
「せんせいー、まぶしくて見えません」
「あ、ごめんなさいね」
先生が話を中断してカーテンを引きます。
よーほるの、と小さくとなえたのをにゆちゃんが耳聡くつかまえて、「さっきの授業の?」と尋ねます。
「うん」
「好きなん?」
「そうなん」
私はうなずきます。私たちの言葉は口に出されると著しくゆがみます。教科書に使われている言葉と、はげしく違ったかたちになるのです。くもやをるやに、と言った先生の声にはゆがみがありません。先生はそのための訓練をしていますから、ただしい発音で言葉を言います。でもときどき、驚いたりしたときにはゆがみが出ます。
にゆちゃんがふうん、と言って実験道具を抱えなおします。にゆちゃんはとても小柄ですから、移動教室はいつも大変そう。少し持とうか、と言うのに、にゆちゃんはいいよ、と言います。「うちけっこう力あるねん」にゆちゃんはたしかに力持ちなのですが、私の半分しかないようなちいさな腕ですから、上半身をそらさなくては全部のものが持てませんし、本やガラス管が体の輪郭からてんでにはみだして、私はたまらなくなるのです。にゆちゃんは、この世界の何もかもを目にしてやろうとするみたいに顔をきょろきょろさせています。いつもと同じ学校ですのに。と、
よーほるの
と言ってにっこり笑いました。私はにゆちゃんの顔を見返して、
「あっ」
と言いました。いま、なんと言ったの? にゆちゃんもあの歌を気に入ってくれたのでしょうか。いいえ、違います。にゆちゃんは国語が苦手です。今のは、私をからかうために言ってくれたのでしょう?
「なあ、もっかい言ってや」
「いやや。一回しか言わへん」
「なんで、もっかい聞きたいわ」
「いやや」
にゆちゃんはきっぱり言って、また荷物を抱えなおしました。ガラス管がかちゃんと鳴りました。ガラス管はどれもこれも古くて、ヒビが入ったり黄色っぽくなったりしています。私のガラス管も似たり寄ったりです。もう、新しいものはないのです。
授業がはじまると、私たちは理科室の机に並んで座り、ガラス管に色のついた水をいれたり、まぜたりします。理科は少しつまらない。にゆちゃんと別の班だから。私は班長のサミノさんの指示に従って、試験管の中に、つばを吐いたり窓から手を伸ばして摘んだ葉っぱを閉じこめたりします。試験管の中身は、変化することもあるし、しないこともあります。私たちは全ての記録をノートに書きます。
先生は黒板に大きなグラフを描いています。いくつもの色をつかって虹のようです。理科室は校舎の一階にあるし、植え込みと小道を挟んですぐのところに高い塀があるので、めったに外の光は入ってこられません。黒板は光を反射しないで、黒々としたまま、先生の描く虹がふくらんでいく。虹のしくみも理科でならいました。光の屈折。光はまがる。
よーほるの
の歌のむまが踏んだ草の露も、光をまげたでしょうか。
にゆちゃんの班は、実験が佳境に入っているようでした(佳境、はこの間国語でならった言葉です)。大小いくつものガラス管には色のついた水が入っていて、火にかけられたり、大きな洗濯バサミではさまれたり、金属の蓋をかぶせられたりしています。ガラス管同士はゴムの管でつながれて、机の上はまるで教科書の写真で見た遊園地か、大都会のよう。にゆちゃんはひときわ大きな、目盛りのついたガラス管を設置し終えたところです。自分より頭一つ分も大きな人もいるのに、にゆちゃんはお任せにしないで自分でやったのでした。きっとにゆちゃんは鼻のあたまに汗をかいているでしょう。理科室が一階でなく、三階や四階にあったなら、にゆちゃんの汗も光って見えたでしょうか。
理科の授業のあと、にゆちゃんが尋ねます。
「実験、見てた?」
「見てた。成功しとったやん。すごかった」
にゆちゃんは無表情になってうん、と言います。無表情、というよりは、表情が動くのを抑えこんでいる顔。にゆちゃんはほめられるといつでもこんな顔になる。にゆちゃんが黙ってしまったので、私たちの抱えるガラス管の、がちゃ、がちゃ、という音がはっきりと聞こえます。私はにゆちゃんと歩調をあわせます。がちゃ、がちゃ、という音がぴたりと重なります。
「重いねえ」
とにゆちゃんが言います。
「めんどいな、これ」
「な」
私たちは実験道具をロッカーに収めて次の授業の準備をします。どの授業もにゆちゃんとずっと一緒です。席ははなれていますが、おなじ教室で、おなじ先生のおなじ声、おなじゆがまない言葉を聞きます。
放課後になるとマーチが聞こえます。吹奏楽部のマーチです。吹奏楽部は、放課後が終わるまでずっとマーチを演奏し続けています。マーチにあわせてみんなが下校していくのを、私は三階の窓からこっそり見ています。
みんなは学校の正面玄関から順番に出ていきます。と言っても出席番号のように、厳密な順番があるわけではありません。一人とか二人とか、三人、五人で固まって出てくるのです。上から見ていると、途切れ途切れながらくりだされる、こぶのある糸のように見えます。三人、五人でいる人たちがこぶです。ときどき前と後ろのこぶが合流して、大きなこぶになったり、一人、二人にほぐれてほそい糸になったりします。
校門を出ると、みんなは溶けます。校門を出たすぐのところにある溝をまたぐと、お湯にとかしたお砂糖のように(私は理科の飽和水溶液の実験を思い出しています)、髪の毛から爪先まで、スウッととけて、制服も靴もなくなります。まれにとけない人がいて、溝のそとまで歩いてしまうのですが、その時は大人の人がやってきて、とんとんと肩か首のところを叩きます。すると、やっぱり、とける。
翌朝の、きまった時間になると、私たちは登校します。校門の溝からむくむくと再生して、頭や目鼻、体、制服と靴を備えて歩きだす。再生は一人ずつなのに、校門から玄関までのあいだに、一人とか二人とか、三人、五人になるのでした。歩くのが速い人や遅い人、再生の早い人と遅い人がいて、あの子が好き、あの子は嫌い、というのがあって、こぶと途切れになるのでした。それは個人差なのです、と、社会科でならいました。私たち「近代の学校」は、このようにして保全されます。
ですから本当は私も下校しなければなりません。もう少しすると、先生たちが下校します。先生たちは溝をまたいでもとけません。先生たちが下校すると、吹奏楽部のマーチが止まり、学校が暗くなります。夜が来て、ふくろうが鳴き、夜泣きのカラスが鳴きます。
早く下校しなければ。そう思うのに、今日も私はぐずぐずと窓の外を眺めているのでした。校庭を歩くみんなの行列はだんだんと途切れがおおくなる。私もあの列に入らなくてはなりません。もうだめかしら。まだ大丈夫。玄関から誰かが出てくるたびに焦りがつのります。だのに、下校する、ということを考えただけで、力が抜けてへなへなとその場にしゃがみこんでしまう。だって下校をしたら今日が終わってしまう、だなんて、おかしなこと。私たちは保全されていて、明日は絶対に来るのです。でも、一度へなへなになった私は、もう立ち上がることができない。
私はへなへなのまま這って教卓の下に行く。夜の学校は真っ暗でうかつに動くと危ないので、吹奏楽部のマーチが止まる前にそこに移動するのでした。そして、翌朝、みんなが登校するまでそこにいる。そこにいて、にゆちゃんが来るのを待っている。
ぎゅう、ぎゅうと鳴くのは夜泣きのカラス。カラスは黒いから窓の外を見てもどこにいるのだかわかりません。何より学校は真っ暗ですから、私の手のひらも、鼻にくっつくくらいに近づけても見えません。手のひらを鼻にくっつけると、鼻の頭がぬるぬるしているのがわかります。手のひらからは香ばしいような酸っぱいようなにおいがします。実験の薬ともノートやえんぴつとも違う、私のにおいです。よーほるの、と口の形だけで言うと、かさかさの唇の皮が、手のひらをひっかきます。
朝になるとみんなと一緒ににゆちゃんが登校します。にゆちゃんは一人、二人、三人や五人、の中の一人です。一人で校門まで歩きます。一人で階段を登り、教室に入って、私におはようを言います。
「おはよう、にゆちゃん」
今日も会えましたね。