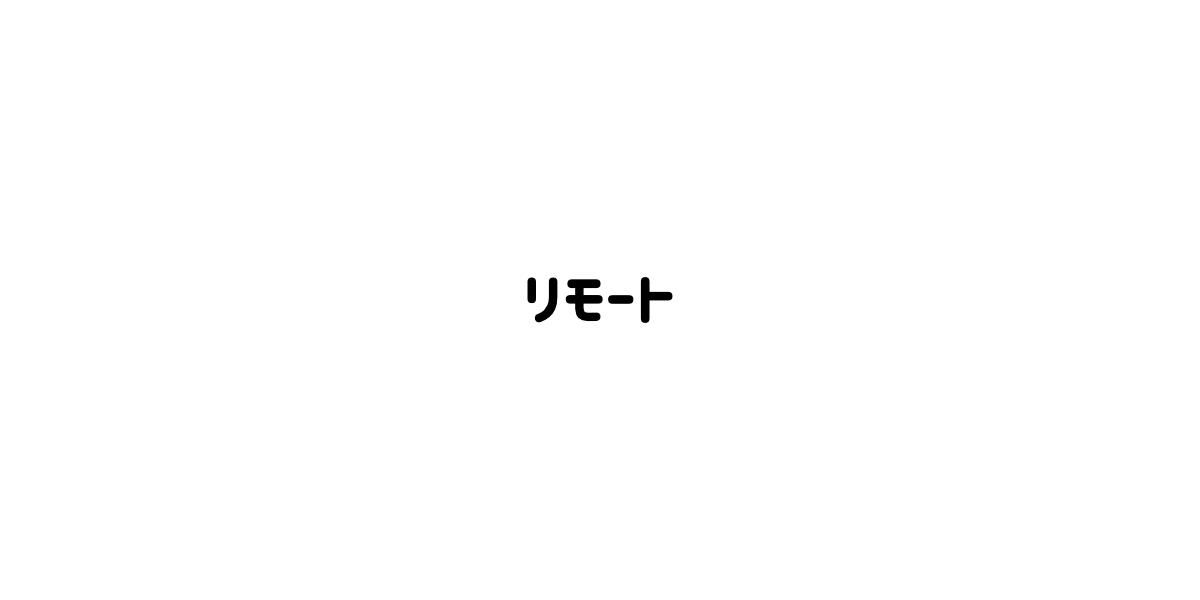サトルが来ることは、サトルが来る前から聞いていたんだ。ヤマノ先生が一週間ぐらい前に教えてくれた。だけど、自分たちと同じ男子中学生であること、事故で体が動かないこと、だから「ロボット」で学校に通うことぐらいしか教えてくれなかった。ヤマノ先生は今年で定年だけど、それでも「ロボット」なんて言い方、ちょっと古臭くて、最初は何かの冗談なのかと思った。
でも確かに、サトルを初めて見た時、「ロボット」っていう感じがしたんだ。テレビで同じようにリモートで学校に通う子供を見たことがあるけど、それはもっと洗練されていたのもあるんだと思う。テレビではアンドロイド型のものもあったし、個性の強いメカニック系のものもあった。サトルのは、カラーリングもほとんどされていない部分もあったし、少し型が古い印象があったからなのかもしれない。でも、前世紀のいわゆる「ロボット」とは、似ても似つかないんだけどね。
「きっとそれは」サトルはいつか答えてくれたね。「テレビに出るような子供たちは、大口のスポンサーがついている場合がほとんどだからだよ。昔は企業のロゴをつけてたなんて例もあったそうだし」
「サトルにはそういうスポンサーはいなかったの?」
そう聞くと、サトルは画面の奥で笑ってたね。
「現実的に言えばそれは運とコネの問題だ。だけど、心象的には、アイデンティティの問題でもある」
「アイデンティティ?」
「この体の所属は誰のものか、という、古典的な話だよ」
サトルは指の先だけが辛うじて動かせると言っていた。だから指につなげたデバイスで入力された言葉が音声化されて伝わるんだったね。そのせいもあるのか、使う言葉が妙に堅苦しくて大人びて聞こえることがあった。
「先生」
サトルはよく先生に対しても歯に衣着せぬ発言をしていたのを覚えている。
「ここ一週間の間、僕がこの教室内で発言した回数が、他の生徒の平均と比べて極端に低いことが気にかかります」これは、社会の教師に対して批判した時だ。「教育の機会均等というよりかは、僕のこの筐体のために先生が指名をためらっているのだとしたら、その点はご配慮いただかなくてもいい、ということを伝えたいのです」
でもこれは失敗だった、とサトルは後で言ったね。
「僕の中でこれは、前世紀からある人種間の差別と同類の問題なんだ。でも、この学校の教師はただ不慣れで、戸惑っているだけだ。だから、僕の言葉はただの皮肉になってしまったし、彼らの業務量を増やしただけだろう」
サトルは特別だった。生徒たちは、そこに憧れや嫉妬みたいなものを感じていたんだと思う。カオリのことは覚えてる? この前、久しぶりに彼女に会ったんだよ。
「サトルには感謝してる」
そう彼女は言っていたよ。指を広げて、目の前でグーパーして見せた。
サトルとカオリの話は、秋の終わりぐらいだったかな。みんなサトルに慣れてきたころで、サトルの見た目について冗談を言えるぐらいになっていた。安っぽい保護素材とか、効率だけ考えた六本の脚とか。その中には際どいジョークもあったのかもしれないけど、サトルは笑ってやり過ごしていたね。
だから、カオリを揶揄する男子たちの言葉に、サトルがあんなに怒ったのが意外だった。カオリが持っていた六本の指と、自分の姿を重ねたのかな、と最初は思ったけど、たぶんそれは違うよね。
「嬉しかったんだ」カオリはそうお礼を言っていた。「私もよく六本の指について友達にからかわれた。いつも適当にやり過ごしてたけど、サトルがあんなに怒ってくれたから、ああこれは、笑って済ませていいことじゃないんだって、そう理解できたんだ」
だけどね、サトル。カオリの六本目の指はもうないんだ。手術でとってしまった。
「実は、サトルが怒ってくれたあの日、もうあの日には、手術の日程が決まっていたの。だから、嬉しい気持ちもあったけど、なんだか複雑だった。私はどっち側の人間なんだろうって」
カオリはいい子だね。サトルもそう思うだろう?
君と最後に一緒に話したのは、その冬の一番寒い日だった。
いつもサトルのリモート筐体は学校の隅の倉庫に保管されていた。ヤマノ先生が放課後そこまで運んでいて、その日も先生が運ぶはずだった。だけど、他の先生が焦った様子でヤマノ先生を呼びに来た。だからその代わりに、一緒にサトルを連れていくことになったんだ。
「どうして学校に来ようと思ったの?」
その質問を君にしたことを覚えているだろうか。君は少し考えているようで、珍しく沈黙が続いた。サトルの六本分の足音が静かにがしゃがしゃ廊下に響いていて、なんだか懐かしい気持ちになったことを覚えている。
「肉体と精神、どちらが優れていると思う?」
君は答える代わりに質問を返した。精神かな、と答えると、君は「確かにそれが一般的だろう」と、画面の奥で頷いて見せた。
「行方不明者のことを考えてほしい」君はそこで立ち止まったんだ。「十年経とうが二十年経とうが、肉体が出てこなければ、彼らはずっと行方不明のままなんだ。恐らく死んでいるにも関わらず、肉体がなければそこに死は存在しない。この世界では、物理的存在が常に一義的になるんだ」
いつもはゆったり喋るサトルだけれど、この時の君は、この台詞をたぶん一息で言い切った。それからまた、六本の脚でがしゃがしゃ歩き始めた。倉庫はすぐそこだった。
「画面の向こうからリモート的に存在するだけでは、たぶん僕は何の痕跡も残せなかったと思うんだ。だから僕には肉体が必要だった。そういえば、少しは伝わるかな」
その時、君にそう聞かれて頷きはしたけれど、本当はよくわからなかった。少し実感をもてたのは、サトルの父親が逮捕されたのを知った時だ。
サトルの父親の罪状は詐欺罪だった。サトルの障害児福祉手当を違法に受給していたからだ。なぜ違法かと言えば、サトルは既に死んでいたからだ。この学校に来る何か月も前から。
後で知ったことだけど、サトルの「ロボット」は、父親が遠隔で操作していたということだった。彼は仕事も辞めて、ずっと家に籠って、「ロボット」を動かしていた。画面にはサトルの生前の動画を合成し、父親自身がキーボードで打った言葉を、サトルの「ロボット」は喋っていた。サトルの生前の行動をデータ化して、どうしても父親自身がその場を離れなければならないときは、ボットのようにこたえさせていたこともあったそうだ。その父親がどういう気持ちで「ロボット」を動かしていたかはわからない。ただ、不正受給していたお金には一切手がつけられていなかったそうだ。
あの一番寒かった冬の日、ヤマノ先生は、その父親が逮捕された件で校長先生に呼ばれていた。じゃあ。じゃあ、あのとき、「肉体と精神」の話をしていた君は、誰だったんだろうか。サトルのボット? それとも? それが知りたくて、こんな手紙を、君に送るんだ。出す当てもない手紙を、電子の波に向けて。
「さあ、電源を切ってくれ」
倉庫の中に入ると、君はそう言った。電源の場所なんて僕は知らなかった。
「ここだよ」
サトルの画面の下あたりにプラスチックの蓋があって、そこを開けるとボタンが見えた。「ゆっくり、確実に押してくれ」
君が最後にそう言って、僕がそのボタンをゆっくり、確実に押した。感触は曖昧で、音もしなかった。
※坂崎かおる「リモート」は、2024年に河出書房新社から刊行された短編集、坂崎かおる『嘘つき姫』に再録されています。