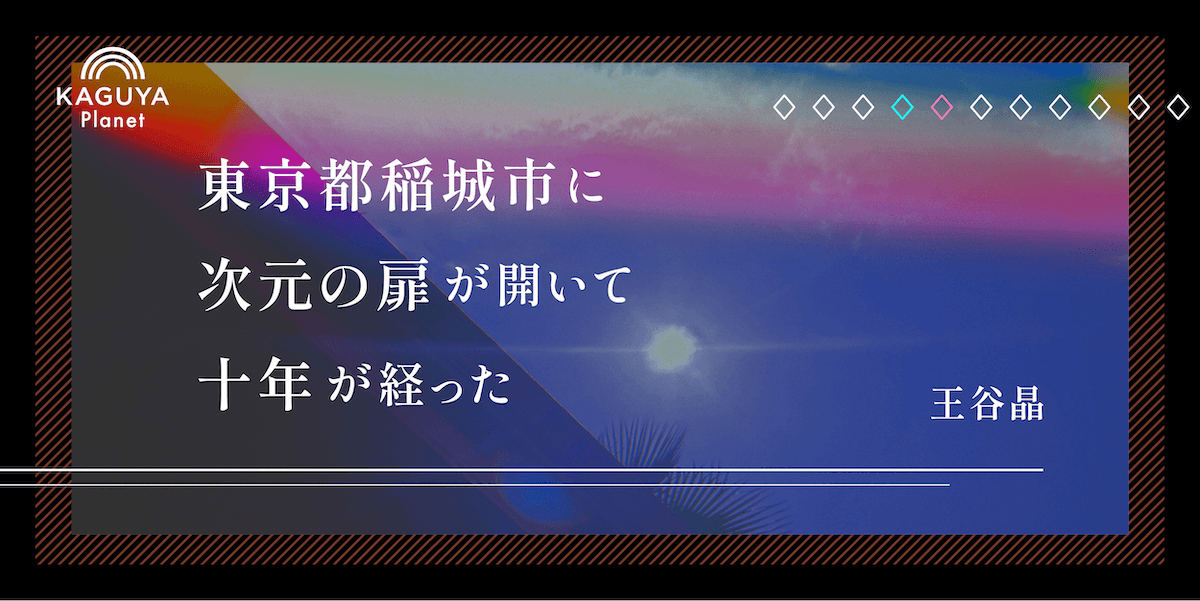先行公開日:2023.5.27 一般公開日:2023.6.17
王谷晶「東京都稲城市に次元の扉が開いて十年が経った」
7,551字
寮から職場まではのんびり歩くと十分くらいかかってしまう。自転車に乗っている同僚もいるくらいだ。ヒロシは急いでいた。寝坊をした。ほぼ部屋着のまま従業員しか通らない裏道を走るその顔を、建ち並ぶ色鮮やかな透明のビルを通過した太陽の光が青、オレンジ、緑、ピンクなどに染めていく。
従業員通用口から中に入り、ロッカールームで急いで制服に着替える。制服というか作業着と言ったほうがいいようなそっけないツナギに、これまた農協のおっちゃんが被っているようなそっけないキャップを被る。テーマパークの従業員というと派手なコスチュームを思い浮かべるが、こういう格好のほうがかれらにウケがいいのだと教わった。
名札を付け、翻訳用のタブレットが充電されているか確認し、同じシフトの数人と会釈で挨拶しながら外に出る。あと少しで開場されるゲートの前にはすでに観客が並んでいて、ヒロシたち従業員が姿を現すとその波が一斉に上下左右に揺れた。
『本日は未来シアターINAGIにお越しいただきまことにありがとうございます。只今から開場のお時間となります。会場内は走らず、係員の誘導に従ってゆっくりお進みください』
三割くらいいる人間の観客に向けていくつかの言語で案内が読み上げられると、ゲートが開いた。色とりどりの観客たちが、いっせいにぽよぽよと揺れながら敷地に入ってくる。ヒロシは自分のほうにまっすぐ、鮮やかな緑と黄色をした観客が二名やってくるのに気づいた。
二人は共に富士山のような形をしており、大きさはヒロシの背より少し高い。上下に小刻みに揺れながら、その透明の身体の中に気泡をいっぱいに飛ばしている。すかさずヒロシが翻訳タブレットをかざすと、
『わたしたちさっき到着しました! イナギは初めて! あなたは人間ですよね?』
と、アプリが翻訳した言語を音声で読み上げる。ヒロシはにっこり笑って
「そうです。稲城市へようこそ。どうぞ楽しんでいってください」
と言う。二人はさらに身体を弾ませながら、
『あなたはスタンダードな人間? この世界の一般的な生物?』
と訊いてきた。ヒロシはほんのわずか、ほんの一瞬間を置いて、
「はい。私はこの地球に住む一般的な人間です。名前はヒロシと言います。よろしくお願いします」
と伝えた。
東京都稲城市に次元の扉が開いて十年が経った。
都心から離れた多摩川沿いの緑豊かな街は、今や東洋一とも称される芸術的な高層ビルが建ち並ぶメガロポリスと化した。そのほとんどが、次元の扉の向こうからやってきたゼリー人間の高度な技術によって設計・建築されている。
ゼリー人間は稲城ゲート(正式名称は東京都外部次元間特別連絡口)が通じている別次元にある地球に生息する、最も高知能な生物だ。当初、ゼリー人間たちの容姿――体長100から200センチメートル、主に円錐台様の透明で柔軟な肉体、個体別に高彩度の体色を持ち、四肢は無く、視覚や聴覚はあるが目・耳・鼻・口等の器官は外部から視認できる形態ではない――つまり、巨大なゼリーとしか言いようのない姿に、こちらの地球の人間はパニックを起こし、関係に緊張が走る一幕もあった。しかしやがていくつかの共通点をみとめることで、官民交えての積極的な交流が始まった。
まず、ゼリー人間は言語を使ってコミュニケーションを行う。
こちらの人類は視覚、聴覚、触覚などを利用してコミュニケーションをはかるが、ゼリー人間は大部分を視覚に頼る方式で会話している。それは主にかれらの透明な体内に浮かび上がる気泡と身体全体の振動具合で表現される。下から上へと立ち上る気泡の大きさ、数、量などを視認することで、ゼリー人間は高度な意思疎通を行っている。
稲城ゲートが開いて間もなく、多数の言語学者やスーパーコンピューターによるシミュレーションを用いて、猛スピードで互いの言語の翻訳AIがプログラムされた。その結果、ゼリー人間側は小型のモニター付きヘッドセット様の翻訳機を身に着けることで、こちらの人間も専用アプリを入れたタブレット等を携帯することで、両者のコミュニケーションは当初の予想よりもはるかにスムーズに行われるようになった。
藤沢ヒロシは稲城市内の観光施設で働く二十九歳の人間だ。稲城で生まれ、大学の六年間だけ練馬区の富士見台で暮らし、また稲城に戻ってきた。
祖父がJR稲城長沼駅近くに小さな土地を持っていたため、ヒロシ以外の家族は立ち退き料で都心に引っ越した。ヒロシだけが稲城に残り、かつてよみうりランドと呼ばれていた施設の従業員宿舎で生活している。
青色の味気ない作業着姿で、ヒロシは「未来シアターINAGI」の敷地をぶらぶらと歩く。英語と日本語、それから気泡を閉じ込めたアクリル板のプレートで「案内係」と書いてある名札を胸に付けている。ゼリー人間だけでなくこちらの地球の外国人観光客も数多く訪れる施設だが、ヒロシが喋ることができるのは日本語だけで、あとは肌見放さず持っている業務用のタブレットが頼りだ。トイレやレストランの場所であったり、アトラクションやシアターの内容を案内する。正直、シンプルな機能のロボットでもできる仕事であり、ロボットのほうがうまくできる仕事ですらある。
それでもヒロシのような人間が雇われている理由は、この施設の主な顧客層であるゼリー人間たちが「現地人たちとの交流」を求めているからだ。
ゼリー人間たちの性質はきわめて穏やかかつ理知的で、さらに好奇心が強く、社交的だ。かれらはこちらの地球人とコミュニケーションをとることに熱狂しているようだった。毎日毎時、次元の扉からはひきもきらずに観光目的のゼリー人間たちがやってくる。かれらはゲート前で出迎える揃いの制服を着た職員たちに歓声をあげ(音声はほとんど発しないが)、なんということのない挨拶のやりとりに感動し、その弾力のある身体を上下左右に揺らしている。
たぶん。ヒロシは職場の隅でぼんやり突っ立ったまま考える。たぶん、ゼリー人間にとってこっちの人間は、猿とか犬とか猫が服を着て喋ってるような感覚なのだろうな。それは面白いし、興奮するよな。『ズートピア』とか『オッドタクシー』の世界に飛び込んだみたいなものだ。そりゃあはしゃぐ。
ヒロシはすっかり様変わりした生まれ故郷の姿を眺めている。子供の頃はよく遊びに来ていたこの遊園地も、昔の面影はほぼ無い(ゼリー人間の文化にジェットコースターは無かった。拷問器具の一種とみなされ強い拒否反応を受けた)。よく祖母に連れて行ってもらった長沼のグルメシティももう無い。スカイツリーよりも遥かに高い、輝く透明の塔のようなビルが畑だらけだった土地ににょきにょきと生え、毎週のように海外から何かの偉い人がやって来るし、ハリウッドセレブも来るし、反ゼリー人間デモみたいなのもしょっちゅうあるし、たった十年でまるきり知らない土地のような、騒々しい街になってしまった。
それでもヒロシが稲城に残ろうと思ったのは、他ならないこの職場、「未来シアターINAGI」があるからだ。
ゼリー人間の世界とこちらの世界の大きな共通点は、両方の文化に演劇があることだった。
こちらでいう映画やドラマもそれなりに発展はしているらしいが、何よりも生の舞台、ライブで行う演劇が非常にさかんなのだという。そこで文化的交流の礎として、よみうりランド敷地に巨大な複合劇場が建設され、ゼリー人間やこちらの人間の各種舞台芸術がほぼ毎日上演される運びとなった。
ヒロシはここで、ゼリー人間の演劇を観た。主演はジェロ・ブラックチェリー(かれらの名前をこちらの言葉に翻訳することは非常に困難だが、翻訳AIはその語句を選んだ)という、あちらでは非常に高名だという舞台俳優で、その黒に近い赤褐色の大きな身体を震わせ、円形のステージにゆっくりと現れたときの“オーラ”は今でも覚えている。威厳があり、同時に引き込まれるような親近感があった。共演者の小柄な薄いブルーのゼリー人間と共に、ジェロ・ブラックチェリーはスポットライトでさまざまな角度から照らす演出に合わせ、身体の中に気泡をいくつも浮かび上がらせ、時にゆったりと、時に激しく、舞台の上でぷるぷると震え続けていた。
もちろん、その舞台が何を表現しているのか、その時のヒロシには見ただけではまったく分からなかった。歌舞伎のイヤホンガイドと同じ形式の音声解説を聴きながらの鑑賞だったが、大きなゼリーがぷるぷるしているその仕草から、太古の昔のゼリー世界で起こった破壊と再生の歴史ロマンを読み取ることはできなかった。でも、ヒロシはその演劇をとても楽しんだ。すごいと思った。感動した。すごくよかった。演劇に感動するのは、久しぶりのことだった。
作業着に包まれた身体でひそかにのびをする。健康そのもので、毎日よく眠れるしご飯も美味しい。これまで自分の身体や体調に不満を持つことはほとんど無かった。しかしゼリー人間が現れてから、ヒロシはどうしても「自分もゼリー人間だったら」という考えが止められない。正確には、ゼリー人間の役者になれたらいいのに、という願望だ。それくらい、ゼリー人間の演劇は面白かった。最初はただぷるぷるしているだけに見えていた役者の動きも、いくつも舞台を見ればそのボディランゲージ的意味合いが読み取れるようになっていく。喜びも悲しみも、苦痛も笑いも、全ては気泡と振動で表される。自分もあんなことができたら。
稲城に戻る前、ヒロシは役者をやっていた。かつては演じることが確かに好きだったが、実は、今はもうどうなのか分からない。ヒロシは体力があったし、声もよく通るし、台詞を覚えるのも早かったし、トラブルにも臨機応変に対応できるタイプだった。それは舞台俳優に向いている素質のはずだった。でもだんだん、どんな役を演じても「これは違う」という奇妙な肌感覚が付きまとい、演技に集中できなくなってしまったのだ。それはヒロシ自身だけでなく、ヒロシの演技を見た人たちも感じた違和感らしかった。
これまで演じてきたのは、ヒロインに執着して横恋慕する若い男、妻の友人と不倫する中年男、長年連れ添った妻を亡くした農村の老人、同級生にひそかに恋するゲイの青年、などなど。脚本が悪かったのか? 演出が悪かったのか? 自分が悪かったのか? いくら考えても答えは出ない。思う所があり、男性だけであらゆる年代・ジェンダーの役柄を演じる劇団に参加してみたこともあった。そこのワークショップでヒロシは家族関係に悩む若い女性やパート先の社員をいじめる主婦などを演じたが、そこでも反応は似たようなものだった。なんだかピンとこない。君はいったい誰なんだ?
ヒロシは、最初自分が「男」を演じることができないような気がして、もしかして自分は「女」を演じたいと思ってるのかなと考えた。しかし「女」を演じることも同様にしっくり来なかったし、うまくできなかったし、誰かに感銘を与えることもできなかった。ヒロシの演技は見る者を不安にさせるらしかった。演出家に決まって言われたのは、「君が何をしたいのかわかんないよ」という言葉だった。
別人を演じるのが芝居なのに、その別人を演じることに違和感を感じるのはおかしな話だとヒロシは思った。つまり自分は何にも、誰にもなれないのだ。役者に向いていない。そう判断し、富士見台のアパートを引き払った。
昼の休憩時間になり、ヒロシは別の案内係と交代してバックヤードに下がった。寮の小さい台所ではたいした料理もできないので、昼食はいつもコンビニの弁当かおにぎりだ。屋内の休憩所はいつでも使えるが、天気もいいので外で食べることにする。
従業員用の駐車場の隅にあるベンチに座り、ヒロシはまだ開発が進んでいない長閑な川崎市側の風景を眺める。いずれこのがらんとした空もカラフルな塔に埋め尽くされるのだろう。都心もゼリー人間がもたらした技術と文化により、だいぶ様変わりしたと聞いている。
そのとき、視界の隅に、何か明るい赤色のものが入り込んだ。
振り向くと、そこにひとりのゼリー人間が居た。150センチほどの体長で、全身に均一に畝のでこぼこが付いたかたちをしている。俗にクグロフ型ゼリー人間と呼ばれているタイプだ。お客が迷い込んできてしまったのか。ヒロシはおにぎりを置いて立ち上がりそのゼリー人間に近付いた。
「何かお困りですか」
タブレットを片手に声をかけると、赤色のゼリー人間はぼよん、と横揺れをした。
『いえ、特には』
ヒロシのタブレットが機械合成音を吐き出す。
「あの、ここは従業員しか入れないゾーンなんです」
そう言うと、ゼリー人間は身体をぐるりと回転させ、側面に貼り付けてあったスタッフパスをヒロシに見せた。ということは、このゼリー人間はゼリー人間演劇の関係者なのか。
「失礼しました。でも、こんな所で何を……?」
『練習できる場所を探しています』
ゼリー人間の体内に気泡が浮かび上がる。
『私は役者です。ソワレの出番までに少しでも練習をしておきたい』
真っ赤な身体が上下にぽよぽよと快活に揺れた。やる気がみなぎっているという感じの動きだ。しかし、ヒロシはこのゼリー人間に見覚えが無かった。
数年ここで働けば、ゼリー人間俳優のことは嫌でも知識が増えていく。大御所のブラックチェリーの公演はめったに無いが、スタンダップコメディアン的な存在のオレンジソーダや人気急上昇中の若手俳優キーライムなどは、テレビにもよく出ていてこちらの人間のファンも多い。クランベリーやアップルミントも常連役者だ。でも、このクグロフ型の真っ赤な役者は今まで見たことがなかった。
『初舞台なのです』
ヒロシの視線に気付いたのか、ゼリー人間はそう言った。
『絶対に失敗できない!』
上下に何度も揺れるその身体は、もしかして緊張しているのかもしれないとヒロシは思った。
「あの」
小刻みに揺れるその役者に向けて、ヒロシはためらいがちに声を発した。
「自分に、何か手伝えることはありますか」
『あなたが?』
意外な言葉だったのか、ゼリー人間はぴたりと動きを止めた。
「いや、あの、自分も少し前に役者をしていて」
『ほう!』
畝のある身体が再び揺れた。
『今はやってないのですか?』
「はい、辞めています」
ゼリー人間はしばし沈黙し、それからゆっくりと左右に揺れはじめた。
『役者は、一日やったらもう一生やめることはできない』
「はあ」
『私たちの世界にある格言です』
こっちにも確か似たような格言がありますよ、とヒロシは言おうと思ったが、詳しくは思い出せなかったので黙った。
『あなたは演じることのなんたるかを知っているわけだ』
「いやあ……それはどうですかね」
『私の演技を見てほしい。今日は絶対に失敗できないのです』
ふたたび上下に揺れながら、ゼリー人間はヒロシにぐぐっと近付いた。
『ぜひ見て、感想をお願いしたい』
ゼリー人間は準備運動のようにゆっくり左右に揺れてから、一度大きく伸び上がり、そしてその赤く透明な体内にひときわ大きな気泡を生み出した。
『もはや、お湯は沸いてしまったのですよ!』
翻訳タブレットはそんな言葉を発した。
『もはや、お湯は沸いてしまったのですよ!』
もう一度。
『もはや、お湯は沸いてしまったのですよ!』
もう一度。
「あの、台詞はこれだけですか」
このまま何度でも繰り返しそうな気配があったのでそう訊くと、ゼリー人間はぴくっとわずかに震えた。
『そうです。しかし重要な台詞です。この一言を受けてあの有名な『ならばあとは蒸されるだけだ』のシーンが始まるのです。この台詞でどれだけ緊張感を高められるかが肝心なのです』
「ならばあとは蒸されるだけだ……」
『おっ。お上手! そうだ、掛け合いをしてください。こう、ゆうっくりと、円を描くように揺れながら』
ゼリー人間が大きく身体を動かす。ヒロシは思わず、それを真似て上半身をぐるぐると回してしまった。
『素晴らしい。では私の台詞に続いてください。――もはや、お湯は沸いてしまったのですよ!』
「ええと――“ならばあとは蒸されるだけだ”……?」
『もっと力強く! かのサワーレモンの名台詞ですよ! もう一度!――もはや、お湯は沸いてしまったのですよ!』
ゼリー人間の赤い身体が天に向かってぐうっと伸びる。ヒロシはまだ衰えきってはいなかった体幹でもって上半身を回しながら、腹から声を出した。
「ならば、あとは蒸されるだけだ!」
『もはや、お湯は沸いてしまったのですよ!』
「ならば、あとは蒸されるだけだ!」
ヒロシは繰り返した。太陽の光がゼリー人間の身体を通り抜け、赤く染まった光線がヒロシの身体に降り注ぐ。青い作業着が赤い光に照らされて、ブルーベリーのような紫色になった。
同じ台詞を、同じ動きを繰り返すうちに、ヒロシはあれっと思った。
自分はいま、何を演じているのだろう。
演目は分からないが、おそらくサワーレモンという役名で、それはゼリーの姿をしているはずだ。手足と毛の生えた不透明の縦長の肉体である自分とは似ても似つかない存在を演じているはずだ。でも、あれだけヒロシを苛んだ違和感が、いまはどこにも無かった。
『もはや、お湯は沸いてしまったのですよ!』
「あのう」
『なんですか。急に中断しないでください』
「ごめんなさい、ちょっと気になって……あの、自分のやっている役は男性ですか、女性ですか」
ゼリー人間は身体のてっぺんのあたりをぷるんと揺すった。
『知らないのですか。我々にはそちらでいう性別というものは無いのですよ』
「はあ」
『こちらに来るにあたって私も勉強しましたが、その性別というやつ、理屈は理解しても正直さっぱりわかりません。そちらの演劇もそのせいで筋を追うのがなかなかむつかしい。興味深いですが』
ゼリー人間たちの目から、自分たちこの地球の人間がどれだけ奇妙な生き物に見えているのか、ヒロシは想像してみた。それはこちらがゼリー人間を見る目と同じくらい、奇異と僅かな見下しが含まれているのだろう。でも。
『あなたがたと私たちで同じ舞台に立って演じたら、面白いでしょうねえ』
ぷるぷると横方向に小刻みに揺れながら、ゼリー人間は言った。
「成立するでしょうか。芝居として」
『できますよ。だって私たち、もう一緒に演技してる』
ぽこぽこと気泡が立ち上がる。何の迷いもない言葉だった。
「できますかね」
『できますとも』
ヒロシは紫色になったまま、自信たっぷりにあざやかに赤く輝く役者を見つめた。自然と自分が笑顔になっているのが分かった。この表情は、どう翻訳されるのだろう。でもお互いこの不格好な機械を通さなくても、何か伝えあえるものはあるはずだ、きっと。そう思って、もう一度上半身をぐるぐると回した。